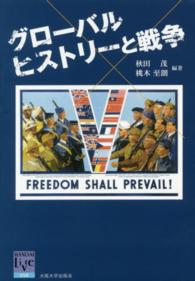内容説明
「書く」ことと、印刷およびエレクトロニクスの技術が、ひとびとの精神、文学、社会のうえにどのように影響を及ぼすか。本書は、文学と思考のなかにごく最近まで重く沈澱していた声の名残りをあとづけ、知的興奮をさそう新しい発見をとりあげる。その発見は、ホメロスの詩や現代のアフリカの叙事詩、およびその他の世界中の口承文芸に関するわれわれの理解を書き改め、哲学的、科学的な抽象思考の発生に関する新しい洞察を与えてくれる。
目次
第1章 声としてのことば
第2章 近代における一次的な声の文化の発見
第3章 声の文化の心理的力学
第4章 書くことは意識の構造を変える
第5章 印刷、空間、閉じられたテクスト
第6章 声の文化に特有な記憶、話のすじ、登場人物の性格
第7章 いくつかの定理(応用)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
69
我々は《声の文化に属する人々にとって言葉がどういうものだったか想像できなくなっている》。パリーはホメロスの語形が韻律のためにのみ選ばれている事から、それが記憶によってうけつがれる声の文化の産物であると述べた。例えば声の文化と文字の文化の境に立つプラトンは、彼の国家から詩人を排除しつつも、書く行為を非人間的なものと考え葛藤したという。ならば紫式部も…物語を語る自らの場そのものを「書く」という離れ技を演じたあの紫式部も…その個人的な営みにはやはり葛藤があったろうと思う。優れた作品は文化的葛藤から生まれるのだ。2018/02/01
ハチアカデミー
20
A 文字の影響下に生きる現代人のメカニクス! 現在の人間の思考や行動が如何に文字の影響を受けているのかを、声の文化との対比によって思考する刺激的な名著。声の文化は状況依存的な思考をするが、文字は抽象的な思考を可能にする。その変化によって、現実の認識も、さらに言えば自我の認識すらも変わってしまうことが、実例を挙げながら考察されてゆく。また、文字だけでなく、印刷技術の影響も言及。民俗的差異だけでなく、『ホメロス』から『ユリシーズ』まで、古今の文学作品も例に挙げられる。文明論、メディア論、文学論として一級品!2012/06/07
サアベドラ
18
orality&literacy研究の古典。著者のオングはもともとは16世紀の人文主義者ペトルス・ラムスを専門とする文献学者。文字を持たない文化(=声の文化)で語られた叙事詩や口頭伝承と、文字を持つ文化(=文字の文化)で書かれた悲劇や小説などとの叙述スタイルを比較することにより、文字が人間の心性をどのように変化させ、現代の思考の型の形成に寄与したかを説く。文字を操る現代人の無意識の部分に切り込む、刺激的な研究。この研究をどうやって史的文脈に落としこむかが、われわれ歴史を研究する者の課題の一つとなっている。2014/02/08
風に吹かれて
15
1982年刊行、1991年訳本刊行。文字のない「一次的な声」の文化と文字を使う文化。声の文化は相手があってこその発話が行われるので集団的であるのに対し文字の文化は書くこと読むことが自分自身に跳ね返り孤独ではあるけど思考を深め、また詳細な記録を残せることから科学の発展にもつながった。文字がなければ現在の生活はなかった。文字が哲学をどのように導いたか等課題はまだまだ多いようだ。ネットが広がり、やり取りがすぐにできる文字の世界が新たな「声の文化」として現出している今日、文字について改めて考えるべきかもしれない。2019/08/16
てれまこし
9
文字に親しんだわれらには声の文化に生きた人がどのように思考したかもはや想像しがたい。そして文字が普及した今日においても、多くの人はまだ完全に文字の文化を身につけていない。そう考えると、柳田国男が読み書きを知らない人々の文化を言語化しようとした政治的意味も理解できる。近代的な教育により人々は声の文化から引き抜かれる。だが文字の文化を体得するには至らない。近代社会で彼らは公共圏から締め出され、彼らを理解しない人間に代表されることを余儀なくされる。それが真の民主化を妨げる。民俗学はこの民主化の赤字を埋めるもの。2020/02/12