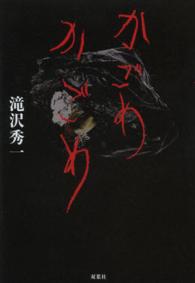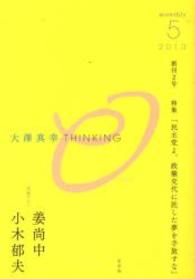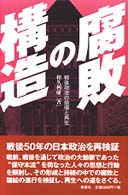内容説明
今も、世の中では、子どもの自殺が続き、少年事件がマスコミを騒がせている。では、われわれは、現代の子どものために、何ができるのか。学校や社会は、どうあるべきなのか。それについて、本書では考えている。
目次
おなかが痛い、頭が痛いと言って、登校をしぶる男の子は、やがて全く学校に行かなくなった
こんなけんかばっかりの家で、病気にならないほうがおかしいよ
子どもは、家族みんなの苦しみを癒す大きな力を持っている
子どもにいろんな症状が起きる原因は、一つしかない。それは、周囲とのパイプの詰まり
学校で「いつも無表情で笑顔がない」そんな子どもは、大きな問題を抱えている可能性がある
大人の認識が甘すぎる!体罰は、子どもの発達に悪影響を与える
甘えるのが下手な子、我慢している子には、親の愛情がうまく伝わらない
「心の鎧」を着ている大人は、子どもの甘えをはねつけてしまう
「この子は、何を考えているか分からない」―親子の心の結びつきが生じにくいアスペルガー症候群
子どもの症状に応じて知っておかねばならない五段階の対処法〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
25
いただいた本。前書きがとても悲しかったですが、地味でもまっすぐにやさしく同じことを訴える著者の姿勢がとても好きです。水曜日は校庭公開の日で我が家に娘がだれでも連れてきていい日。たくさんの子たちが来て、校庭やほかの友人の家を行ったり来たり。泣いたり、けんかしたり、怒ったり。でも親が出るまでもなく、子どもたちでずいぶん解決できるようになってきました。でも…三年生にとって友達って本当に大切になってきているんだなあ…。2020/12/24
manya
3
今の世の中、子供達には住みにくい世の中になってしまった気がする。そんな中で、我々大人の出来る事は何だろう?家族だから信じてあげて、居場所を作ってあげようと思う。
Azusa_F
2
明橋先生の言葉は、いつも不思議と柔らかで優しくて、それでいて本質をしっかり見てくれているようで、そういう意味では本当にほっとする。「パイプ詰まり」という言葉を日々意識していかないと、いつか子供も私自身も「詰まって」しまうんだろうなあ。2013/08/03
ジャッキー
1
子供と親、子供と学校のいずれか、もしくは両方のパイプが詰まっている場合にどうにかしようともがく。それが反抗期なのかもしれない。しかも、パイプは変形したりもする。パイプを通すために何ができるのかを考えるのが親や学校の務めなのかもしれない。2015/10/25
s2013253
1
(A)「輝ける子」「がんばってる子」と同様、非常に示唆に富んだ本である。体罰に対する大人の認識の甘さなども指摘されている。子どもを育てている人なら前二冊とあわせて読んでおいて損のない本だと思う。2014/08/17