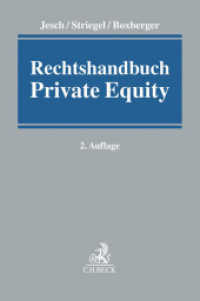内容説明
稀代の読み手は何を読み、思考して来たのか―。朝日新聞掲載(2005‐2017年)の書評107本を全収録。1960年代から80年代にかけて執筆された書評、文芸時評、作家論、文庫解説、全集解説など、著者自筆単行本未収録論文を約51本収録。
目次
第1部
第2部
第3部
著者等紹介
柄谷行人[カラタニコウジン]
1941年兵庫県尼崎市生まれ。東京大学経済学部卒業。英文科修士課程修了。1969年、夏目漱石論により群像新人賞を受賞。以来、文学、哲学、歴史学など幅広い分野をまたぐ著述活動を展開。法政大学教授、近畿大学教授、コロンビア大学客員教授を歴任。90年から2002年まで『批評空間』を編集。2005年より朝日新聞書評委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Happy Like a Honeybee
7
柄谷氏の書評集は珍しいと思ったら、一冊の本としては初めてだったようだ。 大岡昇平や坂口安吾をもっと読むべきと痛感。 思想と読書量は比例するとの印象を受けた。 自分のような一介の労働者にこそ、世の中を渡り歩く良書が必要だ。2018/03/11
渡邊利道
5
2000年代の朝日新聞紙上での書評、60-80年代の書評、文芸時評、そして全集や文庫などの解説の三部構成。ざっと見ると、90年代に断絶があり、それ以前が作家の内面にあるモチーフが、人間の構造的な「実存性」を写し出し作品として現出するという感じで、社会反映論的なものを拒絶して一種の抽象性を求めているのに対し、以後ではもっと大きな歴史の結節点として作品を見ている。これが作者いうところの「病気が治った」ということなのだろうが、この場合どうしてもやはり病者の光学の方に魅力を感じる。2017/12/10
ピラックマ
3
大ボリュームだが、数頁の書評や解説集で体力使わず楽しめる。毎夜寝る前に1本づつじっくり2ヶ月楽しみました。文学論集もそうだったが文藝批評家としての柄谷氏の文章はどれも熱く圧巻の展開である。吉本隆明への若い頃の憧れとの反駁のようなものがない交ぜになった”言語にとって”への解説が印象に残った。2018/02/03
りゃーん
3
柄谷行人が、私が好む武田泰淳「富士」と古山高麗雄「湯たんぽにビールを入れて」という傑作を絶賛して嬉しかったし、逆に、スゴいんだろうが、よく意味が判らない、坂上弘や小川国夫のスゴさを解説する手際は神技クラス。例えば、今、島本理生や綿矢りさの文学的意義を解説して面白い批評家がいるのか?現代の前衛と云われる中原昌也や木下古栗の難解さを平易に説明できる批評家がいた試しもない。奇をてらって仮面ライダーや地下アイドルを論じるだけで、こういう時評・書評で面白いものを書ける批評家が既にいないのだと本書を読んで呆然とした。2018/01/15
yoyogi kazuo
1
元妻の冥王まさ子の文庫解説が読める。あと70年頃の文芸批評であちこちに喧嘩腰なのが読める。21世紀に入ってからの朝日の書評は気の抜けたビールみたいなもの。せめて東浩紀の本でも取り上げる元気もなかったか。2024/05/25
-
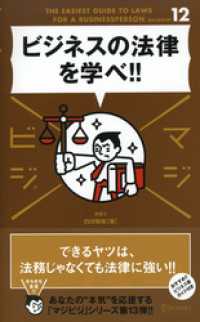
- 電子書籍
- ビジネスの法律を学べ!!(マジビジ)