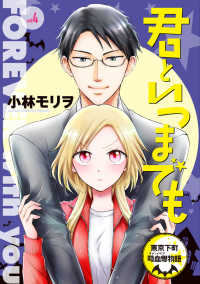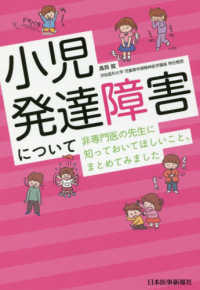出版社内容情報
<第5次水質総量規制対応>
法規制強化に即応した食品製造責任者・環境管理担当者必携の技術書!
実務ポイントを図表などを多用し、分かりやすく簡潔に解説しました。
■ 主要構成
序章 食品工場の排水処理をめぐる法規制の動向と今後の対応策
第1部 食品工場における生物処理プロセスの必須事項
第1章 生物処理の特性
第2章 排水処理システム導入における留意点
第3章 排水処理設備の運転管理上の問題点と対策
第4章 汚泥処理・減容化技術
第2部 法規制に対応した新排水処理方式と資源循環型への転換
第1章 第5次水質総量規制の概要
第2章 法規制の強化に対応する排水処理技術
第3章 下水道放流基準への適合化技術
第4章 排水・廃棄物の再利用技術
第3部 排水処理設備の最適管理を目指して
第1章 各種食品工場に見る排水処理設備の実際と運転管理への取り組み
第2章 バルキングの診断および対策の実際
第3章 生産能力強化に伴う汚濁負荷量増加への対策技術
終章 21世紀の環境低負荷・資源循環型社会構築の課題と展望
■ 内容目次
序章 食品工場の排水処理をめぐる法規制の動向と今後の対応策<稲森悠平/小沼和博>
1.第5次水質総量規制におけるCODに加え窒素・リンの追加された背景と意義
2.事業場系排水としての重要な食品工場の排水の規制方向と対策技術のあり方
3.窒素・リンの負荷削減における除去と同時に回収・資源化を考慮した技術の重要性
4.窒素・リン対策のこれからの方向性
第1部 食品工場における生物処理プロセスの必須事項
第1章 生物処理の特性
第1節 好気性処理の基本事項<佐野和生>
1.微生物叢と排水の性質
2.浄化微生物叢の形態
3.微生物の生長
4.発育に影響を与える物理的条件
5.有毒物
6.微生物の生長と排水処理の関係
7.細菌のフロック化
8.細菌と栄養
9.細胞質の形成と酸化
10.酸素の必要性
11.曝気槽内酸素濃度と汚泥発生量の関係
12.細菌のエネルギー代謝形態
13.有機物の分解経路
14.懸濁性生物処理における問題
14.1 バルキング現象
14.2 栄養気質と水温変化
14.3 硝化および脱窒素細菌
15.排水処理設備設計における留意事項
15.1 排水の特性
15.2 調整槽
15.3 排水処理法の組立て
15.4 発生汚泥の減少化
16.生物処理でのバイオマスの管理
17.酸素の供給
第2節 嫌気性処理の基本事項<宝月章彦>
1.反応のメカニズムと特長
2.反応速度
3.生物学的エネルギー効率
4.余剰汚泥発生
5.必要栄養塩
6.メタン生成菌
6.1 至適pH
6.2 メタン菌の形態
7.硫酸塩還元菌
8.基質の分解性
9.処理方式
9.1 温度
9.2 相分離
9.3 菌体の保持
10.排水処理における嫌気性処理の位置付け
10.1 省エネ・省資源型設備として
10.2 増設・増産対応設備として
10.3 下水放流の除害設備として
第3節 好気性/嫌気性複合処理の基本事項<曽我和雄>
1.食品工場排水の特徴
2.排水処理技術
2.1 調整槽、前処理設備
2.2 嫌気性処理法(UASB法、EGSB法)
2.3 好気性処理法
2.4 高速型凝集沈澱法
2.5 汚泥処理
第2章 排水処理システム導入における留意点
第1節 排水処理システム導入に伴う生産プロセスの再検討<中島 淳>
1.生産プロセスにおける対策の概要
1.1 生産プロセスにおける対策の重要性
1.2 生産プロセスにおける対策の分類
1.3 対策策定のための実態把握
2.インプット対策の策定とそのための実態把握
2.1 インプットアウトプットモデル
2.2 インプットの把握
2.3 アウトプットおよび既存排水処理の再認識
2.4 大まかな戦略の検討
2.5 計算の事例
2.6 インプット対策の実際
3.プロセス対策の策定とそのための実態把握
3.1 生産プロセスにおける水使用と排水発生
3.2 前処理プロセスでのCOD・窒素・リン対策
3.3 加工プロセスでのCOD・窒素・リン対策
3.4 仕上げプロセスでのCOD・窒素・リン対策
3.5 機械器具・作業上洗浄のCOD・窒素・リン対策
4.生産プロセス対策と排水処理対策
第2節 食品原料と汚濁負荷状態による排水処理プロセスの選択<中畑繁夫>
1.排水処理プロセスの選択の考慮すべき事項
2.排水処理施設の構成
2.1 前処理工程
2.2 生物処理工程
2.3 高度処理工程
2.4 汚泥の処理・処分
3.前処理プロセス
3.1 夾雑物の除去
3.2 pH調整
3.3 油分の除去
4.好気性処理プロセス
4.1 活性汚泥法
4.2 生物膜法
4.3 生物学的硝化脱窒および生物学的硝化脱窒・脱リン法
5.嫌気性処理法
5.1 嫌気性ろ床法
5.2 嫌気性流動床
5.3 UASB法
6.嫌気・好気複合処理法
第3章 排水処理設備の運転管理上の問題点と対策
第1節 好気性処理設備<村中雄一>
1.膜状生物処理設備
1.1 膜状生物処理設備の特徴
1.2 膜状生物処理設備の運転管理
1.3 膜状生物処理設備の処理悪化の原因と対策
2.懸濁状生物処理設備
2.1 懸濁状生物処理設備の特徴
2.2 懸濁状生物処理設備の運転管理
2.3 懸濁状生物処理設備の処理悪化の原因と対策
3.管理項目
3.1 共通項目
3.2 膜状生物処理設備における保持生物量
3.3 懸濁状生物処理設備
第2節 嫌気処理設備<高村義郎/塩田憲明>
1.嫌気処理プロセスの分類と特徴
1.1 リアクター形式と処理特性
1.2 生物膜と懸濁グラニュール
2.嫌気処理の運転管理
2.1 最適処理のための留意点
2.2 運転パラメータとモニタリング方法
3.固定床とUASB運転の知見
3.1 固定床法
3.2 UASB法
3.3 固定床法とUASB法の比較
第3節 好気性/嫌気性複合処理設備
1)グラニュール式発酵と活性汚泥<曽我和雄>
1.グラニュール式発酵の運転管理上の問題点と対策
1.1 嫌気性処理における有機物の分解
1.2 嫌気性処理の環境要因
2.活性汚泥の運転管理上の問題点と対策
2.1 活性汚泥法の原理
2.2 活性汚泥の管理
2)固定床式嫌気性処理と活性汚泥<高村義郎/宮本 武>
1.処理のプロセスの特徴
1.1 嫌気性処理と好気性処理
1.2 固定床式嫌気性処理
2.運転管理上の問題点と対策
2.1 固定床式嫌気性処理の運転上の問題点と対策
2.2 活性汚泥の運転上の問題点と対策
第4章 汚泥処理・減容化技術
第1節 余剰汚泥処理プロセス設計<丹野健一>
1.余剰汚泥とは
1.1 発生機構
1.2 余剰汚泥の性状および特徴
1.3 余剰汚泥の処理計画について
1.4 余剰汚泥の処理方法
2.脱水処理
2.1 脱水処理の意義
2.2 脱水処理に必要な機器・薬剤
2.3 脱水機の種類
2.4 前処理工程(凝集工程)
2.5 凝集剤
2.6 凝集作用
2.7 各種脱水機に対する凝集方法
2.8 スクリュープレスCPHS型の適用による余剰汚泥処理
3.汚泥減容化処理技術
3.1 基本原理
3.2 可容化方法の種類
3.3 汚泥減用処理の具体例
第2節 汚泥処理<寺谷直也>
1.脱水方法
1.1 脱水の目的
1.2 食品工場排水汚泥の特徴
1.3 凝集剤の利用と効果
1.4 脱水機の種類と特徴
2.脱水汚泥の処理
2.1 乾燥
2.2 焼却
2.3 コンポスト化
2.4 その他の汚泥有効利用
第3節 減容化プロセス
1)好熱菌による汚泥消滅プロセス<赤司 昭/長谷川 進/宝月章彦>
1.既存の余剰汚泥減量化技術
2.エステプロセス
2.1 エステプロセスの概要
2.2 エステプロセスの原理
3.実施例
3.1 室内実験
3.2 パイロットテスト
4.経済性
4.1 算出基準
4.1 運転費
5.受注実績
2)オゾンを用いた汚泥減量プロセス<西村総介>
1.余剰汚泥処分の現状
2.現実的選択としての汚泥減量プロセス
3.汚泥減量プロセスの仕組み
4.オゾン法の原理
4.1 オゾン処理による汚泥性状の変化
4.2 オゾン法の装置構成
4.3 オゾン法の特長
5.オゾン法の適用実績
6.適用評価方法
6.1 シミュレーションによる設計方法
6.2 硝化脱窒法への適用
7.オゾン法適用に当たっての留意点
8.高温消化オゾン法について
第2部 法規制に対応した新排水処理方式と資源循環型への転換
第1章 第5次水質総量規制の概要<荒木智行>
1.経緯
2.在り方答申の概要
2.1 水質総量規制の実施状況などについて
2.2 第5次水質総量規制の在り方について
3.総量規制基準の設定方法などについて
4.基準等答申の概要
4.1 基本的考え方
4.2 CODの総量規制基準
4.3 窒素およびリンの総量規制基準
4.4 窒素およびリンの汚泥負荷量の測定方法など
5.今後の予定
第2章 法規制の強化に対応する排水処理技術
第1節 食品工場排水の窒素、リン除去技術
1) 窒素除去対策技術<知福博行>
1.窒素の形態
2.除去技術
2.1 物理化学的処理法
2.2 生物処理法
3. 流動床方式の実施例
4. グラニュール脱窒法の実施例
2) リン除去対策技術 <上野泰功>
1.2槽式間欠曝気法の概要と実施例
1.1 2槽式間欠曝気法の構造
1.2 2槽式間欠曝気法の運転
1.3 2槽式間欠曝気法の適用事例
2.MAP法の概要と実施例
2.1 MAP法によるリン除去の化学反応
2.2 MAP法のフロー概略図
2.3 MAP法の実施例
第2節 高度処理技術
1)残留BOD・COD・SS除去対策<安達 晋>
1.残留BOD・COD除去技術
1.1 生物反応を利用した高度処理
1.2 物理化学処理を利用した高度処理
2. 残留SSの高度処理
2.1 凝集沈殿処理
2.2 高速造粒沈殿法(PBS)
2.3 清澄ろ過処理
2.4 浮上ろ過法
2)色度除去対策<安達 晋>
1.凝集沈澱法による色度除去効果
2.化学的酸化法による色度除去効果
3.活性炭吸着による色度除去効果
4.各色度除去方式の設備比較
3)BOD、窒素、リン除去の制御技術<佐藤茂雄>
1.活性汚泥処理法における窒素、リン除去
1.1 窒素除去の原理
1.2 リン除去の原理
2.活性汚泥法の各種処理プロセスの概要
3.プロセス制御
3.1 送風量制御
3.2 余剰汚泥量制御
3.3 返送汚泥量制御
3.4 消化液循環制御
3.5 凝集剤注入量制御
第3章 下水道放流基準への適合化技術
第1節 高速嫌気性リアクターによる処理<茂木浩一>
1.リアクター
1.1 段階設計
1.2 内部循環
2.ケーススタディー
2.1 乳業排水―低濃度排水の例
2.2 食品加工―中濃度排水の例
2.3 ビール製造排水―高濃度排水の例
3.下水道放流に際しての留意点
3.1 バイオガスの発生
3.2 排水BODの硫酸塩(X-SO4)
3.3 処理水SS
3.2 油分
3.5 処理水硫化物および臭気
第2節 好気バイオリアクター処理<月橋伸夫>
1.食品工場排水の下水道放流
1.1 食品工場排水の下水道放流基準
1.2 従来の下水道除害施設
1.3 好気バイオリアクターによる下水道除害施設
2.酵母処理による下水道除害施設
2.1 酵母処理の概要
2.2 酵母処理の実際
2.3 酵母処理の今後の課題
第4章 排水・廃棄物の再利用技術
第1節 食品工場における固形廃棄物の処理と再利用<八村幸一>
1.食品工場から排出される固形廃棄物の特性
2.固形廃棄物の処理・再資源化技術
2.1 焼却処理
2.2 炭化処理
2.3 好気性発酵処理
2.4 嫌気性発酵
2.5 飼料化
3.食品廃棄物リサイクルの実施形態
4.食品廃棄物再利用検討手順
第2節 水のリサイクル技術<川端雅博>
1.水回収技術
1.1 水回収の考え方
1.2 水回収技術
2.水回収実施例
2.1 食品工場における水回収例
2.2 下水処理水回収例
第3節 リンの回収・資源化技術<高井智丈>
1.リンの回収・資源化技術
2.排水・汚泥からのリンの回収・資源化技術の動向
3.脱リン吸着剤を用いたリン吸着回収技術
4.排水汚泥からのリン回収・資源化技術
4.1 脱リン吸着装置の開発
4.2 再生ステーションの開発
5. 余剰汚泥からのリン資源回収システム開発
6.今後の課題および展開
第4節 食品廃液の飼料化<山本英雄>
1. 汚泥の飼料化
2. 廃液の飼料化
第3部 排水処理設備の最適管理を目指して
第1章 各種食品工場に見る排水処理設備の実際と運転管理への取り組み
第1節 飲料工場における排水処理の現況<藍原英樹>
1.本社工場の概要
2.製造の概要
3.電気、重油使用量
4.排水処理施設概要
5.運転管理概要
5.1 排水フロー
5.2 処理水質
6.運転管理のポイント
6.1 日常管理ならびに留意点
6.2 栄養剤の補給
6.3 溶存酸素の管理
6.4 過去のトラブルと対処の実例
7.現設備における問題点
7.1 汚泥の動向
7.2 能力の増強
第2節 醸造製品
1) ビール工場の排水処理管理への取り組み<平野展生>
1.サッポロビール社排水処理設備の変遷
2.ビール製造工程と排水の種類
2.1 仕込工程(麦汁ろ過、熱麦汁静置)
2.2 発酵、貯酒工程
2.3 ろ過工程
2.4 容器充?工程
3.ビール工場の排水処理設備について
4.嫌気性排水処理設備の運転管理
2) 日本酒<渡辺高年>
1.清酒製造排水の特徴
1.1 洗米排水
1.2 季節性
2.日常管理
2.1 洗米排水処理
2.2 洗米排水量(濃度)の抑制
2.3 調整槽
2.4 曝気槽
2.5 沈澱槽
2.6 凝集沈澱、ろ過
2.7 沈澱不良など
3.窒素・リンの削減について
4.その他
4.1 処理量の削減
4.2 今後の処理方法
4.3 仕込休止中の汚泥保全と立上げについて
3) 醤油製造排水の処理と運転管理<石田由紀夫>
1.醤油製造工場について
1.1 工場の概要
1.2 製造の概要
2.排水処理施設
2.1 排水処理施設の経緯
2.2 排水処理設備概要
2.3 UASB処理
2.4 好気的処理
3.運転管理
3.1 日常運転管理
3.2 運転管理のポイント
3.3 過去のトラブルとその対処の実例
第3節 牛乳・乳製品<矢崎雅俊>
1.用水使用の実態と排水の実態
1.1 用水と排水の実態
1.2 排水の水質と負荷変動
1.3 排水量と汚濁負荷量の増加
2.排水処理設備の実態
2.1 標準的な排水処理設備
2.2 高度な排水処理設備
2.3 下水放流と排水処理設備
2.4 周辺環境と排水処理設備
3.排水処理設備の運転管理の取り組み
3.1 排水処理設備の運転管理の要点
3.2 排水処理設備の操作要素
3.3 排水処理設備の保守管理の要点
3.4 その他の留意点
4.排水処理の計装設備
5.排水処理設備の今後の問題
5.1 余剰汚泥に関わる諸問題
5.2 排水量の低減
第4節 油脂製品-植物油脂製造工場排水処理設備とその運転管理<堀 一>
1.植物油脂製造業の概要
1.1 植物油脂製造業の構造
1.2 用水と業態の関連
2.植物油脂製造工程
2.1 搾油工程
2.2 油脂の精製
3.用水と排水
3.1 水使用の概要
3.2 工程別用水量
3.3 排水濃度
4.植物油脂製造工場における排水処理の現状
4.1 植物油脂製造工場排水処理法
第5節 農産加工品
1)小麦澱粉<村山隆二>
1.排水処理設備の推移
1.1 創業当時
1.2 住民の怒り
1.3 水質汚泥防止法の施行
1.4 酵母菌で処理して、酒の香りのする排水処理に挑戦!
1.5 創エネルギー時代
2.現状処理状況
3.現状の課題とこれからの排水処理への期待
2)南瓜加工場と排水処理施設<及川健一>
1.南瓜加工場施設の経緯と概要
1.1 加工場施設の経過
1.2 南瓜共選加工施設の概要
2.加工場概要
3.排水処理設備概要
4.排水処理設備の運転管理
4.1 操業開始時の運転
4.2 日常業務ならびに日常の留意点
4.3 加工トラブルと対処の実例
第6節 食肉および畜産加工品
1)食肉センター<越野 修>
1.十勝事業所の概要
2.製造の概要
3.排水処理設備概要
4.運転管理概要
5.運転管理のポイント
5.1 日常業務ならびに日常の留意点
5.2 過去のトラブルの対処の実例
5.3 将来における対策
6.その他
2)ハム・ソーセージ<井上祥一郎>
1.低負荷・半回分活性汚泥処理法
2.滝沢ハム(株)泉川工場排水処理施設
2.1 設計諸元
2.2 自動制御システム
2.3 処理工程の流れと水質の変化
2.4 供用開始後3年間の処理水質の経緯
2.5 汚泥沈降速度
第7節 水産加工品<佐野和生>
1.原料処理の排水
2.加工工程の排水
3.単位原料と排水の量と質
4.生産工程別の排水水質
5.排水処理における前処理工程
6.生物処理
7.排水処理の困難さについて
8.水産加工製造業で使用されている排水処理について
第8節 惣菜<副島武雄>
1.工場の概要
2.製造の概要
2.1 製造工程のフロー
2.2 原料使用量、製品出来高
2.3 ユーティリティー使用状況
2.4 廃棄物処理
3.排水処理設備概要
3.1 フローシート
3.2 配置図
3.3 設備仕様
4.運転管理概要
4.1 水質データ
4.2 品種別原排水質
4.3 主要機器の管理状況など
4.4 将来における対策
5.その他
第9節 菓子類<大西正人>
1.工場の概要
2.製造の概要
2.1 果肉ゼリーの製造
2.2 カステラの製造
3.排水処理施設概要
4.運転管理概要
4.1 製造工程別原排水データ
4.2 総合排水データ
4.3 運転データ
5.運転ポイント
5.1 日常の管理
5.2 過去のトラブルとその対処
5.3 現設備の問題点と将来の対策
6.その他工場紹介
第2章 バルキングの診断および対策の実際<長谷川 進>
1.活性汚泥法における各種トラブルの原因と基本的な防止対策
1.1 活性汚泥法の固液分離障害
1.2 活性汚泥法の問題点と改善の考え方
2.バルキングの分類と発生機構
2.1 糸状性バルキングと非糸状性バルキング
2.2 バルキングの原因微生物
2.3 バルキングの発生機構
3.バルキングの管理指標
3.1 運転管理指標
3.2 汚泥の沈降性評価指標
3.3 微生物のモニタリング
3.4 糸状体量
4.バルキング発生時の応急対策
4.1 薬剤添加による応急処置
4.2 運転操作条件変更による処理
4.3 長期運転休止対策
4.4 実施例の紹介
5.バルキングを起こさない水処理技術
5.1 糸状性バルキングを起こしにくい運転操作
5.2 糸状性バルキングを起こしにくい処理方式
第3章 生産能力強化に伴う汚濁負荷量増加への対策技術<田原邦彦>
1.食品工場排水の特性
1.1 生産能力強化と排水処理
1.2 食品工場の排水性状
1.3 排水の流出特性
1.4 食品排水の性状特性
2.現有処理設備の運転最適化
2.1 運転管理指標最適化
2.2 運転管理上のトラブルとその傾向
2.3 曝気不足、過曝気の判定
2.4 DOの測定最適化
2.5 沈澱池の管理と最適化
2.6 MLSSの最適管理
2.7 運転管理の最適化
3.処理設備の適正計画
3.1 負荷変動への対応策
3.2 性状変動への対応策
3.3 生物処理機能の補強
3.4 排水処理設備の能力強化
3.5 工程内排水の回収削減
終章 21世紀の環境低負荷・資源循環型社会構築の課題と展望<稲森悠平/野田尚宏/小沼和博>
1.21世紀における水環境問題の重要性
2.水系循環と物質系循環のハイブリッド化の重要性
3.窒素・リンに的を絞った対策技術の重要性
4.環境低負荷・資源循環型社会構築の課題と展望
■執筆者
稲森 悠平 独立行政法人国立環境研究所バイオエコエンジニアリング研究室室長
小沼 和博 ダイキ(株)中央研究所
佐野 和生 (株)水圏環境コンサルタント 代表取締役
宝月 章彦 神鋼パンテツク(株)専務取締役 環境装置事業部長
曽我 和雄 住友重機械工業(株)プラント・環境事業本部環境システム事業センター 技術部長
中島 淳 立命館大学 理工学部環境システム工学科 教授
中畑 繁夫 三菱化工機(株)環境事業本部商品開発担当 担当部長
村中 雄一 (株)荏原製作所 総合事業統括技術統括技術第二部
高村 義郎 神鋼パンテツク(株)環境装置事業部水処理本部技術部 部長代理
塩田 憲明 神鋼パンテツク(株)環境装置事業部水処理本部技術部
宮本 武 神鋼パンテツク(株)環境装置事業部水処理本部技術部
丹野 健一 オルガノ(株)薬品事業部テクニカルセンター係長
寺谷 直也 石川島播磨重工業(株)回転機械事業部汎用機械設計部課長代理
赤司 昭 神鋼パンテツク(株)技術開発本部第2研究開発部第5研究室 主任研究員
長谷川 進 神鋼パンテツク(株)技術開発本部第2研究開発部第5研究室 室長
西村 総介 栗田工業(株)プラント・サービス事業本部開発部プラント開発チーム主任研究員
荒木 智行 環境省 水環境部閉鎖性海域対策室 総量規制係長
知福 博行 神鋼パンテツク(株)技術研究所環境装置事業部水処理本部技術部 担当次長
上野 泰功 ユニチカ(株)環境事業本部環境技術開発部
安達 晋 (株)荏原製作所 エンジニアリング事業本部総合事業統括技術統括技術第一部 主任
佐藤 茂雄 (株)明電舎総合研究所環境研究部 主管技師
茂木 浩一 石川島播磨重工業(株)環境プラント事業本部第二基本設計部 部長代理
月橋 伸夫 (株)西原環境衛生研究所 海外事業部 統括マネージャー
八村 幸一 鹿島建設(株)環境本部有機性廃棄物資源化グループ 課長
川端 雅博 オルガノ(株)総合研究所開発センター 次長
高井 智丈 武田薬品工業(株)生活環境カンパニー 研究開発部
山本 英雄 (株)セキネ 顧問
藍原 英樹 北海道コカ・コーラボトリング(株)取締役 技術部長
平野 展生 サッポロビール(株)製造本部エンジニアリング部 副課長
渡辺 高年 大関(株)丹波工場 工場長
石田由紀夫 (株)大津屋 開発室係長
矢崎 雅俊 森永乳業(株)生産技術部マネージャー
堀 一 (株)ホーネンコーポレーション 生産技術部次長
村山 隆二 長田産業(株)管理・開発部 部長
及川 健一 佐呂間町農業協同組合 農産部青果加工課 課長補佐
越野 修 (株)北海道畜産公社 主任技師
井上祥一郎 (株)エステム 営業本部理事
副島 武雄 生活協同組合 コープこうべ 生産事業部設備管理 係長
大西 正人 (株)九電工 営業本部環境技術部 営業グループ長
田原 邦彦 森永エンジニアリング(株)環境事業部 次長
野田 尚宏 早稲田大学理工学研究科