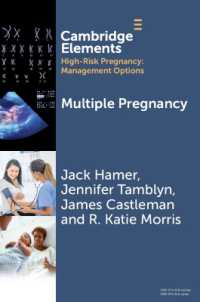出版社内容情報
異物混入対策の効果を決定的に左右する人(作業者)の問題を中心に捉え、単なる技術論から脱却し現場の共感と納得を通して 「混入ゼロ」を実現するまったく新しい規範と行動指針!!
■ 主要構成
第1篇 人を動かす異物対策の新しい視点と動機づけ
第1章 問題発見:消費者クレーム受付対応
第2章 異物対策の基本骨格と混入事故の人間的要素
第3章 作業者の創意を結集する異物対策のルール作り
第4章 作業者の動機づけおよび意識改革のための教育訓練
第5章 異物事故に伴う危機管理と自主回収の考え方
第2篇 人を基軸にした異物対策の総合システムと運用方法
第1章 作業者由来の異物防除システムとその運用
第2章 5Sを基本にした非生物系異物の管理システムとその運用
第3章 そ族・昆虫の防除システムとその運用
第4章 食品からの異物除去システムとその運用
第5章 異物対策のための施設・設備の管理
第3篇 現場の知恵・工夫を集めた混入ゼロへの具体的取組み
第1章 クレームのもたらす企業利益の計量化
第2章 食品企業の改善事例
第3章 流通・量販店の改善事例
■ 内容目次
第1篇 人を動かす異物対策の新しい視点と動機づけ
第1章 問題発見:消費者クレーム受付対応<佐藤邦裕>
1.なぜ異物混入クレームが減らないのか
1.1 異物混入は古くて新しい問題、人間臭いクレームである
1.2 現在(いま)、世の中で何が起こっているのか-ある食中毒事件から-
1.3 異物混入防止対策はなぜこれほど立ち遅れているのか
1.4 異物混入の発生状況
2.異物混入防止対策の現状
2.1 クレーム対応の問題
2.2 異物混入防止対策
第2章 異物対策の基本骨格と混入事故の人間的要素<佐藤邦裕>
1.異物対策の基本骨格
2.実際の異物混入事例における人間的要素を探る
2.1 金属異物
2.1.1 ボルト・ナット類
2.1.2 ステンレス(非鉄金属)の混入、作業機械(部品)の一部が混入
2.1.3 金属タワシ
2.1.4 釣針
2.1.5 縫針
2.1.6 金属検出機の運用不備
2.1.7 ダミーサンプルの混入
2.2 六角レンチ、工具類
2.3 金属以外の危険異物
2.3.1 石
2.3.2 ガラス片
2.3.3 プラスチック片(容器・包材の一部破損)
2.3.4 ホチキス針・クリップ・カッターナイフの刃
2.4 その他(製造環境由来、私物など)
2.4.1 ゴムパッキング
2.4.2 清掃用具類(ほうきの穂、デッキブラシ)の一部、木片、竹片など
2.4.3 支給品(作業衣、筆記具)の一部
2.4.4 輪ゴム・ひも
2.4.5 絆創膏
2.4.6 ヘアピン・ネックレス
2.4.7 貨幣
2.5 昆虫類やネズミ、カエルなどの小動物
第3章 作業者の創意を結集する異物対策のルール作り<佐藤邦裕>
1.作業場における現状(ボルト、ビス、ナット、ワッシャー)
2.危険な金属異物(製造現場での使用は禁止とするもの)
3.組織的なルール活用の仕組み作り
3.1 取組みの骨子
3.2 まとめと評価
資料:異物混入防止のための整理・整頓の徹底のお願い
第4章 作業者の動機づけおよび意識改革のための教育訓練<佐藤邦裕>
1.管理すべき立場の人間が気を付けなければならないこと
2.従業員管理が不行き届きの作業場で見かける事例と改善策
3.効果的な講習会や教育研修の持ち方
資料:「従業員の衛生教育および管理」計画書
一般従事者向け毛髪対策講習会の進め方(例)
第5章 異物事故に伴う危機管理と自主回収の考え方<佐藤邦裕>
1.商品回収が必要となる基本的な条件
2.異物混入対策と危機管理
3.異物混入事故に際しての商品回収や危機管理に関する基本的な考え方
資料:消費者に安全な食品を提供するための提言
クレーム対応上の商品回収の原則
第2篇 人を基軸にした異物対策の総合システムと運用方法
第1章 作業者由来の異物防除システムとその運用
【毛髪混入防止システム】<島田博行>
第1節 システム設計のために最低限収集すべき情報
1.毛髪の科学的特性や生理生態について
1.1 毛髪の構造と毛髪の特性
1.2 毛髪の本数と寿命
2.食品工場に持ち込まれている毛髪の実態
3.持ち込み毛髪の男女間での差
第2節 システムの作り方
1.異物対策3原則による分類
2.異物対策における基本ルールの見直し
2.1 現状の見直し
2.2 危害分析手法による問題点の想定
2.3 着替える前のルールの見直し
2.4 着替えてから入場までのルールの見直し
2.5 入場する際のルールの見直し
2.6 入場後から作業中のルールの見直し
第3節 落下毛髪の採集調査方法とその評価
1.落下毛髪の採集調査の方法
2.データの評価
2.1 原因や裏付けのためのデータ収集と評価
2.2 作業者が毛髪を落としている事実の再確認とその視覚効果
第4節 管理を効率化するための改善の進め方
1.集合研修の開催とその方法(意思の伝達・問題提起・行動計画発表)
2.全体的な改善活動の実施(計画作り)
3.活動後の確認作業の実施(計画の見直し)
3.1 目視による日常的な確認・監視の必要性と意義
3.2 誰がやるのか
3.3 確認すべき内容(決めてあるルールのすべて)と評価
3.4 確認結果のフィードバックとルールの見直し
4.従事者由来の異物混入事故防止対策の取組みのために
【私物の管理】<佐藤邦裕>
1.製造現場で使用される(必要な)ものであるにも拘わらず、支給されておらず自前で調達して
いるもの
2.製造作業で使用するものであり職場でも支給されているが、使用感や個人のこだわりから独自
に調達しているもの
3.製造現場で必要のないものであるが持ち込んでしまったもの
4.私物管理の難しさ
第2章 5Sを基本にした非生物系異物の管理システムとその運用<江藤 諮/島田博行>
第1節 5Sによる管理システムの考え方
1.5Sという概念と整理・整頓・清掃のシステム化
2.整理・整頓・清掃の管理強化による排除効果の高い異物について
3.人のことを考えた異物混入事故防止の基本について
4.異物混入の背後にあるミスと潜在的リスクの関連
第2節 管理システムの設計と確立のために
1.異物の管理のための基礎知識(ルール作りの大原則)
1.1 使用制限の対象とすべきものとは
1.2 管理の対象とすべき状況とは
2.設計のための調査手法として
2.1 危害分析による現場リスクの把握と評価
2.2 異物混入防止のための危害分析手法
2.3 危害分析結果と現場との比較
2.4 現行ルールの実施状況の確認
2.5 ルールとして決めていないが異物混入事故防止のうえで不適当な状況の確認
3.評価に基づく管理の推進
3.1 整理・整頓のための基本条件と考え方
3.2 清掃を効率化するための施設・設備
4.排水処理条件
5.清掃・洗浄作業のための準備について
6.使用制限をした場合の代替案の例について
第3節 システムの作り方と運用のために
1.現状認識の重要性
1.1 工場の危険性を間近に見る
1.2 過去のデータの利用
2.役割分担の重要性について
2.1 企業トップの役割
2.2 現場管理者の姿勢と役割分担
2.3 現場従事者の担当区分の必要性
3.活動の内容
3.1 基本ルールの決定
3.2 目的の適切通知と取組みの意思表明、およびルールの内容の伝達
3.3 初期改善の重要性と取組み
4.管理状況の確認
4.1 確認の必要性と目的
4.2 記録確認の内容
4.3 日常確認以外の現場目視の実際と確認頻度
4.4 効果的な確認のために
5.教育の実際と改善ポイント
5.1 現場管理者へのフィードバック
5.2 一般従事者へのフィードバック
5.3 従事者への専門教育
第3章 そ族・昆虫の防除システムとその運用<江藤 諮/島田博行/佐藤邦裕>
第1節 そ族・昆虫によって引き起こされる問題
1.微生物制御としてのそ族・昆虫
2.異物混入の原因物としてのそ族・昆虫
第2節 製造現場におけるそ族・昆虫類の基礎知識
1.食品工場に侵入、生息するそ族・昆虫類
2.昆虫類の基礎知識
2.1 節足動物と昆虫の分類
2.2 食品工場における昆虫の生態的な分類と区分
資料1 食品工場において異物混入の問題となりやすい飛翔性昆虫
2.3 昆虫を同定する
3.ネズミの基礎知識
3.1 ネズミとは
3.2 主な種類と特徴
第3節 総合的な防除システムの考え方
1.総合的な防除とは
1.1 工場施設の防御力強化
1.2 防御力の維持
1.3 侵入、生息状況の監視(モニタリング)
1.4 駆除
2.そ族・昆虫に対する防御力の考え方
2.1 バリア機能(物理的防御力)
2.2 誘引源コントロール
2.3 発生源コントロール
2.4 サニタリーデザイン
3.そ族・昆虫モニタリングの考え方
3.1 モニタリングの目的
3.2 モニタリングの方法
3.3 モニタリングトラップの種類
3.4 モニタリングデータの評価
4.原因究明活動
4.1 目視調査
4.2 粘着トラップを用いた原因究明活動
5.駆除技術
5.1 薬剤の種類と適切な使用方法
5.2 防除機器の種類と適切な使用方法
第4節 防除計画の作成
1.防除の基本工程
2.教育・訓練計画
3.関連法規
第4章 食品からの異物の除去システムとその運用
第1節 目視による異物の除去<島田博行/佐藤邦裕>
1.目視検品を行うための必要な準備
2.作業環境の問題
3.労働条件の問題
4.作業台の特性
5.作業者を考えた検品作業とは
第2節 金属検出機による異物の除去<久保寺 茂>
1.金属異物混入の実態
2.金属検出機の基本原理
2.1 検出原理
2.2 磁界中の金属の特性
3.金属検出機の検出ヘッド構造と特徴
3.1 検出ヘッド構造と特徴
3.2 金属の通過位置と検出感度
3.3 金属の流れ方向と検出感度
4.包装形態と検出感度
4.1 包装形態と検出感度
4.2 包装材と検出感度
5.設置上の注意点
5.1 電磁波ノイズ
5.2 電源ノイズ
5.3 電流ループ
6.金属検出機とX線異物検出機
第3節 軟エックス線による異物の除去<安藤英明>
1.エックス線について
1.1 エックス線とは
1.2 発生
2.エックス線検査装置について
2.1 エックス線検査装置の原理
2.2 エックス線検査装置の安全性
2.3 エックス線検査装置の経緯(変遷)
3.エックス線検査装置の購入および使用にあたって
3.1 エックス線の性質による留意点
3.2 検査範囲
3.3 排出装置の選定
3.4 エックス線検査装置に使われる画像装置の理解
3.5 安全面での留意点
3.6 精度の維持
3.7 保守・メンテナンス
資料:その他の異物除去装置カタログ集
第5章 異物対策のための施設・設備の管理<大原静男>
第1節 敷地全体での工場の考慮すべき検討項目
1.光と昆虫類
2.栄養(植樹、芝、池)と昆虫類
3.屋外排水処理設備と昆虫類
4.小動物と異物
第2節 問題点の把握・選定・対策
1.床材料の選択・納まり
1.1 塗床仕上げの問題点
1.2 塗床仕上げの考慮すべき条件
1.3 塗床材料の選定方法
1.4 塗床工法の場合の対策
1.5 ステンレス床材について考慮すべき条件
2.壁・天井材料の選択
2.1 ボード仕上げの問題点
2.2 ボード仕上げの考慮すべき事項
2.3 ボード仕上げの選定方法
2.4 ボード仕上げの場合の対策
2.5 タイル仕上げ・ステンレス仕上げの問題点
2.6 タイル仕上げ・ステンレス仕上げの場合の対策
3.塗料材料(防カビ塗料)
3.1 問題点
3.2 対策
3.3 金属面に塗る塗料の種類および正しい施工方法
4.建具の選択
4.1 各種の建具の特徴
4.2 各種の建具の使用基準
4.3 共通の問題点
4.4 共通の対策
5.室内配管
5.1 問題点/5.2 対策
6.排水勾配・排水溝・排水口・配水管の納まり
6.1 臭気が強く固形物を含まない粘性のない液体
6.2 固形物を含み粘性のある液体
6.3 高温では液体であるが常温では固体(バター等)
6.4 高温では大量に溶けるが常温では結晶となる固体(糖分等)
7.照明
7.1 室内灯
7.2 室内灯の問題点
7.3 室内灯の対策
7.4 屋外灯
7.5 屋外灯の問題点
7.6 屋外灯の対策
8.換気・空調ダクト
8.1 問題点/8.2 対策
9.カビ・結露の発生
9.1 問題点/9.2 対策
10.冷凍・冷蔵室
10.1 問題点/10.2 対策
11.エアシャワー・パスボックス
11.1 問題点/11.2 対策
12.フォークリフトによる破損
12.1 問題点/12.2 対策
13.エレベーターピット・ダムウェーターピット
13.1 問題点/13.2 対策
第3節 工場運営上の正しいメンテナンス
1.メンテナンスの項目
2.日常の小さな手直し
2.1 照明器具のランプの交換
2.2 床の仕上げ材の剥がれ
2.3 壁の孔
2.4 スチール部分の塗装の剥がれ
2.5 ステンレスの錆び
2.6 シーリングの剥がれ、劣化
第4節 生産設備の増設時、建物増築時の注意点と関連法規
1.建築基準法-建築基準法施行令-建築基準法施行規則
2.消防法-消防法施行令-消防法施行規則
3.消防法-危険物の規制に関する制令-危険物の規制に関する規則
4.工場立地法
5.騒音規制法-騒音規制法施行令-騒音規制法施行規則
6.大気汚染防止法-大気汚染防止法施行令-大気汚染防止法施行規則
7.水質汚濁防止法
8.建築基準法、浄化槽法
9.悪臭防止法-悪臭防止法施行令-悪臭防止法施行規則
10.食品衛生法
第6章 異物の検査法
第1節 異物の簡易検査法<野中大輔/飯田敦史>
1.異物検査の目的
2.工場でできる異物の検査法
2.1 形態観察
2.2 水への反応の観察
2.3 燃焼性の観察
2.4 磁性の観察
2.5 試薬による呈色・溶解等の観察
第2節 混入毛髪の同定および追跡調査<島田博行/邑井良守>
1.毛髪同定法の概要
1.1 同定を実施するために必要なサンプルの条件
1.2 サンプル全体の肉眼および低倍率での観察
1.3 スンプ標本による観察
1.4 透過(プレパラート)標本による観察
1.5 生物顕微鏡下での観察
2.追跡調査とその技術
2.1 追跡検査の手法
2.2 物理的損傷とその判定
2.3 カタラーゼテスト
2.4 その他の検査
第3篇 現場の知恵・工夫を集めた混入ゼロへの具体的取組み
第1章 クレームのもたらす企業利益の計量化<角野久史>
1.京都生協におけるクレームの受付状況
2.安心・信頼できなくなった食品および食品メーカー
2.1 増加する回収
2.2 自主回収基準の設定
3.クレーム対応の基本
3.1 Y乳業の対応
3.2 京都生協のクレーム対応マニュアル
4. クレーム対応の基本
4.1 クレームに対する視点
4.2 クレームのもたらす企業利益の計量化
第2章 食品企業の改善事例
1.冷凍食品<川本 誠>
1.毛髪混入防止対策
1.1 毛髪混入のメカニズム
1.2 服装
1.3 粘着ローラーを使っての除去と留意点
1.4 個人の意識向上により自分たちの職場から毛髪混入を発生させない
1.5 組織としての取組み
2.金属異物混入防止対策
2.1 金属検出器の精度確認(テストピースが排出されるまでが一連の動作)
2.2 金属検出時の処置
2.3 金属検出機で検知されにくい金属と散発して発生する金属クレーム
3.その他の異物対策
3.1 異物に関する情報の収集
3.2 5S日番活動
2.水産ねり製品<加藤 登/花岡 豊>
1.ねり製品の異物混入の実態
2.ねり製品の製造工場における異物混入対策への対応
3.珍味食品類<富田 勉>
1.珍味食品類の異物
2.水産原料中の異物
3.異物混入防止対策
4.穀類、ナッツ<橋際正行>
1.穀類(香辛料)
1.1 異物混入経路
1.2 香辛料の流通(選別)経路
1.3 産地での異物除去
1.4 国内での異物除去、毛髪対策
1.5 粉末香辛料の運用面での毛髪除去
2.ナッツ(クルミ)
2.1 風力選別
2.2 色彩選別
2.3 目視選別
2.4 金属探知機
5.ハム・ソーセージ<中原 彰>
1.人毛
2.豚毛・豚骨
2.1 原料豚肉に豚毛が 混入する原因
2.2 豚枝肉に豚毛を付着させないための対策と効果
3.その他の異物
6.牛乳・乳飲料・デザート類<堀内正義>
1.牛乳・乳飲料・デザート類の異物の実態
1.1 牛乳・乳飲料・デザート類の異物の実態
1.2 デザート類の混入異物の傾向
2.異物対策の基本
3.5Sに関わる異物対策
4.その他衛生環境に関わる異物対策
7.調味料類<田中秀夫>
1.異物クレームの実際と原因物質
2.対策技術への取組み
3.製造現場への適応方法
4.改善取組み継続のための効果的仕組みと運用ルール
8.弁当・惣菜<加藤勇治>
1.異物混入とクレームの関係
2.クレーム受付け台帳の作成
3.特性要因図の考え方
4.不完全な対策の連続
5.従業員の躾・身だしなみマニュアルの例
6.個人衛生チェックシート
7.金属検出機と使用管理
8.正しい金属検出機の使い方
9.漬物<國原正記>
1.会社・工場紹介
2.和風キムチにおける異物クレーム実態
3.クレームに対する意識の変化とその対応例
4.異物対策の具体例
5.原料白菜由来異物除去対策の具体例
6.商品回収基準
10.パン・菓子<力野加津子/中嶋 博/石黒 厚>
1.原因
2.目的
3.再現テストの実施
4.対策
5.人が人を動かし全員一致で異物除去
11. 菓子類(1)<益子 剛>
1.お客様苦情と製造物責任(PL)
2.TPM活動の品質管理
3.防虫管理
4.防鼠管理について
12.菓子類(2)<近藤純夫>
1.混入異物の内訳
2.異物混入事故の原因と対策
3.「毛髪混入防止」に対する取組み事例
13. 即席めん類<法西皓一郎>
1.異物の定義と分類
2.可視的異物
3.加工食品についての異物混入などの経験
4.即席めんにおける異物混入の原因と対策
第3章 流通・量販店の改善事例
1.生協における改善事例(1)<小森谷忠昭>
1.現場の長の変化による改善事例
2.従業員の変化による改善事例
3.従業員による改善事例
4.工場内清掃の成功事例
5.設備的な問題対策
6.全体的な異物混入対策
2.生協における改善事例(2)<結城健児>
1.クレーム防止の取組み
2.お取引き先との取組み
3.百貨店の改善事例(1)<木谷一成>
1.高島屋の品質に関する基本姿勢
2.異物混入など(PL的)事故につながる初期発生時点での情報収集と対応策
3.異物混入や食中毒(PL的)事故発生時の対応に対する基本姿勢の明確化
4.食品クレームの発生状況の1999年度と2000年度の比較および再発防止策
5.店内でのネズミ・ゴキブリ駆除の強化策
4.百貨店の改善事例(2)<吉田親義>
1.阪急百貨店の組織について
2.お申し出の状況
3.異物混入の状況
4.衛生個別懇談会について
5.店頭での実践について
5.CVSの改善事例<山上俊一>
1.「弁当」「惣菜」類の食品としての特徴
2.「異物」混入防止にあたって
3.異物の発見と除去
6.大手量販店の改善事例<小田川 平>
1.インストア加工における苦情等について
2.改善のターゲットと障害
3.本質的な問題
3.1 食品衛生の聖域化の問題
4.具体的事例
4.1 量販店側の改善点の概要
4.2 原材料、資材の購入先の管理
5.何が人を動かせるのか
■執筆者
佐藤 邦裕 日本生活協同組合連合会品質管理部部長
江藤 諮 イカリ消毒(株)技術部CLT研究所所長
島田 博行 イカリ消毒(株)事業本部営業推進部課長
久保寺 茂 アンリツ(株)インダストリアルソリューションズ開発本部開発部主幹技師
安藤 英明 (株)キリンテクノシステム国内営業部課長
大原 静男 (株)奥村組東京支社建築設計部
野中 大輔 イカリ消毒(株)川越営業所係長
飯田 敦史 イカリ消毒(株)技術サービス部主任
邑井 良守 イカリ消毒(株)環境文化創造研究所環境調査室室長代理
角野 久史 (株)コープ品質管理研究所取締役所長
川本 誠 (株)ニチレイフーズ高槻工場品質管理部部長
加藤 登 (株)紀文食品購買本部本部長付マネジャー
花岡 豊 (株)紀文食品供給本部東京工場副工場長
富田 勉 (株)なとり食品総合ラボラトリー所長
橋際 正行 小林桂(株)明石工場工場長
中原 彰 林兼産業(株)開発部部長
堀内 正義 ジャパンミルクネット(株)(全酪)品質保証部課長
田中 秀夫 (財)日本醤油研究所理事
加藤 勇治 フーズテクノかとう(有)代表
國原 正記 備後漬物(有)品質管理室室長
石黒 厚 (株)ドンク営業サポートグループ品質管理課長
中嶋 博 (株)ドンク名古屋品質管理
力野加津子 (株)ドンク営業サポートグループ品質管理
益子 剛 カルビー(株)お客様相談室
近藤 純夫 新栄食品(株)品質管理部顧問
法西皓一郎 (社)日本即席食品工業協会事務局長兼 技術委員会委員長
小森谷忠昭 東葛市民生活協同組合事業支援部商品課
結城 健児 エフコープ生活協同組合商品本部商品管理担当
木谷 一成 (株)??島屋MD統轄本部商品試験室グループマネジャー次長
吉田 親義 (株)阪急百貨店フード事業部業務運営部衛生担当専任課長
山上 俊一 前 CVS品質管理部長
現 中国パール販売(株)品質管理部部長
小田川 平 (株)品質管理センター食品調査・開発室課長