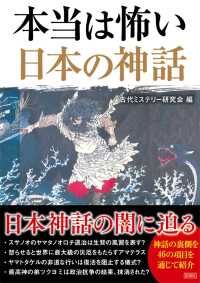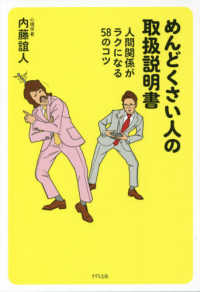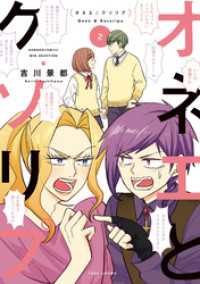- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
全国でたった3人!の銭湯ペンキ絵師。唯一の若手が語るその魅力。
目次
子供の頃
描いて、落ち込む
「質問の答え」ではなく、「質問の意味」がわからない
弟子入り
会社を辞めたこと
両親
1型糖尿病のこと
「好きなことを仕事にする」とは
夫について
「『女性』ペンキ絵師」という肩書
「女性」職人の妊娠出産について
銭湯ペンキ絵に何が描かれてきたか
銭湯ペンキ絵はメディアだ―ペンキ絵と世の中の経済との関わり
ペンキ絵は、変わるべきか
銭湯ペンキ絵を百年先に残すために、意識的にしてきたこと
銭湯ペンキ絵はアートか否か
銭湯の未来
著者等紹介
田中みずき[タナカミズキ]
1983年生まれ。明治学院大学在学中に銭湯ペンキ絵師・中島盛夫氏に弟子入り。大学院修了後、出版社編集業等を経て、アートレビューサイト「カロンズネット」の編集長を務める。2013年より夫の「便利屋こまむら」こと駒村佳和と銭湯のペンキ絵を制作。通常の銭湯でのペンキ絵制作に加え展覧会、イベント、ワークショップなど多くの方にペンキ絵を使って銭湯に関心を持っていただける活動を模索中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
竹城 俊之介
57
先日、東京銭湯に行って人生初ペンキ絵を見ました。実物は素晴らしかった。日本に3人しかいない銭湯絵師の1人、田中みずきさんの本。 実に理知的な思考をされる方で驚きました。幼少期から学生時代、お仕事、ご結婚、出産、美術論など共感したり関心したり、人の思考に触れるのが楽しいと感じる本でした。 「銭湯ペンキ絵の始まりは大正元年のキカイ湯」だと何の疑問も抱かず暗記してましたが、田中さんの考察が一歩踏み込んだ内容で興味深く拝読。ペンキ絵の始まりの話、これ面白いなあ。 銭湯が好きとか関係なくオススメな一冊でした。2025/12/08
けんとまん1007
56
銭湯。いい響きを持つ言葉。そんな銭湯を思い浮かべると、富士山を中心とした絵が脳裏をよぎる。すべての銭湯が、そうだとは思わない。そんな絵を描く職人。職人としての在り方・考え方が書かれていて、職人に限らず、広くあてはまることが多いと思う。人は、与えられるだけでは、どこかで息詰まるし、浅く終わるのではと思う。苦労し、自分なりの思いを持つかどうか・・・やはり、ここに尽きるのかなと思う。2021/09/16
アッキ@道央民
48
銭湯のペンキ絵、連想するのがあの富士山の絵。それを描くのを仕事にしている女性がいるんだなぁ~と思って手に取ってみた1冊。そんな絵を描く職人の事についてなど書かれているが、元々著者が美術を学んでいる事から、美術的な観点からペンキ絵の事、または職人の仕事の事等も書かれているけどなかなか興味深いし、合間合間に紹介されているペンキ絵見てみると、やっぱりこれア-トじゃないの?とも感じる。って言うか、銭湯行ってペンキ絵見ながらゆっくりお湯に浸かるのも良いかなぁ~なんて気分になってしまったよ。2021/12/08
井月 奎(いづき けい)
45
絵を描く人は文章の上手い人が多く、この著者の文章も長く深く思考されたことが分かりやすく書かれています。わかりやすい文章なのですが、ペンキ絵のこと、芸術論、職人や古い体質の働き方のとらえ方や考え方が実に考察深く含蓄に富み、ときには学術的に書かれています。いつも問いをもち仕事をする、問題意識を抱きつつ生活する、高いパフォーマンスを維持する方法を考える。休みなく頭を回転させて、ペンキの刷毛をふるっていることが想像できて刺激的です。本書からひとつすばらしい気づき、言葉を「逸脱は日常生活にあるから意味を持つ」2021/09/25
たらお
31
全国でたった3人!の銭湯絵師。銭湯が町の中からなくなりつつある昨今、気になるのはどうしてこの職を選択したのかという点なのだが「好きか否かよりも、興味を持って問いを持てる仕事は面白く感じられる~問いを持って取り組んでいけるか否かというところだ。」というところにつきるようだ。元は編集の仕事もしており、文章も論理的で、考えは内面よりも社会とのつながりや制度に対してむかっている。実は、我が町の銭湯でもこの方が描いたことが新聞紙上に載っており、それが引っかかっていたので読んだ次第。近々その銭湯に行ってみようと思う。2023/01/24