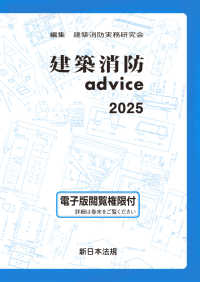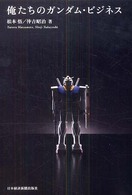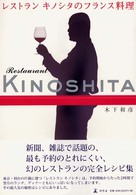内容説明
歴史的に相撲の形式を整えてきたのは吉田司家である。横綱を考案し、免許を与えつづけ、その土俵入りも指導した。行司への教育はもちろん免状も渡した。その吉田司家の後裔が、存廃の危機にある大相撲に「歴史に学べ」と一言を呈す。相撲廃止の危機は明治時代にもあった。それを二十三世追風はどのように乗り切ったか。歴史に学び、原点に還ることこそ、今、必要だ。
目次
1 二十三世追風国技相撲道を死守す(相撲廃止の危機を突破;吉田追風家の権威を守る;二十三世追風、縦横無尽の活躍 ほか)
2 歴代の吉田追風(吉田司家中興の人 十三世吉田追風;十五世追風 肥後藩細川綱利に仕える;吉田司家の名声あがる ほか)
3 吉田司家と五条家について
4 肥後が生んだ横綱
5 吉田司家その後
著者等紹介
吉田長孝[ヨシダナガタカ]
1944年、熊本市生まれ。1951年、24世追風引退により7歳で25世追風を継承。13歳で九州場所前夜祭において横綱鏡里・吉葉山の三段構えを司式した。明治神宮での横綱推挙式において41人目横綱千代の山から59人目横綱隆の里まで横綱及び故実門人を授与し、熊本の吉田司家邸内にて1985年まで立行司木村庄之助、式守伊之助以下三役格の行司の免許状も授与してきた。また、1919年から始まった全国学生選手権の個人優勝者に「絹手綱」を1985年まで授与した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Akihiro Nishio
16
熊本にて熊本の偉人伝を読む。熊本の吉田司家は室町時代に朝廷より相撲の神事を司る勅を受けた。時代の変化や武家の勃興により忘れられていた時期もあったが、江戸時代に復活。細川藩に召し抱えられ、以降現代相撲の型や横綱制度、行事制度を整え、免状を発行する独占権を得る。明治初期は相撲の危機であったが、吉田司家23代善門が個人的に奮闘し、国技としての相撲を提唱し存続させることに成功した。25代善孝の時代に相撲協会へと権限を委譲し、現在は象徴的役割を果たしている。2018/05/16