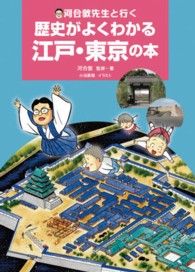出版社内容情報
中島岳志[ナカジマタケシ]
著・文・その他
内容説明
It’s automatic!?誰かのためになる瞬間は、いつも偶然に、未来からやってくる。自己責任論も「共感」一辺倒もさようなら。利他論の決定版。
目次
第1章 業の力―It’s automatic(落語「文七元結」;古今亭志ん朝と立川談志の解釈 ほか)
第2章 やって来る―与格の構造(ヒンディー語の与格構文;言葉はどこからやって来るのか? ほか)
第3章 受け取ること(利他と利己のパラドクス;ありがたくない「利他」 ほか)
第4章 偶然と運命(イラク人質事件と自己責任論;タイの洞窟遭難事故 ほか)
著者等紹介
中島岳志[ナカジマタケシ]
1975年大阪生まれ。大阪外国語大学卒業。京都大学大学院博士課程修了。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。専攻は南アジア地域研究、近代日本政治思想。2005年、『中村屋のボース』で大佛次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
187
ジャック・アタリさんの「合理的利他主義」への懐疑からこの本は書かれている。親鸞の言う他力、ヒンディー語の与格的構造、与える利他ではなく受動的に発動する利他の時制、九鬼周造の偶然・邂逅などを考えることを通じて、「利他の本質」が明らかにされる。最近流行りの利他ではあるが、善意や支配や利己的なサバイバル術にしてはいけないという著者の強い思いが伝わってくる。私は中島さんの文章が好きだ。論理的には鋭く追求するが、常に、人としての優しさが伴っている。この本も、そんな中島さんのお人柄を感じることのできるいい一冊だった。2022/02/07
けんとまん1007
147
3年ほど前から、「利他」は自分の中で重要な言葉の一つ。今回、この本を読んで、やっとその意味の理解の入口に立ったように思う。利他は、発動するもの・・・オートマチックという視点が、納得できるものが多い。それと、時間軸の捉え方も、なるほどと思う。結果を思い描くのではなく、時間を置いて(未来に)結果的に何かが起こるということ。そして、与格という視点。その人の生き方が、如実に表れるのかもしれない。2022/02/18
ちゃちゃ
120
日々のあり方を考える上で示唆に富む好著だった。親鸞に多大な影響を受けた著者。「私が私であることの偶然性」を自覚することが他者への共感や寛容に繋がると説く。私たちが今ここにあることは、“思いがけず、たまたま”なのだ。“社会や他者のため”の貢献や自律は、利己的な欲望が含まれ我知らず支配関係を生む。さらに注目したのは、主格に対する“与格”という捉え方だ。“私が~する”のではなく、“私に~がやってくる”というヒンディー語文法の概念。利他は自己を超えたオートマティカルな力によってもたらされる。目から鱗の連続だった。2023/06/17
アキ
109
羽生結弦が恩師の言葉を胸に、4回転アクセルに挑んだことをインタビューで知る。これこそ本書での利他とは未来から贈与されるという実例ではないか。近代とは主格の時代だとしたら、ヒンディー語の与格のように、我々が失ってしまった「幻」と付き合い、身が動くことを大事にする。利他的な行為も、いつの間にかそれが支配的になることもあることを知り、相手に利他が発動する「受け取るとき」を待つしかない。それは自己責任などという、自己の偶然性を無視した考えを否定し、「今」の意味を未来から倒逆的に理解することに他ならない。2022/02/20
シナモン
104
利他であろうとするとき、そこに本当の利他は生まれない。利他とは「受け手」によって生まれるもの。日々精一杯生きて自分のすべきことを淡々と行う。その静かな繰り返し。そこに「思いがけず」の利他が生まれる。焼き物の「窯変」のたとえが沁みた。心に深く刺さる一冊だった。2024/12/23
-
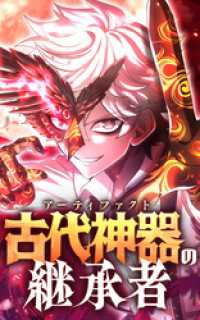
- 電子書籍
- 古代神器〈アーティファクト〉の継承者【…
-
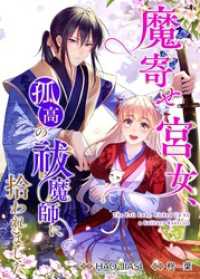
- 電子書籍
- 魔寄せ宮女、孤高の祓魔師に拾われました…
-
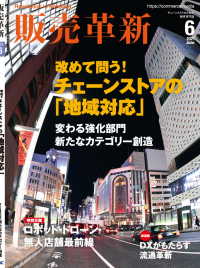
- 電子書籍
- 販売革新2021年6月号 - チェーン…
-

- 電子書籍
- 剣豪医無双剣 艶色斬り コスミック時代…