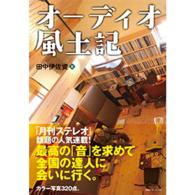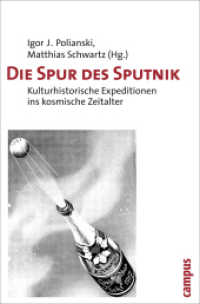内容説明
世界各国の作家や詩人たちがアメリカ・アイオワ大学に集まり行われる約10週間の滞在型プログラム「インターナショナル・ライティング・プログラム(IWP)」。お互いをほとんど知らずに出会い、慣れない言語や文化の違いに戸惑いながらも少しずつ変化していく書き手たちの関係性の機微を、小説家・滝口悠生が日記として綴る。
目次
1 2018年8月19日~8月27日
2 2018年8月28日~9月19日
チャンドラモハン
3 2018年9月20日~10月5日
アイオワの古本屋
4 2018年10月6日~10月31日
著者等紹介
滝口悠生[タキグチユウショウ]
1982年東京都生まれ。2011年「楽器」で新潮新人賞を受けデビュー。2015年『愛と人生』で野間文芸新人賞。2016年『死んでいない者』で芥川賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆきらぱ
35
淡々としているようで熱く広がってゆくように書かれる文章がたまらなく良かった! 「やがて忘れる過程の途中」という一見冷めたようなタイトルは「容易に忘れる事など出来ない日々」にあえてつけられたものなのかも。大人になって誰かの夫でも妻でも親でもなく文学という共通のものだけで集って友達になってゆく日々がとても貴重。ところどころで涙が出た。2022/01/18
ケイティ
24
世界各国から招集された作家たちと、アイオワで滞在型プログラムを過ごした日記。淡々と、しかし丁寧に柔らかく毎日の出来事や心情、気づきを綴る文章から、滝口さんの人柄が伝わってくるよう。言葉が通じきらない状況ならではのコミュニケーションは、相手への想像力を駆使して、簡単に反応しないことで自分の中で醸成されていく深みがある。そして、真摯に伝える思いは通じる。そんなささやかな営みに、自分の留学時代も懐かしく思い出した。タイトルが最高に素晴らしい。2024/04/09
M H
17
滝口さんの作品は「高架線」「ラーメンカレー」のみ既読でどちらも好きなのに理由が説明できない不思議さを感じている。本書はアイオワ大学のIWPという10週間滞在プログラムの日記。ぎちっとした行間なのか造本のせいかちょっと読むのに苦戦しつつ、集まった約30名との交流、距離感を眺めていた。とはいえバックボーンは様々。仲良くなる人はなるし、あまり話さないままプログラム終了の人も。滝口さんのデリカシー、受容(放置とは違う)ぶりにホッとする。2025/08/03
Matoka
15
《メモ》『異なる言語にするというのは、意味を同じくするのではなく言語における意志のかたちを探すということなのかも、だから翻訳が可能なんだな』 『読んだりしたものをきれいに説明したり言語化したりできないから「あまり読んでいない」という。』 とても面白かった。細かく日記形式で書かれているので自分もその場にいて同じ体験をしたかのような感覚にもなった。2021/04/29
kuukazoo
9
アイオワ大学のInternational Writing Programという滞在プログラムに参加した2018年8月19日~10月31日の日記。27か国28人の作家が生活を共にしワークショップや朗読会をし旅行にも行く。皆キャラが濃くよく喋り歌い踊る。そんな中で滝口さんは英語があまり得意でないが、ぼーっとしつつも皆と親睦を深めていく。母国語の翻訳がないため英訳で読むしかなく否応なく英語を身につけねばならない他の参加者には色々複雑に思うことがあったかも。忘れる過程の途中で日記に書かれたこと書かれなかったこと。2021/05/17
-

- 和書
- アメリカの歴史 3