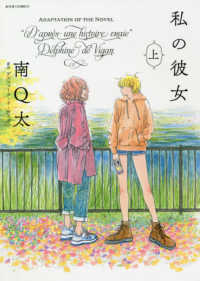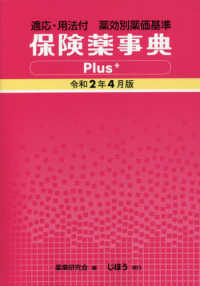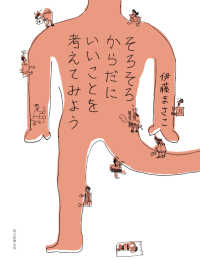出版社内容情報
ドイツの映画の独自性や、どのような社会的背景のもとにそういった作品群が成立したかを大まかに把握できる。
内容説明
スクラダノフスキー兄弟、ラング、リーフェンシュタール、コイトナー、ファスビンダー、アキン…。ユニークな人材が織りなす物語の集合体としてのドイツ映画史に10の視点から光を当て、その本質を浮かび上がらせる。
目次
第1章 ドイツ映画の誕生物語―スクラダノフスキー兄弟とオスカー・メスター
第2章 ドイツ映画と“神話的なもの”―“光の映画”と“闇の映画”の交錯としての
第3章 戦前のドイツ映画における首都ベルリン
第4章 ファシズム政権下の“異国映画”―ツァーラ・レアンダーと李香蘭
第5章 冷戦と東西ドイツ映画
第6章 “挫折”と“俗悪”の美学―ニュー・ジャーマン・シネマとは何だったか
第7章 ファスビンダーとラープ―挑発としての映画
第8章 ヴェンダースとハントケ―人生と芸術の融合
第9章 ドイツ映画はヒトラーおよびナチ時代をどう描いてきたか
第10章 二〇〇〇年以降のドイツ映画
著者等紹介
瀬川裕司[セガワユウジ]
明治大学国際日本学部教授。専門はドイツ文化史・映画学。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。横浜国立大学教育学部専任講師、同助教授、明治大学理工学部助教授、同教授、ベルリン自由大学客員研究員を経て2008年より現職。文学博士。2003年ドイツ政府フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tieckP(ティークP)
8
まったく詳しくないので勉強のために読んだのだけれども、知識を得るだけでなく、読み味も良いし無駄な章もなくて娯楽書としても楽しめた。映画に対する態度が学問や正義に偏りすぎてないのが良いのだろう。もちろん、アート系の映画についてはそのような取り扱いがなされているし、ナチスも東西冷戦も移民問題も主要なテーマとしてしっかりまとめているけれども、ありがちな「裁く」トーンがない。多くの映画・物語を見たことでの達観した面白さへの態度が全体を支配している。この本の感想がほぼないのはドイツ映画を論じる人には低俗過ぎるのか。2022/04/13
-

- 洋書
- PARTIR
-

- 電子書籍
- 美少女学園 近藤あさみ Part.18…