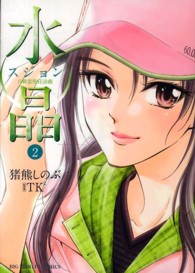出版社内容情報
はしがき
第一章 古墳は貴族・豪族だけのものか
1. 津山市佐良山古墳群 2. 佐良山古墳群の内訳 3. 前期古墳と後期古墳 4. 「豪族」 の古墳と有力農民の古墳
第二章 蒜山盆地・吉備高原の開拓
1. 蒜山盆地と吉備高原の調査 2. 蒜山盆地の弥生時代遺物 3. 吉備高原の弥生遺物と遺跡 4. 高地帯への進出
第三章 蒜山原四つ塚古墳群
1. 蒜山原の古墳 2. 四つ塚古墳群の構成 3. 各古墳の状況 4. 四つ塚古墳群の廃絶
第四章 弥生時代集落の基本単位
1. 日本原・御崎野遺跡の竪穴住居址 2. 北吉野村野田遺跡の発掘から日本原の悉皆調査 3. 津山市沼遺跡の発見と第一次発掘 4. 以後の沼遺跡の発掘 5. 単位集団としての沼遺跡 6. 福岡市比恵遺跡と静岡市登呂遺跡 7. 弥生集落相互の関係の類型
第五章 月の輪古墳に葬られた人々 (1)
1. 三つの棺 2. 中央棺と南棺 3. 副葬品からみた中央棺と南棺の違い 4. 中央棺は男、 南棺は女と推定 5. 男が威張る世の中
第六章 月の輪古墳に葬られた人々 (2)
1. 中央棺の被葬者 2. 造出しの棺
3. 船師集団の長 4. 月の輪地域の政治的統一
第七章 塩を焼く民の発見 (1)
はしがき
岡山へ移り住んでから今年で四七年になる。 その間、 多くの考古遺跡を見学し、 調査し、 その幾つかを発掘した。 その度に、 いろいろな問題が出てきて、 その解決に再び調査・発掘を行うということを繰り返してきたが、 満足するような結論はなかなか得られない。 学問を含め物事には絶対的な解決などあろうはずはないと思うので、 それはそれでよいのであるが、 齢と共に 「なぜあの土地を調査したのか」 「この古墳を掘って何を考えたのか」 という人達の疑問に、 これまで判りやすい形ではほとんど答えてこなかったような気がしていた。
そんなある時、 岡山部落問題研究所の雑誌 『部落問題-調査と研究』 の百号記念パーティーの席で、 その研究所の理事長でかつ友人の原野翹あきらさんにたまたま会い、 何か書くようにとのお誘いを頂いた。 原野さんのかなり強い要請もあり、 また僕は河野通博さんや菊井禮次さんなどと共にこの研究所の設立時に多少かかわったこともあったので、 お引き受けすることにし、 一九九三年二月刊行の一〇二号から 「垣間みた原始古代」 という題名で連載を始めた。 ふた月に一回の割で書いていったが、 やがて気疲れが溜まり、 一四回で降りた。
その後、 旧友薬師になって、 はたと本書の内容を思い、 いささか慌てる仕儀となった。 しかし気を取り直して考えてみると、 僕はかぐや姫を見ようとして原始古代の淵を覗いたわけではないし、 原始古代は世に言われるほどロマンに満ちたものでもない。 共通していることは、 平安時代の男達と同じように僕も好奇心のかたまりであることくらいである。
さていうまでもないことだが、 居住の跡であれ埋葬の場所であれ、 多くの人々の理解と協力なしには調査・発掘は何一つできない。 本書に出てくる遺跡についてもまったく同じことである。 章毎にお名前あるいは文献を挙げて謝意を表したが、 すべての方々を記録し記憶しているわけではない。 はしがきを閉じるに当たり改めてこれまでご協力下さったすべての方に心から感謝申し上げる。 またこのような形での再録を承諾された 『部落問題-調査と研究』 編集部各位に厚くお礼を申し上げたい。
一九九七年七月一一日百間川畔にて
近 藤 義 郎
-

- 和書
- SF大将 ハヤカワ文庫