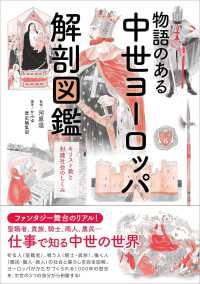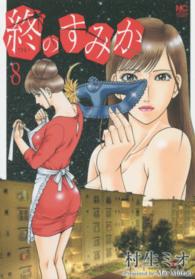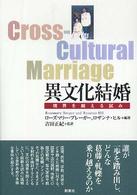出版社内容情報
★バインダーの選定・適正添加と脱バインダの最適化【執筆 村田製作所】
★製造工程の条件が微細構造に与える影響とその制御【執筆 太陽誘電】
★微細構造の制御とその緻密化【執筆 TDK】
◎脱バインダ技術とその最適化 ◎焼成条件と微細構造制御◎低温焼成技術◎スラリー調製と均一分散化 ◎シート成形と薄層・積層化技術
★本書はこんなノウハウが詰まっています★
1、脱バインダ工程のコツとポイント!
2、原料粉末合成時の粒径・粒度分布・不純物量・組成の制御 テクニックとは?
3、スラリーの粘度、微粒子の分散・凝集現象の制御!
4、高分子分散剤が粉体粒子の分散への与える影響とは?
5、シートにおいて有機添加剤、バインダーに要求される役割とは??
6、柚子肌、クラック、塗工スジ、ピンホールを未然に防ぐ!最適なシートの作り方!
7、最適なバインダーの種類や添加量とは?
8、グリーンシート成形における不具合発生の要因と装置・操作条件の最適化!!
9、各工程パラメータが焼結体の微細構造に与える影響とは?
10、LTCC多層モジュールの部品実装技術と設計手法!
11、圧電セラミックス、積層セラミックコンデンサなどのセラミック電子部品の材料・プロセス技術、評価法、応用!
第1章 セラミックス原料粉末の合成とその評価
原料粉末の合成において粒径・粒度分布・不純物量・組成を制御し
なければ後の成形、焼成また製品特性に影響を与える。そこで各種
合成法における優位性とそれによって出来る粉末について評価、解
説する。
1.セラミックス粉末合成法について
1.1 固相合成法 1.2 液相合成法 1.3 気相合成法
2.粉末評価について
3.実例(高純度アルミナ粉末)
3.1 主な用途 3.2各種合成法
第2章 各種有機添加剤の要求物性と粉末への適正添加
スラリーを最適化するための高分子分散剤の選定・設計のポイント
を解説する。そして、シート成形法を中心にバインダーを選定する際
の考え方やバインダーに求められる特性、条件から最適なバインダ
ーの種類とその添加量について実際にセラミックスを成形しているメ
ーカーの開発者自身が言及する。
第1節 成形用有機添加剤(バインダーを除く)の要求物性とそ
の使い方
1. 高分子分散剤の吸着特性
2. 高分子分散剤の分子構造と分散性
2.1 分散剤の分子構造の影響 2.2 高分子吸着に及ぼす溶媒効
果
3. 粒子の表面特性と高分子分散剤の吸着
第2節 バインダーの選定とその適正添加
1.電子部品用セラミックスの製造に用いるバインダーに要求される条
件
2.各成形法で要求されるバインダーの特性
2.1 シート成形法
2.2 その他の成形方法
2.2.1 押出し成形法 2.2.2 鋳込み成形法
2.2.3 射出成形法 2.2.4 加圧成形法
第3章 スラリー調製と微粉末の均一分散化
テープ成形を最適化するためにスラリーの粘度、微粒子の分散・凝
集現象の制御は重要である。この章では界面活性剤の最適化、温
度と溶剤量がスラリー粘度に及ぼす影響そして分散微粒子のナノレ
ベルでの制御の可能性などについて解説する。
第1節 スラリー粘度の調製
1. スラリーの粘性挙動
2. 脱泡と粘度調整
3. 粘度評価
第2節 スラリーにおける微粒子分散・凝集設計技術
1. 分散・凝集の原理
1.1 DLVO理論 1.2 高分子分散剤による分散・凝集
2. スラリーにおける微粒子分散・凝集の評価方法
3. スラリー分散状態によるバルク体の変化
3.1 分散状態がセラミックス焼結特性に与える影響
3.2 ナノ微粒子の自己集積膜形成
第4章 グリーンシート成形とその薄層・積層化技術
機械の視点から成形条件がシートの膜厚、クラック・ピンホール・ク
レーター等の欠陥へ与える影響、そしてシートへの応用加工技術で
あるレーザーマイクロ加工について解説する。
第1節 ドクターブレード法
1.積層電子セラミック部品の製造プロセス
2.ドクターブレード法の原理
3.シート物性に影響を及ぼす因子
第2節 スロット・ダイ法
1. スロット・ダイ法とは
1.1 スロット・ダイ方式の原理 1.2 オフ・ロールとオン・ロール方
式
2. 高速・薄膜成形のための要件
2.1 リップの形状 2.2 成膜厚みとクリアランス 2.3 成膜
速度と粘度
2.4 成膜厚みと速度 2.5 スロット・ダイのリップ厚み
3. スロットダイ方式による成形ライン
3.1 乾燥炉 3.2 スロット・ダイとスラリー 3.3 薄膜成形の条
件
第3節 グリーンシートへのビアホール加工技術
1. 実験方法
1.1 セラミックスグリーンシート 1.2 レーザードリリング
1.3 積層チップインダクターと高周波積層モジュールの試作
2. 結果および考察
2.1 セラミックスグリーンシートの光学反射性
2.2 レーザードリリング加工
2.3 積層チップインダクター
2.4 800MHzデジタル携帯電話用高周波パワーアンプモジュール
第5章 焼成技術と焼結体の微細構造制御
焼成プロセスを最適化するにあたっての有効な評価法と反応機構を
明確にするための観測・測定法の解説。そして、低温・短時間焼結を
可能とするマイクロ波焼結法とそれによって得られた焼結体の電気
的、機械的特性および微構造について従来の電気炉焼結体と比較
した結果とその評価などについて解説する。
第1節 焼成条件の最適化とその管理
1. 焼成過程に影響を及ぼす因子
2. 加熱速度および冷却速度の影響
3. 焼成温度の影響
4. 焼成時間の影響
5. 焼成雰囲気の影響
6. 焼成時の加圧の影響
第2節 焼成プロセスの分析・評価技術
1. X線回折法(XRD)
2. 熱分析法
2.1 示差熱天秤(DTA―TG) 2.2 発生気体分析(EGA)
第3節 マイクロ波加熱による焼成技術
1. ZnOバリスタ
1.1 バリスタ特性 1.2 添加剤の誘電特性
2. PZTアクチュエータ
2.1 均一焼結法 2.2 焼結体の微構造 2.3 焼結体の特性
3. コンデンサー内蔵多層セラミックス
3.1 焼成条件 3.2 多層セラミックスの特性 3.3 焼成メカ
ニズム
第4節 焼成中における微細構造の制御
1.MnZnフェライトの相平衡
2..MnZnフェライトにおける焼成条件と微細構造
3.MgZnフェライトにおける焼成雰囲気と微細構造
第5節 焼成体の構造とその測定・評価
1.はじめに
2.焼結体の構造
3.微細構造の観察
4.微細構造の定量
5.3次元構造の推定
6.その他の微細構造
第6章 焼結体の微細構造に与える各工程パラメータの影
響 (粉体・成形体・添加剤・焼成 etcの影響)
焼結体の微細構造は製造プロセスに大きく依存するためどの様に
微細構造を設計・管理するかは重要である。この章では特に誘電体
材料の組成や焼成温度、焼成中の反応によって生成される二次相
や緻密化のメカニズムの変化、粉体の活性度などについて解説す
る。
1. 微細構造の重要性
2. BT-Nb-Co系における組成の影響
3. BT-Mg-Re系における組成の影響
4. 粉体活性度の影響
第7章 脱バインダ工程とその最適化
脱バインダ工程を適正化するための要因は多岐に渡っており、また
その解明が困難である。この章ではその脱バインダ工程を適正化
するためにバインダの挙動、問題点およびその解決策について実
際に工程を管理しているメーカーと分析メーカーからの視点で解す
る。
第1節 脱バインダ技術とその最適化
1. 脱バインダ工程最適化の必要性
2. バインダの熱分解挙動
2.1 PVBの熱分解挙動 2.2 アクリル系樹脂の熱分解挙動
3. 脱バインダ工程に用いる装置
第2節 脱バインダ工程における熱解析とその評価
第8章 低温焼成プロセスの確立とその応用
低温焼結セラミックスとその多層基板技術は高周波回路のモジュ
ール化に最適である。この章では、低温焼成多層セラミック基板の
特徴と評価法、そして小型化、信頼性向上、ノイズの抑制がが可能
となる低温焼結セラミック多層モジュールにおける材料およびプロセ
ス技術と実装・設計技術について解説する。
第1節 原料粉末 ガラスセラミックス
1. 原料料粉末組成系
1.1 ボロシリケート系 1.2 アノーサイト(Ca
長石)系
1.3 その他の長石系(Ba長石、Sr長石) 1.4 コージエライト系
1.5 ディオプサイド系 1.6 チタン酸ランタノ
イド系
2. 原料粉末製造プロセス
2.1 溶融プロセス 2.2 粉砕プロセス
3. 原料粉末の評価
3.1 粒度測定
3.1.1 レーザー回折法 3.1.2 比表面積測定
3.2 熱膨張係数測定
3.3 示差熱分析測定
3.4 組成分析測定
第2節 低温焼成多層セラミック基板
1. LTCC基板の種類とその特徴
1.1 ボロシリケートガラス+アルミナ 1.2 長石系結晶性系
ガラス+アルミナ
1.3 コージエライト系ガラスセラミックス 1.4 ディオプサイド
系ガラスセラミックス
1.5 チタン酸ランタノイド系ガラスセラミックス
2. LTCC基板に求められる特性とその評価方法
2.1 誘電率と誘電損失 2.2 曲げ強度 2.3 熱膨張係数
2.4 ヤング率 2.5 熱伝導率
3. LTCC複合基板
3.1 複合基板の用途 3.2 収縮挙動マッチング
3.3 熱膨張係数マッチング
第3節 低温焼結多層基板におけるモジュール化技術
1. 低温焼結セラミック多層モジュールの特徴
2. 低温焼結セラミック多層モジュール製品例
2.1 RFダイオードスイッチ
2.2 デュアルバンド対応アンテナスイッチ・ダイプレクサ
2.3 受信フロントエンドデバイス
3. 低温焼結セラミック多層モジュールに使用される材料系、および
プロセス技術
4. 低温焼結セラミック多層モジュールの部品実装技術
5. 低温焼結セラミック多層モジュールの設計手法
第9章 各種セラミック電子部品の製造とその要素技術
第1節 携帯電話用積層セラミック電子部品
1. セラミック多層基板とパッシブ・インテグレーション
1.1 セラミック多層基板を応用した電子部品
1.2 積層セラミック電子部品の製造工程
1.3 セラミック多層基板のデザインルールと設計法
2. 携帯電話の高周波回路ブロック・ダイヤグラム
3. セラミック多層基板を応用した受動部品
3.1 ロー・パス・フィルタ 3.2 バンド・パス・フィルタ
3.3 ダイプレクサ
3.4 カプラ(方向性結合器) 3.5 バルン 3.6 ア
ンテナ・スイッチ
4. パッシブ・インテグレーションの応用例
4.1 フロントエンドモジュール
4.2 アクティブ素子を実装した応用例 ~パワーアンプモジュール
~
第2節 多層セラミック基板
1. 典型的材料・プロセス技術
2.材料技術 (セラミックス)
2.1 材料組成・構造と各種特性 2.2 焼結挙動
3. プロセス技術 (金属/セラミックス同時焼成)
3.1 材料反応制御 3.2 焼成収縮ミスマッチ
第3節 積層セラミックコンデンサ
1.はじめに
2.誘電体材料
3.Ni電極
4.まとめ
第4節 圧電セラミックス
1. 圧電セラミックス部品の製造技術
1.1 材料粉末の調整
1.1.1 粉末混合法 1.1.2 コロンバイト法
1.1.3 酸化鉛過剰組成法 1.1.4 湿式合成法
1.2 成形
1.2.1 プレス成形法 1.2.2 押出し成形法
1.2.3 シート成形法
1.3 焼成
1.4 電極形成
1.5 分極
1.6 接続と固定
1.7 検査
2. 製品にみた要素技術
2.1 発音体、バイモルフ 2.2 高精度アクチュエーター
2.3 圧電トランス 2.4 超音波加工機
3. 新しい要素技術
3.1 シュミレーション 3.2 AD法