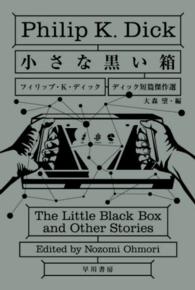出版社内容情報
中国諸地域の多源的文化から巨文明が生成する過程を生態学的区系類型考古学説から捉え、中原中心の王朝史観を超えた歴史理論と、二一世紀中国の多元一体の構成をもつ「中華民族」の地政学的布置を明示。「世紀の書」と称えられる問題作。
【主な目次】日本語版序 火花を捕捉する(郭大順)/はじめに/第一章 二つの怪圏/第二章 学読「天書」/第三章 解悟と頓悟/第四章 「区系」説[(一)燕山南北長城地帯を重心とする北方/(二)山東を中心とする東方/(三)関中、晋南、豫西を中心とする中原/(四)環太湖を中心とする東南部/(五)環洞庭湖と四川盆地を中心とする西南部/(六)鄱陽湖―珠江デルタ一線を中軸とする南方]第五章 星が天に満つ/第六章 三部曲と三模式/第七章 二つの接続/解説 中華文明起源の謎を解く(陸思賢)/附・中国考古学文化区系年表/蘇秉琦略年譜・著作/郭大順・陸思賢略歴/編集註記/収録図版170点
【本書の内容】
◆中国文明の起源を語るとき、「夏王朝」の成立と中原の「二里頭文化」を直結させる史観は、夏―商―周という三代の王朝の流れを中心に歴史を語る「中原史観」をもたらすが、
それでは中国諸地域文化が保持してきた多元性を一体として束ねる中国文明・中華民族の「認同(アイデンティティー)」をもたらすことはできない。
◆中国文明・精神伝承の象徴といえる「華(花)」の起源は仰韶文化に、「龍」の起源は北方の遼河文化にあり、その結合が「紅山文化」にあらわれた。やがて、この結合は山西省南部(晋南)の「陶寺文化」において、山東龍山文化、長江下流域の良渚文化などの流れをも吸収し、多元的な文化を統合した古国を生んだ。
◆この多元性が一つの文明へと融合する過程を提示する「生態学的区系類型考古学説」と、「三過程(古文化―古城―古国)」「三部曲(古国―方国―帝国)」「三模式(原生型、次生型、続生型)」という三つの国家発生・展開の歴史理論によって、著者は中国文明・中華民族の起源から、21世紀中国の国家像・文明像までを構想・提示しようとしています。
◆考古学研究者が現代中国の文明像をまでを構想するというこの壮大な試みがあったことを、日本の中国研究者はこれまで十分に紹介しようとはしてきませんでした。著者の構想にたいして、日本の知識人がいかに相対することができるかは、とても大切なことと考え
ます。詳しくは、本書の「編集註記」をご覧ください。
蘇秉琦〈ソヘイキ〉は、1909年河北省生れ。1934年、北京師範大学歴史系卒業とともに、国立北平研究院に入所、史学研究会考古組に配属され、主任の徐炳昶の指導のもとで、宝鷄闘鷄台遺跡を発掘、日中戦争のなか、発掘遺物と資料とともに雲南の省都・昆明に移り、その成果は1947・48年にはじめてまとめられる。この報告書に付された「瓦鬲の研究」が戦後中国考古学研究の重要な出発点の一つとなった。1949年、中華人民共和国成立。1952年、北京大学史学系に考古教研室が生れ研究主任となる。今日の北京大学考古系の創設者であり、そこから多くの研究者が育ち、戦後中国考古学の流れに大きな影響を与えることとなった。1979年、中国考古学会成立、初代理事長は夏鼐、著者は副理事長。1986年、中国考古学会第二代理事長。1997年6月30日、北京にて死去。この日は、香港が英国による植民地統治を終える最後の日であり、6月17日、香港商務印書館から病床の著者に本書が届けられた。その意味で、本書は、著者の思想の全てを尽くして中華民族の未来へ向けて語ろうとした遺書ともいえる。
内容説明
東アジアの大地に生まれた諸地域古文化・古国の多元性を生態学的な区系類型理論によって捉え、その分裂変化・闘争・融合がやがて中国の巨文明を創りあげる道筋を描き、中原中心の王朝史観を超えた歴史理論を提示する問題作。
目次
第1章 二つの怪圏
第2章 学読「天書」
第3章 解悟と頓悟
第4章 「区系」説
第5章 星が天に満つ
第6章 三部曲と三模式
第7章 二つの接続
解説 中国文明起源の謎を解く(陸思賢)
-
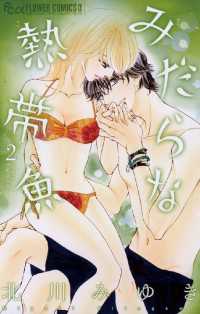
- 電子書籍
- みだらな熱帯魚(2) フラワーコミック…
-

- 和書
- 劇あそび絵本