内容説明
日々回転しつづけるわたしたちのこの世界はフンコロガシに押されていく糞の玉だ。その中で他人の生き血を吸うことに明け暮れる蚊=ビジネスマンが飛び回り、闇の中で光の意味について蛾=若者が語り合い、いつか陽の目を見ようと単調な穴掘り仕事をつづける蝉の子=労働者が這いずっている。人生は虫の生活に似ているなどと思ってはいけない。宇宙に行き交うものすべてが変態を続ける虫の自我の現れなのだから―カフカの『変身』で始まった二十世紀の文化を締めくくる小さく深い虫物語。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
兎乃
25
ほんとに面白かったです。ペレーヴィンの小説はまったく解放されている。人と虫が接続され、輪郭線は無く、空間を超え、自我というウンコと一体になって転がる。自分自身の死体と格闘する蛾のミーチャ。「さっききみは下に落っこちた。井戸の中にだ。覚えてるか?今度はまっすぐ上に落ちてみろよ」。カフカ的不条理でもなく、奥泉氏の人間から変態していくザムザでもなく、はじめっからの虫。思わず笑ったりしながら、身につまされつつ、スゲーなぁって読んだ。行ったり来たりで3度繰り返して読んでしまった(笑)2012/11/25
きゅー
16
人間として生きながら、いつの間にか彼らが蝿、蚊、蟻でもあるという不思議な状況。このめくるめく世界は、通常の感覚世界をはるかに超えており理解しづらい。理解しづらいのは所々で哲学的な問答が挿入されることも理由の一つ。ペレーヴィンはそうした問いを、他の作品でも展開させているが、特に本作では人間であることへの問いを、人間とはかけ離れた生活環境を持つ「虫」を媒介としており、彼の問いの深さと狭さはより一層強まっている。ナボコフ的であり、エロフェーエフ的であり、この迂遠さが現代ロシア的なのかもしれないが、面白さは格別。2012/10/08
ふくろう
13
ダンディなお父さんが、子供にやさしく糞の塊を手づかみで与えるシーンに吹いた。子供は糞をうやうやしく受け取り、自分の糞の玉を作り出す。そして父子は前足で糞の玉を転がし、地球を転がし、ハイヒールのかかとに踏まれるのである。マクロ眼鏡とミクロ眼鏡を二重にかけたら、きっとこんな感じかもしれない。焦点がちっとも合わず、視界がぐらぐらくる。話は重いんだけどどこまでも軽い。まるで命のようだねと嘯きながら、今日もきっと私は蚊をつぶす。ぷちっ。2010/08/28
南禅寺の小僧
6
「すげえや……音も立てずに飛んでるぜ」 「これがアメリカってやつだ」なにこれ最高。2010/12/21
保山ひャン
5
人かと思えば実は虫。虫の生態が話のミソで面白い群像劇。人生を語り、ポストモダニズムを語り、マルクス・アウレリウスに寄せる詩を詠んだりするが、コウモリに襲われたりDDTに悩まされたり、葉っぱもろとも巻かれて喫煙されたりする。随所に哲学的なやりとりがある。献血に頼って生きてきた虫が、一念発起して血を吸いに行って撃沈したり、母子喧嘩で「蠅として生きる」と飛び出した蟻が早速ハエトリ紙にくっついてしまったり、おまえはゴキブリだと言われて落ち込んだり。2017/03/31
-

- 電子書籍
- 幸薄名器ちゃんと絶倫エリートくん むさ…
-

- 電子書籍
- 武道独尊【タテヨミ】第135話 pic…
-
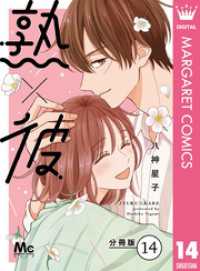
- 電子書籍
- 熟×彼 分冊版 14 マーガレットコミ…
-

- 電子書籍
- 闇のアレキサンドラ もうひとりのわたし…
-
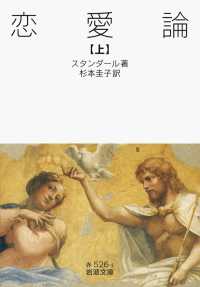
- 電子書籍
- 恋愛論 上 岩波文庫




