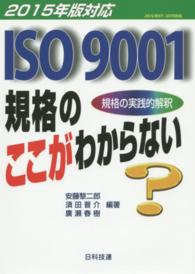内容説明
エネルギーの喪失、方法論の欠如…。“形骸化した伝統”に息吹きを与える“異端の思想”が今こそ甦る。伝統芸術の根源に迫る「ナンバ論」をめぐる二大鬼才の対談。
目次
1 ナンバ的なるもの(ナンバの足跡;「腰を入れる」と「腰を落す」;行進・合唱・遠近法)
2 ナンバの「音」(音づかい;「音」と音程;男の声 女の声)
3 近松と南北(近松―一人称の思想;河内語;問屋語エスペラント;南北―荒唐無籍のナゾ)
4 ナンバの喪失から批評の可能性(ナンバが消えた;テレビ―極限的反ナンバ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yonet35
4
この本、読めば読むほど・・・明治十年生まれ以前の名人の芸を見たくなる。実際にそういう名人の空気感を味わえない、現代の歯がゆさでいっぱいになる。近松や南北、近松半二、大阪の言葉、文楽の流れの歴史を感じられ、面白かった。2011/08/31
筋書屋虫六
2
「武智歌舞伎」のリアルな時代は知らないけれど、その知識教養の深さや慧眼・審美眼は現代では変わる人物がないのだろう。富岡さんでなければ相手になれないと思わせる刺激的な二人の対談。伝統芸能愛好者や研究者からイデオローグとしての自覚をうながす「ナンバ」の発見と理論化。日本の芸能の原点は『農の原理』に立っている。歌舞伎はある意味では天保時代にもう存在価値を失っていたと。今の私達が「伝統」だと思っている歌舞伎は、それ以後に作られた團十郎の十八番や明治の名人の芸を基準にしてますよね。伝承とともに批評の大事さを痛感。2013/03/17
がんちゃん
1
武智歌舞伎の理論的ベースは「ナンバ」と「息をつめる」こと。そして日本の伝統芸術の原点は「農の原理」に立っており、それは水田農耕の「原初生産性」のなかでこそエネルギーが形作られるということ。話は古代史にまでおよび、なかなか興味深い内容でありました。2015/01/14
-

- 洋書
- Mama's Books
-
- 洋書
- Civil War