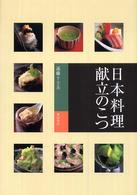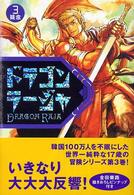- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
内容説明
ひきこもりを取り巻く高年齢化、‘親亡き後’という迫りくる難題、現実社会に潜むアポリアを明らかにし、警鐘を鳴らす渾身の書き下ろし。
目次
序章
第1章 文学に描かれた「ひきこもり」
第2章 ひきこもりか、無業者か―厚生と労働のはざま
第3章 文学に描かれた変哲な面々
第4章 近代社会の中でフリーズした人々
第5章 社会の感受性の中で
第6章 世間という足かせ
第7章 ねじれの位置をめぐって
著者等紹介
鈴木信子[スズキノブコ]
1971年宇都宮市生まれ。1990年栃木県立宇都宮女子高卒業。1994年慶應義塾大学文学部卒業。1995年報道記者として地方紙に入社。地域報道部やくらし文化部に所属し、社会問題を中心に取材。連載も多く執筆した。2012年発達障害に関する大型連載にて、「科学ジャーナリスト大賞2012」(日本科学ジャーナリスト会議選考)大賞受賞。フリーランスに転身(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
6
クレイジーJAPANカルチャーの代表の一つとして有名な引きこもりに関する調査で実は最も圧倒的に多い原因が、イジメでも家庭問題でもなく「その他」という謎。通常の実証的分析によっては解明できない深淵にドストエフスキーやポーやユイスマンスら文学の助けを借りて、フーコーの権力論も参照しつつ本書は分け入っていく。それら世間から閉じ籠り内省の悪循環を重ねる文学的形象たちが共通して怨嗟する言葉に、近代化が進行するにつれて全面化した利益追求を最重要視する合理主義への反発と、だがそこに乗れない自分への反感や迷いを読み取る。2023/12/10