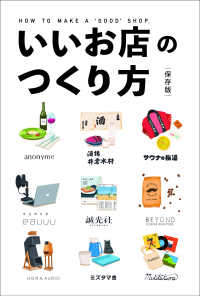出版社内容情報
文学、映画、音楽、ポップカルチャーは、冷戦という<戦争>の武器だった。ソフトパワーを兵器とした情報戦は、いかにして政治的・文化的・社会的機能を果たしたのか。
本書は、冷戦文化研究においてアメリカの影響力の色濃い韓国・台湾・日本・フィリピン・インドネシア等のインターアジアを中心に、冷戦の始まりとされる一九四五年を以前と以降に分断せず、貫戦史的な視点で文化の反復性・連続性・再活用面に注目した論集である。
内容説明
文学、映画、音楽、ポップカルチャーは、冷戦という“戦争”の武器だった。ソフトパワーを兵器とした情報戦は、いかにして政治的・文化的・社会的機能を果たしたのか。本書は、冷戦文化においてアメリカの影響力の色濃い韓国・台湾・日本・フィリピン・インドネシア等のアジアを中心に、一九四五年を以前と以降に分断せず、貫戦史的な視点で文化の反復性・連続性・再活用面に注目した論集である。
目次
第1部 日本(新しい女性に捧げる『赤毛のアン』―村岡花子と戦後アメリカの文化政策;占領者から親しい「隣人」へ―冷戦期の日米親善と庄野潤三『ガンビア滞在記』における「アメリカ」 ほか)
第2部 朝鮮半島(デアドラ論は完成されていない―李孝石の「緑の塔」(一九四〇年)における失敗の諸相
崔載瑞の「マッカーサー」―マッカーサー表象を通じてみた、ある親日エリートの解放前後 ほか)
第3部 台湾(「米国広報・文化交流局」(USIS)と台湾文学史の書き換え―アメリカ援助体制下の台湾・香港における雑誌出版の考察を中心に
東西冷戦下の台湾における「中国派」比較文学の誕生―中華文化復興運動と台米関係の視点から)
第4部 インターアジア(東アジア的モダニズムをめぐって;林語堂、「東洋」と「知恵」の政治性―一九五〇~六〇年代韓国における林語堂ブームと「二つの中国」 ほか)
著者等紹介
越智博美[オチヒロミ]
専修大学国際コミュニケーション学部教授。米文学
齋藤一[サイトウハジメ]
筑波大学人文社会系准教授。英文学
橋本恭子[ハシモトキョウコ]
日本社会事業大学非常勤講師。比較文学・台湾文学
吉原ゆかり[ヨシハラユカリ]
筑波大学人文社会系教授。英文学
渡辺直紀[ワタナベナオキ]
武蔵大学人文学部教授。韓国文学・文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。