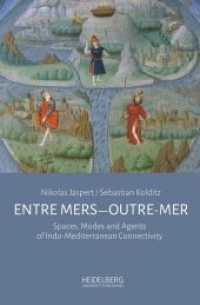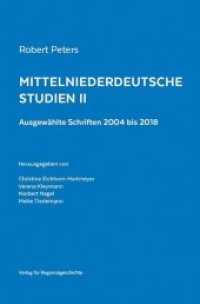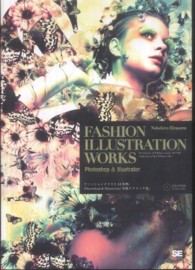目次
第1章 多元文化の実践詩考(多元文化受容とポスト・モダニズム;「現代詩」は難解か;堀田孝一『匂う土』とボルヘス;韓国の詩と日本の詩;「抵抗する叙情」―尹東柱と日本の詩人;沖縄からのメッセージ;沖縄旅行の思い出―多元性と独自性そして独立への道;マイノリティの詩観と「女と国家」;私の現代アイルランド詩の翻訳について;二〇〇六年度イェイツ・サマー・スクールに参加して ほか)
第2章 理想の自然と異郷のふるさと(ヘルダーリンとハイデッガー―ヘルダーリンにおける「ギリシア的自然」と「ドイツ的自然」;ドイツでの思い出;「伝統」と「革新」―ドイツ旅行の思い出と中山直子『春の星』;ワーズワース『叙情民謡集』における叙情;「故郷喪失」と「ふるさとハンティング」―佐藤亨氏『異郷のふるさと「アイルランド」国境を越えて』について;テロと愛と平和とナショナリズム―二〇〇六年度イェイツ・サマー・スクール参加(於・アイルランド・スライゴー)
「イニスフリー湖島」の思い出
自然と生命と美と喜び―現代のインド詩と日本の英語の俳句に見る「平和」
「宇宙と自然と生命の歌」―現代インド詩人V・S・スカンダ・プラサッドの詩・続
種まきと緑と収穫の詩―岡隆夫に見る「農耕詩」の可能性 ほか)
第3章 周辺(フリンジ)の詩人たち(インドの詩人 アフターブ・セットの詩;アイルランドの詩人 ジェイムズ・フェントン;オーストラリアの詩 ヘンリー・ローソン;オーストラリアの詩 モリー・ケネリー;オーストラリアの詩 A・B・パターソン)
第4章 多元的な日本文化(鳴海英吉と演歌的叙情;「歌」の復権;追悼―木島始とその仕事;木島始編・野村修訳『ブレヒト詩集』について;口語体会話とライト・ポエムの可能性―木島始の翻訳言語について;マイノリティとしての私の詩;岡本かの子の印象―『老妓抄』のことなど;樋口一葉の短歌と『たけくらべ』について;日本の短歌と「狂」の思想;ジャック・ケアルックの俳句 ほか)
第5章 平和と原爆詩運動(芸術としての戦争詩;日本初の完全英語版アンソロジー『戦争と平和詩集』―対訳方式から完全英語版詩集への道;核廃絶に向けて・内と外からの「ヒロシマ・ナガサキ」―高炯烈『長詩 リトルボーイ』と多喜百合子、エルネスト・カーン共著『大量虐殺』;池山吉彬『都市の記憶』―詩人の仕事と使命をめぐって;長津功三良『影たちの墓碑銘』―歴史意識とコミュニティへの努力;御庄博実『原郷』―告発する美しい精神;スイスにおける「原爆体験」―浦上天主堂「黒いマリア像」との出会い;『原爆詩一八一人集』について―英語版を中心に;東大論争四十周年・「開かれた大学」への道―東京大学と東洋大学に於ける「原爆詩」イヴェント;御庄博実氏「核はと人間は共存できない」―ヒロシマ再訪・ヒロシマの詩人との出会い ほか)