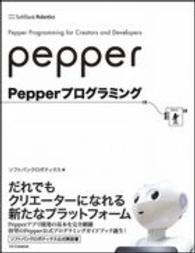内容説明
「考えること」を体系化。小さい要素に分解する「分析」、単純なものから複雑なものへ「総合」、すべての要素を列挙する「枚挙」。
目次
第1章 考えること(多面的思考;論点の設定;要素への還元;演繹的推論と機能的推論)
第2章 分解すること(因果関係;体系化;構造化;フレームワーク)
第3章 チェックすること(仮説思考;比較思考;整合性;網羅性)
著者等紹介
岡本義行[オカモトヨシユキ]
法政大学専門職大学院。イノベーション・マネジメント研究科教授。経済学博士。1947年生まれ。京都大学大学院経済研究科博士課程単位取得退学。企業・産業の国際比較を研究。特にイタリアの中小企業経営、ファッション業界に詳しい。産業集積、「まちづくり」や地域振興に関する政策を研究する一方、ベンチャー企業の育成、中小企業支援を手がける
江口夏郎[エグチナツオ]
株式会社ライトワークス代表取締役社長。法政大学学術担当教授兼任。1965年生まれ。エール大学ビジネススクール修了、東京大学卒。農林水産省、株式会社グロービスなどを経て現職。企業の人材戦略の立案、キャリア開発の支援などで実績を残す。主に上場企業の従業員に対してクリティカル・シンキングの講演、講習を多数おこなう(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Masataka Shindo
0
各人の思考のフレームを「パラダイム」と言い、論理的に正しくてもパラダイムを理解していなければ同意を得ることは出来ない。相手を説得する時に本当に大切なのは、筋が通っているかではなくパラダイムを理解して説得できるかということ。2013/12/13
ミッキー
0
論理的に考える方法について、とてもコンパクトにまとまっている。それでいて背景は古典に裏付けされている。忙しい人に薦めたい。2012/12/13
keiichic
0
社会人のヒューマンスキルについて大きく影響を与えてくれる本。多面的思考、論点の設定は特にクリシンの核となるものだと思う。2009/09/01
arbores
0
考える技術・書く技術と99.9%は仮説の考え方を含んでいるように感じた。各説明において例があるのでわかりやすかった。| 論理的に見ることを基本にして、批判的に見る。分解・統合・チェック2009/05/13