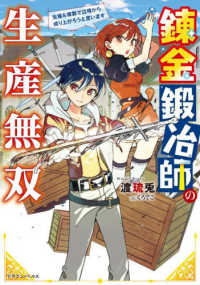内容説明
いつ、どこで、どのような状況で人生の幕が降りても「これでよい」といえること。死を迎える日のための17カ条をとおして、日本的な看取られの在りようを解く。
目次
人として生まれることは難しく、今あるいのちが有難いこと
人はいつか必ず死を迎えるものであると自覚すること
日々、生死一如と心得て生きること
死ぬとき・死に方・死に場所を平生より思いえがくこと
限りあるいのちの短さを知ることは、死に支度には必要なこと
死ぬということは、この世からあの世へと旅立つこと
自分の「願い」を第一にして看取られること
死に向かう過程で生じる五つの苦しみを心得ておくこと
看取ってくれる人々の役割・立場を心得ておくこと
看取られるということは、本人のみならず家族も含めて見護られること
看取られる者・看取る者共々に目指すのは、「救い」ということ
自分の生き様・死に様を決めるのは、自らの生死観であるということ
看取りの善し悪しは、看取りを受ける本人が決めること
死を迎える日に、心残りや憂いがないように努めること
死にゆくとしても、言いたい放題、わがまま放題は避けること
自分の臨終・死後処置については、自身の願いを伝えること
死に向けて心得ておくべきことには、看取られた後の事柄も含まれること
著者等紹介
藤腹明子[フジハラアキコ]
1947年、滋賀県生まれ。国立京都病院附属高等看護学院卒業。佛教大学文学部佛教学科卒業。元飯田女子短期大学看護学科教授。仏教看護・ビハーラ学会会長。日本死の臨床研究会世話人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。