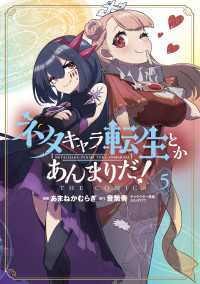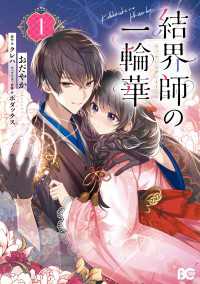内容説明
日本の近代銀行業務の夜明けは、1863年(文久3年)外国銀行の日本進出とともに始まった。幕末開港にともなって日本の外国為替業務を一手に担った在日外国銀行は、第二次世界大戦終了後の占領期には再び対外決済業務を独占するに至ったが、戦後のインパクトローンの供与などその果たした役割は計り知れない。いまここに在日外国銀行の全貌を、一気に書き下す。
目次
第1編 一九世紀後半期―幕末開港から条約改正まで(外銀の本邦進出;外銀の業務活動;わが国通貨主権と外国銀行洋銀券 ほか)
第2編 二〇世紀前半期―新通商条約改正から平和条約まで(明治後期(一八九九・七~一九一二・七)
大正期(一九一二・八~一九二六)
昭和戦前期(一九二七~一九四五・八) ほか)
第3編 二〇世紀後半期―平和条約からバブル崩壊まで(経済成長期(一九五二・五~一九八〇)
金融自由化時代(一九八一~二〇〇〇)
経営戦略の成功と挫折)
在日外銀一四〇年の総括(一八六三~二〇〇三)
著者等紹介
立脇和夫[タテワキカズオ]
1935年島根県出雲市にて出生。1959年神戸大学経営学部卒。1961年フルブライト奨学金により、米国ワシントン大学大学院留学。1962年帰国、日本銀行調査局、米コンチネンタル銀行東京支店、長崎大学経済学部、静岡県立大学国際関係学部勤務を経て、1992年早稲田大学商学部教授、経済学博士。専攻は国際金融論
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。