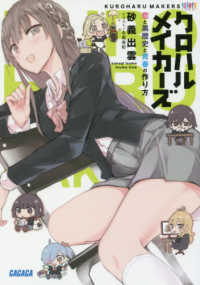内容説明
思い出はモノクロームで蘇る。過去の事でもあり、現在の事でもある沖縄の“復帰後”。一九七二年の日本復帰から現在まで沖縄で起こった印象的な出来事を個人の思い出とクロスして描くユニークな沖縄現代史。社会風俗から時事問題まで硬軟織り交ぜて語る、懐かしくも切ない“我らが時代のフォークロア”。
目次
一九七〇年代―「車は左 人は右」、じゃあ沖縄は?(一九七二年―ドルから円への通貨交換;一九七五年―「ダイナハ」オープン ほか)
一九八〇年代―「ヤマトンチューになりたくて、なりきれない」(一九八一年―具志堅用高、敗れる!;一九八一~八二年―断水326日 ほか)
一九九〇年代―「オータ」と「アムロ」の時代(一九九〇年―大田昌秀革新県政誕生;一九九一年―喜納昌吉、紅白出場 ほか)
二〇〇〇年代以降―「苦渋の決断」はもういらない(二〇〇〇年―「沖縄サミット」開催;二〇〇一年―ドラマ「ちゅらさん」ブーム ほか)
著者等紹介
新城和博[シンジョウカズヒロ]
1963年沖縄・那覇市生まれ。城岳小学校、上山中学校、那覇高校をへて、琉球大学法文学部社会学科社会人類学コース卒業。現在ボーダーインクにて編集者として勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
二人娘の父
7
社会学的に言えば「ライフヒストリー」あるいは「ライフストーリー」なのだろうか。個人的な生活史と復帰後の沖縄の歩みを重ねることで、復帰年にヤマトで生まれた私にも、リアリティを持ってその歩みが迫ってくる。常に沖縄との距離を測りかねている自分のような人間にとって、とても新鮮かつ考えさせられる生活史である。紹介したいエピソードはたくさんあるが、私がすでに見ることができない、海洋博にあったというアクアポリスが非常に気になった。私の中に沖縄が出てくるのはやはり1995年なのだということも再認識した。2021/05/18
Kazuki7701
7
沖縄旅行の帰りに読むため購入。沖縄復帰後からオスプレイ配備まで様々な沖縄での出来事が沖縄の人からの視点で書かれていて新鮮だった。主に著者の経験や感想を実直に述べており、政治的メッセージも無く話がリアルで読みやすい。特に復帰後の話は、沖縄が他の国に占領されていたという実感を持つ事ができた。沖縄旅行で米軍基地の存在をひしひしと感じていただけに、以前よりは少しだけ沖縄の人の感情を理解できたかなと感じている。2016/03/22
kou
1
著者が復帰後の沖縄を著者の視点で振り返る随想録。読みやすく面白かった。何が面白いかと言うと、その時代に生きてなかった自分からしたら当時の状況というのは新聞や沖縄関連本から事実としてしか読み取れないが、その時代を実際に過ごしていた人の回想によって肌感覚で知ることができることであろうか。(もっとも書く人によって捉え方は異なるわけであるが)特に、1995年の少女暴行事件は沖縄の政治的転換のきっかけとなった出来事として有名だが、その時の県民の怒りやインパクトがいかほどだったかというところが興味深かった。また、沖縄2015/01/18
山内
1
非常に面白かった。著者の個人的な経験から語られる現代史だけど、著者と同じ空気、想いを当時私も共有したからか、多くの場面で同意した。大同小異、沖縄県民の根っこには必ず沖縄戦がある。愉快なフォークロアに笑いながら、しかし重たい過去も振り返らせてくれた。 本当は県外の方にも読んでほしいが、県民でないと分かりにくいかもしれない。きっと、ヤマトとこのシマの溝はまだ深いだろうから。2014/09/06
のんしおーね
1
沖縄が好きで何度も行ってるし、本も読んでいるので、いろいろ知ってるつもりだけど、やっぱり、そこで生まれ、育ち、生活している人にはかなわないなーと改めて思った。身をもって体験しているという意味で。その時自分は何をしていたかなーと、思いながら読んだ。なかなか面白かった。2014/07/06