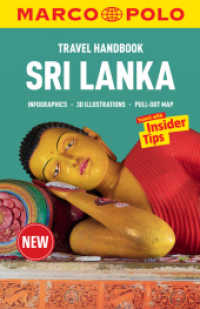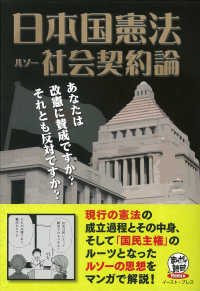内容説明
畳む、巻き取る、重ねる、仕舞う、しつらう。コンパクトに暮らす日本の知恵や工夫はどうして生まれたのだろうか。日々の暮らしの中で知らず知らず触れてきた日本のデザインの原点を探る22のお話。
目次
母と着物と鯨尺
真っ白な紙に心をこめて
時代劇見ながら思うこと―座蒲団
春もよし、秋もよし、の雲錦
屏風の前に座る人
入れ子のお椀の美学
箱から一人歩きを始めた蓋の話―乱れ箱
縁側でお月見
しまうための棚、見せるための棚
女の粋は足袋で決まる〔ほか〕
著者等紹介
長町美和子[ナガマチミワコ]
1965年、横浜生まれ。武蔵野美術大学卒業。婦人画報社にて住宅とインテリアの雑誌編集に携わり、1997年に独立。フリーランスのライターとして、建築、デザイン、暮らしの垣根なく執筆活動をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バニラ風味
21
着物を着るようになってから、いろいろな「これ、なんだろう?」という疑問が出てきました。「鯨尺」というものも、その一つです。時代や場所によって様々な尺があるようですが、その尺に、箪笥や畳のサイズなども合理的に関連していることがわかりました。日本ならではの「足袋」や「紙」「屏風」の歴史・変遷など、感心すると同時に「日本人ってすごい」と思わずにはいられません。「雲錦」「二月堂」も、すてきな言葉。日本の良さを再発見、再確認した気分です。2016/02/23
みさよ♪
2
着物の仕事に就いているので、鯨尺のことを知りたくて借りました。二月堂や入れ子など、名前すら知らないものもあって、昔の人の知恵や習慣など勉強になりました。田島家のお写真が素敵過ぎてため息がでました。特に、水盤に一輪の花を浮かべたり、簾戸などのおもてなしや工夫、丁寧に生きるって素敵だなと思いました。2017/08/13
キミタン
1
「反物の巾(36〜38㎝)は、肩巾または腰巾が織りやすい日本の織機の巾から来ている」…ふ〜ん、じゃあ西洋のヤード巾(91㎝)は身体のでかい西洋婦人の大きさから来ているんだろうか? 立体の鞄や靴を作るのは放牧民、平面の風呂敷や足袋を作るのは農耕民族。…そうなのか?2015/08/21
眠り姫
0
季節や風土、様々な知恵、何よりも思いやりが一つのものの形になる。身近にあるもの、環境の見方が変わりそう。2015/03/06
ymd
0
三ツ星!和寄りのミニマリズム探求。きれいだし、コンパクトで、風流なものがたくさん紹介されてます。2014/06/13
-

- 和書
- 遣唐使研究と史料