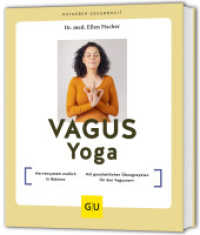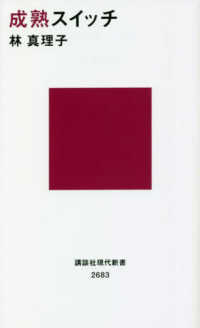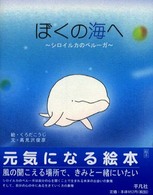内容説明
建築史家にして建築家の藤森照信が縦横無尽に、日本の極小空間=茶室に迫った。自ら国内外の茶室を手掛ける著者が書き下ろした渾身の力作。
目次
第1章 茶室に目覚めたわけ
第2章 日本の茶室のはじまり
第3章 利休の茶室
第4章 利休の後
第5章 建築家の茶室
第6章 戦後の茶室と極小空間
第7章 茶室談義・磯崎新に聞く だから、茶室はやめられない
著者等紹介
藤森照信[フジモリテルノブ]
1946年、長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。専攻は近代建築、都市計画史。東京大学名誉教授。工学院大学教授。86年、赤瀬川原平、南伸坊らと路上観察学会を結成し、『建築探偵の冒険・東京篇』を刊行(サントリー学芸賞受賞)。91年、「神長官守矢史料館」で建築家としてデビュー。97年、「赤瀬川原平邸に示されたゆとりとぬくもりの空間創出」で日本芸術大賞、98年、日本近代の都市・建築史の研究(『明治の東京計画』および『日本の近代建築』)で日本建築学会賞(論文)、2001年、「熊本県立農業大学校学生寮」で日本建築学会賞(作品賞)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
りー
7
利休の思考を追うところ、流石、建築探偵。スリリングでドキドキ。利休の先に一休宗純を見、更に釈迦の「犀の角のようにただ独り歩め」という教えを見る。「利休の探求の背後にあったのは、小乗の悟りだったにちがいない。人は一人、天地の間にあり、表現はそこからはじまりそこに帰る。」――メモ。待庵の建築の元は、戦場で陣に有り合わせでつくられた茶室。二畳は信長と安土城へのアンチ・テーゼ。利久以降の茶道と茶室の歴史。デ・スティール、バウハウスとの出合い。巻末に磯崎新さんとの対談を収録。あぁ、藤森さんの高過庵に行きたいなー。2019/05/18
Haruko
6
正午の茶事も英国のアフタヌーンティーも4時間 その理由から始まり、「世界で最も危険な建物10」に選ばれた自ら設計した眺望を誇る茶室「高過庵」と、極小茶室である利休「待庵」との繋がりまで、建築史上特異な存在である茶室を歴史的事実を踏まえて詳細に語る。数年前、イサムノグチ美術館で、プラスチックとトタンで茶室を製作中の碧眼の青年を奇異な目で見てしまった私こそ茶室の本質を知らなかったのである と自らの無知と傲慢を思い知らされた。2018/01/16
ムカルナス
4
著者は近代建築史が専門で茶の湯好きというわけではないけれど茶室の極小空間のプリコラージュ性(あり合わせの素材で仮設する)に魅せられ茶室に関わり続けている。専門用語だらけの茶室本と違い判りやすいし日本の建築史や文化、歴史の視点からみても興味深い本になっている。それにしても日本建築での様式主義(寺社建築と書院建築)を400年以上も前に打破し自由な発想であり合わせの素材で美的かつ実用的な茶室を考案した利休ってすごいなと改めて思った。 2016/06/13
Tomoka
1
闘茶に関する考察と藤森流茶室論が面白かった。その間の歴史の話が長い。2017/11/12
takao
1
ふむ2017/09/26