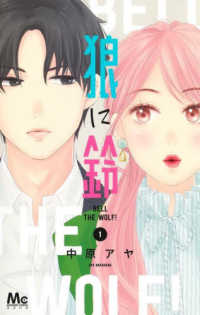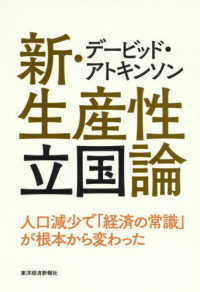内容説明
教養ある読者・聴衆の不在という特異な文化状況のなか、中世のラテン語はどのような変貌を遂げ、最終的にいかにして克服されたか?―不朽の名著『ミメーシス』の補遺との位置づけのもと、渡米後に満を持して筆を起こし、近代語成立前夜までのドラマを鮮やかに描き切った渾身の論集、待望の邦訳。
目次
序 もくろみと方法について
第1章 謙抑体(sermo humilis)
補遺 受難の栄光(gloria passionis)
第2章 初期中世のラテン語散文
第3章 カミラ―あるいは崇高なるものの再生について
第4章 西欧の読者とその言語
著者等紹介
アウエルバッハ,エーリヒ[アウエルバッハ,エーリヒ][Auerbach,Erich]
1892‐1957。1892年ベルリンに生まれる。ハイデルベルクで法律を、第一次大戦後グライフスヴァルト大学でロマンス語文学を学んだ後、マールブルク大学で教鞭をとるが、ナチス政権の誕生とともにイスタンブールへ亡命。1947年アメリカへ渡り、ペンシルヴェイニア、プリンストン、イェールの各大学に迎えられる。ロマニスト、文芸評論家として著名
小竹澄栄[コタケスミエ]
1947年神奈川県に生まれる。1976年東京都立大学人文科学研究科博士課程中退。2005年東京都立大学人文学部教授を退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
ラテン語は聖書を記す言語(著者は「謙抑体」と呼ぶ)ゆえに、中世初期に読者はいなかった。が、聖俗を混交するキリスト教的規範に従うアウグスティヌスは、俗語に近いラテン語で著述した、と本書はいう。一方、ゲルマン人の支配でゲルマン語がラテン語に混入し、聖職者の正しいラテン語教育と古典復興が起こる8世紀(カロリング・ルネサンス)、カール大帝のトップダウンのラテン語囲い込みによってラテン語と俗語の断絶が起こる、と著者はいう、が、中世末期、俗語側からラテン的な教養を読む者が出てくる。ダンテ以後、読者が出現するのである。2020/02/11
じろ
0
まずはアウグスティヌス。崇高な主題のために、崇高な文体を用いるでなく、低い文体、民衆的な題材を用いた。しかしその後のローマの凋落により教養ある読者は失われラテン語は民衆との繋がりを失う。そもそも中世前期には、読者は存在しなかった。カロリング・ルネサンスにおける古典復古は、ラテン語と民衆語の分断を決定的なものにすると同時に中世盛期を準備するものだっただろう。アウエルバッハがアウグスティヌスの文体と、世俗詩人としてのダンテの意義を書く様は、まるでバフチンがラブレーの民衆性を強調するが如く。2014/03/23
-

- 電子書籍
- 仕えたお嬢様がお坊ちゃまになった 第4…