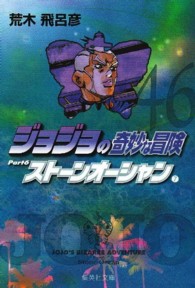- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
出版社内容情報
落人、木地屋、マタギ、ボッカなど、山間秘境を放浪し生活を営んだ民の記録。またその往来に欠かせぬ間道・峠道の果した役割、山の町・市場・湯治場についてなど。「旅の達人」宮本常一が描く、山間往来・放浪の生活文化誌。
内容説明
落人、木地屋、マタギ、ボッカなど、山間秘境を放浪し生活を営んだ民の暮しぶり、また往来に欠かせぬ間道、峠道の果した役割、山の市場・湯治場についてなど、山間往来・放浪の生活文化史。
目次
1 秘境の話
2 山人の道
3 間道
4 古い道
5 峠越え
6 山の町
著者等紹介
宮本常一[ミヤモトツネイチ]
1907年、山口県周防大島生まれ。大阪府立天王寺師範学校専攻科地理学専攻卒業。民俗学者。日本観光文化研究所所長、武蔵野美術大学教授、日本常民文化研究所理事などを務める。1981年没。同年勲三等瑞宝章(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nonpono
42
宮本常一が新刊本コーナに。20代、熊野古道を歩いた後かな、半分くらいわからないまま読んでいた。1907年生まれの宮本先生。初めて、民俗学、フィールドワークに触れる。20年ぶりに読めば、自分が旅した街、登った山、参詣したお寺が増え、昔より肌でわかるような。下界の人々が憧れた山という異界。そこに移動しながら生きるサンカの人々、マタギの人々。現実が苦しいからわたしたちは、実態がない漂泊に憧憬するのか。山は美しく厳しい。正規の街道にない、地図にもない道がたくさんあったのだろう。宮本先生の本は今も浪漫に溢れている。2025/02/20
ダージリン
4
山はなんとも言えぬ魅力がある。木地屋や平家谷はもともと関心を持っているトピックスでもあり、特に読んでいて面白かった。祖谷など、平家の落人伝説がある地は何ヶ所か行ったことがあるのだが、落人伝説をもつ各地を巡る旅をしてみたくなった。最近、南北朝に関心を持ち出しているので吉野もいずれ訪れてみたい。2025/08/16
Go Extreme
2
秘境に託す夢 山のあなた 山のあなた 山の手前の人々の夢 寺川郷談 祖谷山日記 秋山紀行 熊谷家伝記 米良 椎葉山 九州山地の秘境 焼畑生活 サンカ 後南朝 天ノ川 山村の人々の協力 吉野奥 霊地 人の魂の帰りゆくところ 山岳仏教 会津の木地屋 木地師 全国分布 三陸の塩 北上山中の塩道 塩田法 塩道 荷宿 塩と穀物の交換 秋葉街道 秋葉信仰 火伏せの神 鯨介往還 鎌倉と結ぶ道 ボッカ稼ぎ 九州山地の道 狩人 マタギ 国境の道 中国山地 鉄の搬出 山の湯治場 病気治療 人が集う 鉄穴流し タタラ炉 製鉄業2025/05/19
UCorsair
2
山と人。そこに道があり、人が住んでる/住んでいたということは、それなりの理由があるんだということに気付かされる。これから山中をドライブするときは、想像が膨らみそう。2025/01/01
-

- 和書
- 宮本恒靖学ぶ人