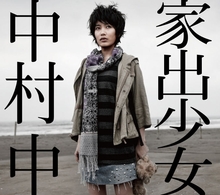- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
18世紀から20世紀初頭に、世界随一の緑の宝庫・日本と中国を訪れて未知の植物を導入し、ガーデニング大国イギリスの隆盛を支えた植物収集探検家たちの活躍を描く、定評ある原著からの邦訳。巻頭に、海を渡った花々を知るための「プラントハンター植物図鑑」を増補した決定版!図版・地図170点、詳細な訳註、参考年表などの資料も充実。
目次
第1章 日本を訪れたプラントハンター(鎖国日本と先駆者クライアー;ケンペルとツンベリー;シーボルト;ジョン・グールド・ヴィーチ;ロバート・フォーチュン ほか)
第2章 中国を訪れたプラントハンター(極東の地、中国;ジェイムズ・カニンガム;ピエール・ダンカルヴィル;第一次使節団;第二次使節団―クラーク・エイブル ほか)
著者等紹介
コーツ,アリス・マーガレット[コーツ,アリスマーガレット] [Coats,Alice Margaret]
1905‐78。イギリス・バーミンガム生まれ。在野の園芸植物史家として研究に傾注し、多数の著書を著す。また、そのかたわらでガーデニングにもいそしみ、外国産の珍しい植物を数多く栽培していた
遠山茂樹[トオヤマシゲキ]
1953年宮城県生まれ。早稲田大学教育学部卒業、明治大学大学院文学研究科西洋史学専攻博士後期課程単位取得満期退学。明治大学、玉川大学、千葉大学などの非常勤講師を経て、東北公益文科大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
26
現代では植物の国内外への持込や持出は簡単ではないが、大航海時代以降19世紀まで、まだヨーロッパに知られていない植物を追い求めてプラントハンターらが世界各地に派遣されたらしい。日本からはツバキやツツジ、ユリなどが持ち出され、逆に明治期以降バラなどが持込まれ盛んに栽培されたようだが、ジャガイモやトマトなどの食糧作物なら分かるが、時には大ケガや大病、死などの危険を冒してまで草花や樹木を集めた男たちが途切れることなく続いたことに驚く。彼らの功績と生涯が、年代順に簡潔に紹介されている本。冒険譚集としても読める。2021/04/15
belle
6
まさに東洋を駆けて美しく珍しい植物を貪欲に探し求める。「紅茶スパイ」でロバート・フォーチュンを、「空白の五マイル」でフランク・キングドン=ウォードを知ったが、他にも多くの植物収集家たちがいた。もちろんシーボルトも。日本も中国も欧米の脅威にさらされていた。ヨーロッパの植物園の隆盛を思う。18・19世紀にかけてはシノワズリー、ジャポニスムと東洋趣味が流行した時代。はじめに色刷りでキクやユリなど~プラントハンター植物図鑑~が付く。手描きの植物画に見惚れる。冒頭はアジサイ。ちょうど今は様々な種が雨に濡れて美しい。2021/06/15
りえぞう
2
なぜここまで植物を狩るのか? 博物学的な意味もあるとは思うが、それ以上に新たな園芸植物を入手したいという欲望はここまで深いのか。命がけでアジアの山奥に入り込んで植物を狩ったプラントハンターたちの情熱には感心するが、狩られて寒いところに連れていかれて、結果として枯れた植物たちも哀れだし……。2022/05/16
志村真幸
1
日本と中国を訪れたプラントハンターたちをひとりずつ取り上げ、その人物、旅程、獲得した植物などを並べていくもの。日本だとクライアーから始まり、シーボルト、フォーチュン、マキシモヴィッチ、マリーズ、イングラムといったひとたちが紹介される。 中国については、トーリン、ポターニン、ウィルソン、キングドン=ウォード、ファーラー、マイヤーなど。ひどい病気にかかったり、銃撃戦に巻きこまれたり、拷問死したりと陰惨なエピソードが目立つのも印象的だ。中国での植物採集は、かなり過酷だったらしい。 2021/02/11