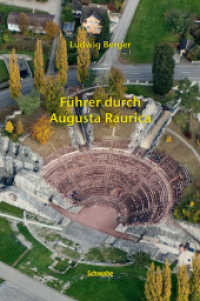内容説明
狂気・真理・権力・主体―これらのテーマを考えぬくうえでフーコーが作り出したさまざまな概念には、現代の社会とわたしたち自身を読み解く鍵が満ちている。一望監視装置が作りだす規律と訓練のテクノロジーと生の政治学の力関係のもとで、どのように生きるのか?異常とはなにか?真理はどのようにして真理として機能するのか?これらの分析をとおして新たな権力論を提示したフーコー。生涯、思想、著作を歯切れよく紹介し、二十世紀最大の思想家の全貌を明らかにする。フーコーの概念を道具のように使いこなすための入門書の決定版。
目次
第1章 ミシェル・フーコーの生涯(懊悩する青年 一九二六~六〇;『狂気の歴史』『言葉と物』の反響 一九六一~七〇;闘う知識人の旗手として 一九七〇~八四)
第2章 ミシェル・フーコーの思想―狂気・真理・権力・主体(狂気―理性の他者;真理―その条件と系譜;権力―生の権力;主体―その桎梏)
第3章 ミシェル・フーコーの著作(著書;講義録;インタビュー、評論など)
著者等紹介
中山元[ナカヤマゲン]
1949年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科中退。思想家・翻訳家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
11
定評のあるちくま新書のフーコー入門より、さらに取っつきやすく分かりやすいフーコー入門。生涯の伝記からキーワードで整理した思想解説まで、嘘のように分かりやすい。それだけじゃなくて、狂気論や権力論といった一般的なフーコーイメージに留まらず、後期の主体論、主体の美学にまで踏み込んでいて輪郭がより一層はっきりする。主体を捕えるありとあらゆる知、制度のメカニズムを系譜学的に暴露しながら、芸術としての生を探求する、ある意味古典的な思想家としてのフーコーがはっきり描かれていてオススメ2011/10/12
佐藤一臣
7
ロボトミー手術患者との邂逅がフーコーに絶大なる問いを与えたようだ。この経験は人間の根幹を揺るがす。ディスクールの理論の「語られなかったことは何か?そしてなぜ語られなかったのか?」は衝撃的な理論だ。学校の歴史では「語られたこととそれを語った人」を学習する。社会を作ったのは、教科書で「語っていないけど行動した人」は無視されている。それを掘り起こすのが本当の歴史ではないかと私は常々思っていたので、フーコーに同種感を持った(おこがましいが)。後半で語られるキリスト修道会の生権力への絶対服従と性癖の告解は気持ち悪い2025/08/20
Tom
4
今は亡き洋泉社から2004年刊。昨今、管理社会ぶりが国民の骨身にまで沁み込み、もはや国家が何もしなくても国民の側から進んで管理されたがる美しい国ニッポンを見るにつけ、フーコーが言ってたことは正しかったんだなと実感する。フーコーの著作は読んだことがないので、予習として手に取った。第一章はフーコーの生涯。同性愛者だとは知らなかった。フーコーはフランス学術界でかなりの批判を受けた。現在のネームバリューの偉大さから、またフランス学術界に自由な気風を勝手に想像して、トントン拍子に駆け上がったものと思っていた。→2024/03/14
うえ
4
「ある朝、突然のように人々は狂者、無心論者、神を冒涜する者、夫とセックスすることを拒む女性など「理性的でない」も感じられる人々を、それまでハンセン病患者を閉じ込めていた施設に収容した…フーコーはこう推理しています。「ごく隠密に、おそらく長い時間をかけて、ヨーロッパ文化に共通の社会的な感性が形成されたに違いない。そしてこの感性が17世紀の後半に、突如として表面に浮かび上がってきたのだ」」実際には隠密にではなく、また突如としてでもなくて、というのな『weird』のテーマであろう。欧州(文化)そのものの特異性。2024/01/04
aof
4
やっぱりフーコーおもしろい。めちゃ好き。これは原書をあたるしかない。 特にフーコーが生涯を通じて問い続けたという「主体はどのように構築されるのか」という問い。ストア派の考え方と、キリスト教の考え方を対比させて考えるのめちゃ興味深い。 「対話」が自己への配慮を促すものなのかと、自己を他者へ委ねていくものなのかの違いとか。対話のワークショップデザインの根幹になりそうと思った。 やっぱり後期フーコー、しっかり読みたいなぁ。でも、難しいんだよなー。2020/05/15