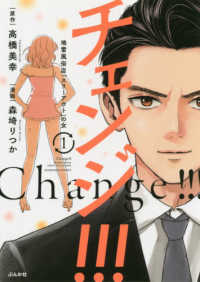内容説明
1989年日本語を自由に操る一人のアメリカ人学徒が山谷に入った。ドヤに住み、一緒に働きながら信頼を得、語られることの少なかった寄せ場に生きる人々の心の襞に分け入り、二年半の歳月をかけ貴重な証言を得ることに成功した。『ニューヨーク・タイムズ』で絶賛された労作、遂に刊行。
目次
第1章 舞台(山谷巡り;山谷の名所 ほか)
第2章 生活(日雇い労働者;組合員とシンパ ほか)
第3章 活動(労働組合の研究会;組合の企画会議 ほか)
第4章 儀式(秋祭りと冬祭り;忘年会 ほか)
第5章 仕事
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぺこ
5
大学の授業で
あきら
3
アメリカ人の学者が山谷に惹かれて、外から写真を撮り観察していた外からの視点と、実際にそこで日雇い労働者として働きドヤ街で過ごした内からの視点から描かれた山谷の風景。他の著書での紹介から本書に行き着いたが、これは文化人類学とかそういうの無しで是非とも読んでほしい。あの建物は誰が建てたのか、この道路は誰が作ったのか、こうした一つ一つの物には作り手がある。目の前の向こう側にあるいくつものストーリーを感じ、そして作者が山谷に感じるものを本書からも感じた。そして私は実際に山谷に足を運んだのであった…2022/04/27
つちのこ
1
図書館本。これまで山谷について書かれた本がたくさん出ているが、ほとんどが外の世界から山谷を覗いたものばかりである。これは著者自らが山谷に入って、そこに暮らす人たちの証言を収集し、外国人の目に写る山谷をストレートに表現した会心のレポートだ。(2000.1記)2000/01/20
あああ
0
山谷に生きる人々について深く学べました2013/11/30
chuchu*
0
東京・山谷に生きる人々の姿が、著者自らの経験を通して生き生きと描かれている。数字では表せないことを描くのが文化人類学だが、まさしくそれを体現しているのがこの本だ。この本は1990年前後の山谷を生きた人々の生きた証である。時間も空間も違えど、私と同じように悩み笑い生きた人々がそこには確かに存在した。そしてこれは決して過去の、一地域の話ではない。歴史は確実に繋がっており、今の日本を生きる一人として知らなくてはいけないことであると強く感じた。2011/11/30