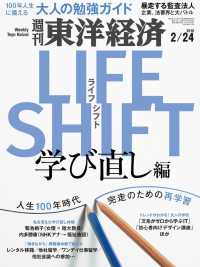内容説明
日米和親条約の締結・調印の地として、嘉永七年、横浜は日本史の表舞台に登場する。安政六年の開港後、横浜は貿易港として急成長を遂げるが、攘夷運動の激化に伴い、英仏両軍の駐屯を許す。横浜の鎖港問題は幕末の政局を左右し、江戸城総攻撃の中止にはイギリス公使の力が与かったとされている。文明開化の窓口となった横浜を経由して、東京の近代化のスピードは加速する。築地居留地、銀座煉瓦街などの東京の街づくりでは横浜がそのモデルとなっていた。東京築港論争などで、東京と横浜が刺激し合いながら発展していく道程を追い、両都市の関係史、比較史の視点から幕末明治の時代を読み解いていく。
目次
プロローグ―江戸・東京と横浜
1 開港前夜の横浜―江戸湾防衛の強化
2 横浜開港と外国人居留地の設定―江戸経済の強化を狙った幕府
3 横浜と攘夷運動―江戸幕府の対外政策
4 戊辰戦争と横浜―神奈川県と東京府の設置
5 明治維新と横浜―東京の文明開化
6 横浜港の危機―東京との築港競争
エピローグ 横浜居留地の終焉
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
64
有隣堂という横浜に根ざした書店の出版物なので、全国的知名度は低いと思われるが、幕末維新史を語るには重要な本だ。横浜と東京の都市発展についてコンパクトにまとめてある。特に横浜開港のいきさつに関して、教科書的な欧米が神奈川開港を求めたのに対し、幕府が横浜にしたといった単純な話ではなかったことが詳述されている。すでに横浜で商売を始めていた欧米商人が、神奈川開港案に猛反対したとか!これに関連して「井土ヶ谷事件」(通勤路に碑があり毎日隣を通る)が紹介されていたり、さすが地方出版物と思われる現地密着が楽しかった。2025/04/20
転天堂
2
横浜に出かけるので、観光気分を盛り上げるために読んだ。神奈川開港のはずなのに横浜村を開港した幕府と列強諸国とのせめぎ合い、東京築港論への反対運動。様々な経緯が絡み合って、現在の横浜が形成されている。今は簡単に移動できる東京-横浜間も、幕末・明治の人々に思いをはせながら移動するのもまた一興である。2024/09/27
おかリン
1
神奈川県立歴史博物館で購入。安藤優一郎氏はいつも読みやすい。第二章が特によかった。岩瀬•井上×ハリスの對話書は同所にも展示されている。🌟🌟🌟2024/09/16



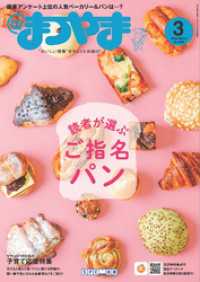
![太陽の戦士レオーナ SEASONⅡ 魔病院の罠[後編]](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)