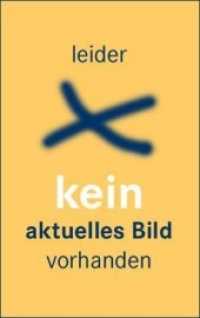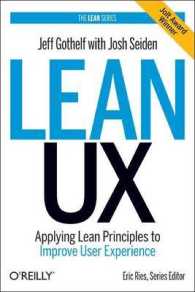内容説明
ソ連時代からの70年間に、アラビア文字→ラテン文字→キリル文字→ラテン文字と三度の変更。しかし、独立後20年の今日も、キリル文字とラテン文字が並存。知られざる中央アジアの大国の近現代史を、ウズベク語文字改革の変転からたどる。
目次
1 ウズベク語表記をめぐる現状(キリル文字とラテン文字の危うい並存;ウズベク語の出版状況)
2 ソ連邦期の言語政策と文字改革(アラビア文字の改良;ラテン文字化の模索;共通ラテン文字構想とその挫折;キリル文字化;キリル文字の抱える問題点)
3 ウズベク語表記の行方(ラテン文字化前夜;独立後のラテン文字化;表象としてのラテン文字;ラテン文字化政策の今後)
著者等紹介
淺村卓生[アサムラタカオ]
1975年、鳥取県生まれ。東北大学大学院国際文化研究科博士後期課程修了。博士(国際文化)。日本学術振興会特別研究員、山形大学非常勤講師等を経て、外務省入省。現在、在外公館勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
12
どの文字や言語を用いるか、ということはその国が如何なるものかを示す重要な要素である。ウズベキスタンは70年間にアラビア文字→ラテン文字→キリル文字→ラテン文字、と文字の変更を行ってきた。本書はその背景を簡潔かつ明解に示している。少しだけウズベク語を勉強していた時に感じたけど、アポストロフィの逆向きの表記記号、確かにPCで打ちにくい。IT化に備えてのはずなのに……。文字とアイデンティティの問題として、ウクライナの反ロシア派がキリル文字の廃止を訴えていることなど、考えさせられることが多かった。2019/12/11
さっきー
1
アラビア→ラテン→キリル→アラビア→ラテン、キリルと国語を時代の変遷とともに変容していったウズベキスタンの言語政策について。ラテン、キリル両表記は単に旧ソヴィエトやCISという表面的な理由だけではなく、民族主義や政治的要素が複雑に絡み合った故のものである。2018/06/10
samandabadra
1
新しいウズベキスタンの言語・文字政策の動向を検討したもの。1920年代からの言語政策に関する紹介もある。勉強になった。2018/03/30