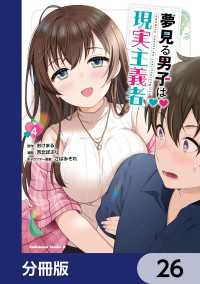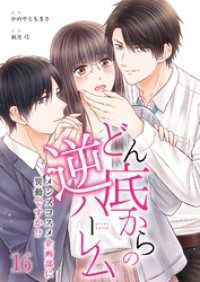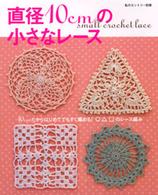目次
第1章 慶応義塾・日吉の戦争遺跡を歩こう(慶応義塾日吉キャンパスと戦争;キャンパスの戦争遺跡を歩く)
第2章 連合艦隊司令部の地下壕を歩いてみよう(延長1200メートルの極秘大地下壕;軍令部第三部・航空本部・東京通信隊地下壕;海軍省人事局地下壕)
第3章 戦争末期の帝国海軍(「絶対国防圏」とその崩壊;なぜ連合艦隊指令部は陸にあがったのか;なぜ連合艦隊司令部は日吉にやってきたのか;連合艦隊司令部)
第4章 戦争遺跡のあるまち日吉(日吉の歴史;日吉台国民学校と海軍省功績調査部 ほか)
第5章 近代戦争の拠点・神奈川(防衛の拠点・神奈川;侵略戦争の拠点・神奈川;本土決戦の拠点・神奈川)
著者等紹介
白井厚[シライアツシ]
慶應義塾大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。