目次
第1章 はじめに
第2章 手話が言語だということは何を意味するか―手話言語学の立場から
第3章 手話言語条例と手話言語法―法学・人権保障論の立場から
第4章 日本手話言語条例を実現させて
第5章 ろう教育における手話のあるべき姿
第6章 手話言語条例が制定された県の取り組み
第7章 手話の言語法の意義―ろう児の親の立場から
第8章 手話を言語として学ぶ・通訳する
著者等紹介
森壮也[モリソウヤ]
JETROアジア経済研究所開発研究センター主任調査研究員、元日本手話学会会長
佐々木倫子[ササキミチコ]
桜美林大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kaizen@名古屋de朝活読書会
39
#感想歌 #短歌 #手話 #言語 教育機会必須だし行政手続き補強必要 手話言語条例制定喜ばし法律文案拝読国際化課題 2017/03/11
ドシル
11
SNSをきっかけに生まれたブッククレット。 全国の自治体で手話に関連する条例が制定され、手話言語法策定を見据えた動きがある中で、「手話が言語ならば、、」と、様々な立場や視点で語られている。 批判あり体験談あり、大変興味深い作品。2016/12/09
みっふぃー
8
住んでる市が手話言語条例について動いているので読んでみた。法律決めたからと言って済むことじゃ無い。手話といっても日本手話じゃ無いと意味がない。という感じかな。手話初級のわたしには難しすぎました。2021/01/20
木ハムしっぽ
7
手話は言語である。そうだろうと思う。でもそう思う私は、ろう学校で主に使われている日本語対応手話と、先天的に聴覚障がいを持つろう者が自然に獲得していく日本手話との区別も分かっていなかった。産まれながらに耳が聞こえない人にとって日本語を習得することは、外国語話者が日本語を習得する以上に困難なことだろう。私が今年の読んだ本の中で最も衝撃を受けた読書体験となりました。 身近に聴覚障がい者がいる聴者は必読書だと思う。2023/06/07
三色かじ香
7
手話言語条例の背景が分かりました。日本手話が第一言語なので、それで授業を受けられるようにして欲しい、という主張は納得ですが、1書き言葉はどうするのか、2ろう者が聴者と話したいときはどうするのか という私の疑問は、この本では解決出来なかったです。2019/01/29
-

- 洋書電子書籍
- Bathild of Francia …
-
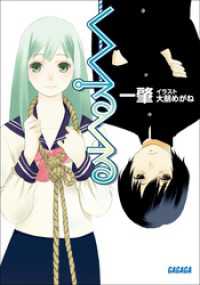
- 電子書籍
- くくるくる(イラスト簡略版) ガガガ文庫






