目次
進化言語学の構築を目指して
言語学編(進化言語学の方法論―反証主義と“妥当性”;パリ言語学会が禁じた言語起源;統語演算能力と言語能力の進化;ブローカ野における階層構造と回帰的計算;行動、認知、社会性に動機づけられた言語)
生物学編(進化言語学の生物学的構築;言語の進化=生き方の進化という観点から;言語障害と分子遺伝学から考える言語進化)
シミュレーション・モデリング編(相互音声模倣による乳幼児の母音獲得の構成的モデル;われらの脳の言語認識システムが生み出す音楽;言語進化の動的理解―生物言語学と構成論的モデルによるアプローチ;繰り返し学習モデルによる文法化の構成論的研究―創造性と言語の起源における言語的類推の役割)
著者等紹介
藤田耕司[フジタコウジ]
1958年生まれ。1982年大阪外国語大学大学院英語学専攻修士課程修了。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授
岡ノ谷一夫[オカノヤカズオ]
1959年生まれ。1989年メリーランド大学大学院心理学研究科Ph.D.課程修了。Ph.D.(生物心理学)。現在、東京大学大学院総合文化研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
books
0
merge only。大中小の容器の実験をヒト言語の階層と絡めて議論しているのが面白かった。
鈴
0
言語がどういうものであるかを知るには、生物としての人間が言語を持つ意味を知らなければいけない、人類進化の歴史も、脳機能も、他の動物の言語的能力についても知る必要がある、と考えていたら行き当たったのがこの本。欲しい情報ほとんど入ってた。2013/12/05
酔花
0
前半の言語学編も楽しめたが、言語そのものよりも、人間の系の中における言語システムに関心があるため、後半の生物編、シミュレーション・モデル編がよりおもしろかった。最後の座談会も、単なるおまけ的立ち位置ではなく本書の締めにふさわしい内容。言葉に対する認識の違いや研究のスタンスなど興味深く読んだ。2012/09/19
-
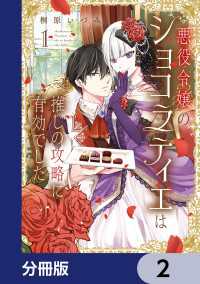
- 電子書籍
- 悪役令嬢のショコラティエは推しの攻略に…







