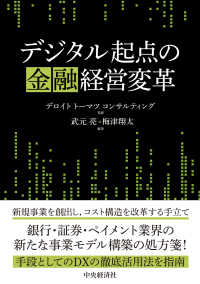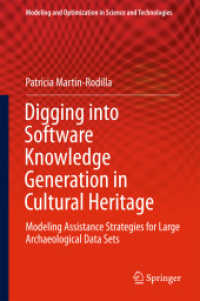目次
1 文法形態の発達
2 接続詞の更新
3 いかにして単語は意味を変えるか
4 動詞avoirの発達
5 Etreとavoir―Il est vacheおよびJ’ai tres faimの文型について
著者等紹介
松本明子[マツモトメイコ]
1948年、北海道生まれ。青森大学、いわき明星大学教授を経て、岡山大学大学院社会文化科学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shiba
2
メイエによる、文法化理論の草分け的ないくつかの論文の和訳/1, 2章、「これほんとに訳合ってる?」と言いたくなるような部分が多く、あまり入ってこなくてしんどい(知らない印欧語の例が怒涛のように提示されるのも大きいと思う、本来なら知らんなら知らんでちゃんと調べて読むべきかな〜)/3章が特に面白い:しばしば専門用語は集団語から言語全体に流入した際にその特殊な・限定的な意味を失うが、そもそも共通語による集団語の語彙の借入と定着はそういうプロセスで"しか起きない"という主張/疑問も多かったし再読したいところです2024/05/11
毒モナカジャンボ
0
複数言語間や同一言語下における異なる社会的集団間の接触によって、それまで使われていた単語の意味が抽象化・捨象されて別の意味を持ったり、場合によってはほとんど文法的な機能に変わってしまったりする。形態論はこの様相変化を捉えるための格好の研究方式である。未来形がなかったり、従位接続詞がほとんどなかったり、接続詞を別言語から借用してきたり。話し言葉で効果を高めるために現れた新しい単語の使い方や文法が書き言葉の文法に包摂されたと思ったら話し言葉で使われなくなっていたり。文法や単語の歴史的変遷を追うのたいへんだ。2020/05/22