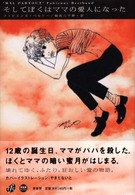出版社内容情報
ハーバード大学ビジネススクール教授・研究部門チームによる初学者・実務家向けクレジット・デリバティブの必携ハンドブック!
クレジットデリバティブのプライシング理論の議論に重点を置くと同時に、クレジットデリバティブの仕組みや種類の解説にも焦点をあてた、従来の類書にはない理論と実践をバランスよく備えた1冊です。図表データを豊富に用いることで理解力を深めているので、これからクレジットデリバティブを学習しようとする人にも格好の入門書です。
信用リスクに関する概観と基本的な信用リスク商品の紹介を中心とする第1部、信用リスク評価モデルの数理的な側面を詳しく解説する第2部、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)および債務担保証券(CDO)の組成やプライシングの考え方を分かりやすく解説している第3部の三部構成で成り立っています。
【目次】
第1部 信用リスクとは何か?
第1章 イントロダクション
1.1 信用リスクとという名の病気
1.2 信用リスクの治療薬:クレジットデリバティブ
1.3 信用リスク病にかかる者
1.4 本書の読み方
第2章 信用リスクとは
2.1 信用リスクの構成要素
2.1.1 信用とは何か
2.1.2 利息の重要性
2.1.3 信用の典型的タイプ
2.1.4 誰がデフォルトするのか
2.1.5 デフォルト発生原因:信用イベント
2.1.6 債務不履行のプロセス
2.2 信用リスクの定義
2.3 信用スプレッドによる信用リスクの数値化
2.3.1 デフォルト確率
2.3.2 リカバリー率
2.3.3 信用スプレッド:信用リスクに対する価値
2.4 デフォルト確率の評価:信用格付機関
2.5 信用リスクの統計
2.5.1 デフォルト率
2.5.2 リカバリー率
2.6 クレジットデリバティブ
2.6.1 トータル・リターン・スワップ
2.6.2 クレジット・デフォルト・スワップ
2.6.3 クレジット・リンク・ノート
2.6.4 クレジット・スプレッド・オプション
2.6.5 ポートフォリオおよび担保保証信用商品
2.7 クレジットデリバティブ市場
2.7.1 地域別市場
2.7.2 市場参加者
2.7.3 商品種別
2.7.4 裏付け参照資産
第2部 信用リスクのモデル化
第3章 信用リスクのモデル化:構造型アプローチ
3.1 信用リスクモデルの構造
3.1.1 信用リスクモデルの構造
3.1.2 Classes of Risk Models: Structural, Empirical and Reduced Form
3.2 構造型信用リスクモデル 6
3.2.1 バランスシート:構造型モデルの構成要素
3.2.2 構造型モデルの限界とタイプ
3.2.3 オプションプライシングと構造型モデルの関係
3.3 オプションの復習
3.3.1 コールとプットオプションの簡易な例
3.3.2 オプション保有時のペイオフ
3.3.3 オプション販売のペイオフ
3.4 Mertonモデル
3.4.1 Mertonモデルの勘所:資産価値のペイオフとしての負債と資本
3.4.2 ブラック・ショールズ経済でのMertonモデルの適用
3.4.3 Mertonモデルの応用例
3.4.4 Mertonモデルの応用:その他の例
3.4.5 リスク中立確率を使用したデフォルト確率の計算
3.4.6 Mertonモデルの感応度分析
3.5 Mertonモデルの拡張
3.5.1 ブラック-コックス拡張モデル:バリア関数
3.5.2 ブラック-コックス拡張版の応用
3.5.3 ブラック-コックス拡張版の適用例
3.5.4 ブラック-コックス とMertonモデルの比較
3.5.5 さらなるマートンモデルの拡張版:ロングスタッフ-シュワルツ
付録 ロングスタッフ-シュワルツモデル
ロングスタッフ-シュワルツモデルの定義
ロングスタッフ-シュワルツの適用例
ロングスタッフ-シュワルツモデルの感応度分析
第4章 信用リスクのモデル化:その他の価格付け手法
4.1 デフォルトの経験的モデルおよび信用スコアリングモデル
4.1.1 Z-Score Model
4.1.2 改定版Zスコア:Z‘スコア
4.1.3 Zスコアのさらなる改訂版:Z''スコア
4.2 誘導型モデル
4.2.1 デフォルト強度
付録 ジャロー-ターンブルモデル
デフォルト強度の求め方
ジャロー-ターンブルモデルを用いた例
ジャロー-ターンブルモデルの感応度分析
第3部 典型的なクレジット・デリバティブ
第5章 クレジット・デフォルト・スワップ
5.1 スワップ
5.2 CDSの定義
5.2.1 標準的なCDS
5.2.2 デジタルCDS
5.2.3 バスケット CDS
5.2.4 ポートフォリオCDS
5.2.5 CDSインデックス: iTraxx
5.3 CDSのプライシング
5.3.1 構造型モデルを用いたシングルネームCDSのプライシング
5.3.2 誘導型モデルを用いたシングルネームCDSのプライシング
5.3.3 マルチネームCDSプライシングの基本概念
5.3.4 マルチネームCDSのプライシング: バスケットCDS
5.3.5 マルチネームCDSのプライシング: ポートフォリオCDS
5.4 CDSの市場
第6章 債務担保証券
6.1 CDOの仕組み
6.1.1 伝統的なCDO
6.1.2 CDOを利用する動機:バランスシートと裁定取引
6.1.3 シンセティックCDO
6.1.4 その他のCDOタイプ
6.2 DO信用補完
6.2.1 2つの信用構造:キャッシュフロー型と市場価値型CDO
6.2.2 キャッシュフロー型CDOの信用補完
6.2.3 市場価値型CDOの信用補完
6.2.4 Pricing a CDO CDOプライシング
6.3 The CDO Market CDO市場動向
付録 CDOプライシング
CDOプライシング:理論
CDOのプライシング:例題
他のCDOプライシング手法:コピュラ関数
目次
第1部 信用リスクとは何か?(イントロダクション;信用リスクとは)
第2部 信用リスクモデル(信用リスクのモデル化(1):構造型アプローチ
信用リスクのモデル化(2):その他の価格付け手法)
第3部 典型的なクレジットデリバティブ(クレジットデフォルトスワップ;債務担保証券)
著者等紹介
中川秀敏[ナカガワヒデトシ]
東京大学大学院数理科学研究科博士課程修了。博士(数理科学)。2000年株式会社エムティービーインベストメントテクノロジー研究所(現・三菱UFJトラスト投資工学研究所)入社。2003年東京工業大学理財工学研究センター(後に、大学院イノベーションマネジメント研究科に異動)助教授着任。2008年一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授着任
本橋英人[モトハシヒデト]
慶應義塾大学理工学部工学科卒業。サンダーバード国際経営大学院国際経営学修士。マサチューセッツ工科大学ASP修了。Financial Risk Manager(FRM)。1992年NTT入社(交換機ソフトウェア開発)。1997年NTTコムウェア(金融リスク管理システムの構築およびコンサルティング)。2008年NTTドコモ国際事業部(海外企業への出資、M&A)
長谷川嘉成[ハセガワヨシシゲ]
京都大学大学院電気工学科卒業。カーネギーメロン大学ソフトウェア工学修士。1994年NTT入社(伝送システム開発)。2002年みずほ銀行出向(業務革新委員会)。2004年NTTコムウェア金融システム事業本部
柴田裕俊[シバタヒロトシ]
早稲田大学大学院理工学研究科修了。理学修士。2002年NTTコムウェア入社。2004年9月まで東工大理財工学研究科(現イノベーションマネジメント研究科)と共同研究。以降、銀行・証券会社のシステム開発に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。