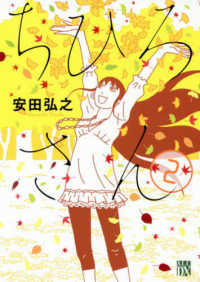出版社内容情報
『出版ニュース』2011.6上旬号より
アジア・アフリカの様々な地域において,「歴史」はどのように描かれてきたか。本書は,アジア・アフリカ各地の固有の言語で書き残された文書や,観察記録,口頭伝承や聞き取り調査で得られた体験者の記憶など,多様な史料を駆使して「歴史」の生成過程を複眼的に分析した論考集。・・・中略・・・世界史の生きた現場を捉え,世界史像を豊かにする試み。
『週刊読書人』2011.7.15 より
近年,ドストエフスキーの新訳から東日本大震災の救援情報の多言語化まで,東京外語大が気を吐いている。そこには,AA研(アジア・アフリカ言語文化研究所)というユニークな研究所があり,さまざまな共同研究の先頭に立ってきた。その成果のひとつである本書は,均質的な集団や社会の内部でなく,帝国と少数民族の接点,近代植民地主義の影響下の地域社会,移住民の社会など,力関係を異にする複数の文化や集団が接触する場で,「歴史」がどのようにとらえられ描かれてきたのかを,非文字史料を含むさまざまな「記録と記憶」に分け入ることで明らかにしようとしたもので,7人の著者がそれぞれ1章ずつを担当している。(中略) 本書で扱う研究方法は,学界ではかなり普及しつつあり,専門研究として現時点で圧倒的な斬新さをもつものとは言えないだろう。しかし,一般書に近い形態での出版物として,本書が扱う事例の面白さと読みやすい叙述は,大きなメリットである。ベトナム史を専攻する評者のような,「専門違いの研究者」にとっても,こういう本はとても有り難い。 (以下略)(評者:桃木至朗)
目次
1 選択される過去―北部エチオピアのキリスト教徒の歴史認識
2 八〇〇年後の「復讐」―西南アジアにおける「ソームナートの門扉」の歴史
3 清朝とコンバウン朝の狭間にある雲南のタイ人政権―一七九二年~一八一五年までの国内紛争
4 植民地期の南インド史記述とその現地的起源―「ポリガール」をめぐる諸言説を中心に
5 マンドゥメの頭はどこにあるのか―ナミビア北部・クワニャマ王国の歴史と現在
6 東南アジアにイスラームをもたらしたのは誰か?―ワリ・ソンゴの起源をめぐる問題とアラブ系住民
7 英系ビルマ人の歴史と記憶―日本占領期(一九四二~四五年)とビルマ独立をめぐって
著者等紹介
永原陽子[ナガハラヨウコ]
1955年生まれ、東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退、現在、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授、専門は南部アフリカ史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。