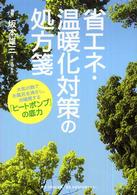内容説明
主に一九世紀から一九一七年のロシア革命までのロシアにおける年中行事的祝祭について、農村や町における正教の祭りや民間の伝統的儀礼、祝祭を中心に紹介。第二部においてはこれらの祝祭が革命以後の時期にいかにソヴェトの祝祭の中に取り入れられ、どのような変化をこうむったのかについて分析。まったく新しいソヴェトの祝祭についても検討を加え、ロシア人の社会生活において祝祭文化がいなかる役割を果たし、いかなる社会的意義を持っていたのかを考察する。
目次
第1部 ロシア時代の祭り(スヴャートキ(聖週間)
マースレニツァ(バター週)
復活祭(パスハ)週
セミーク、トローイツァ(三位一体祭)
春送り祭、「イワン・クパロ」
夏から秋の収穫の祭り
冬の到来を画する祝祭)
第2部 ソヴェト時代の祭り(革命直後の動き;新しい祝日の市民生活ヘの定着;ソヴェトの新年祭;労働、職業、地域の祭り;「ロシアの冬祭り」、「白樺祭」;復活祭の変遷;コルホーズ収穫祭;民族の文化への関心、ソ連崩壊後の祝祭日)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
組織液
9
土着の信仰から始まった祭りが聖教→社会主義→ ロシアのアイデンティティと装いを変えていくのが面白かったです。ドイツ史とか吸血鬼関連の本でも似たような例をみた気がしますね。『ロシア異界幻想』再読したくなりました。2022/06/24
晴天
0
ロシアのおける祝祭は、自然や農耕に根差した土着宗教の色彩を包摂しつつロシア正教の祝祭に装いを変え、革命後は非宗教化とイデオロギー化とが進展するが祝祭の日付はそれほどは変わらず、ふるまいは特に農村ではほとんど変わらなかった。そしてソ連崩壊後はイデオロギー色は排除され、伝統を前面に押し出し、国民統合の旗印に装いを変えつつある。このように時代によって装いは大きく変わっているが、人々の営みや内心における位置づけには根強い連続性がある。祝祭の連続性と非連続性とは、ときの指導部がコントロールしようとしても難しい。2021/10/20
-
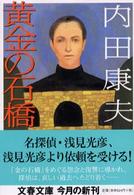
- 和書
- 黄金の石橋 文春文庫