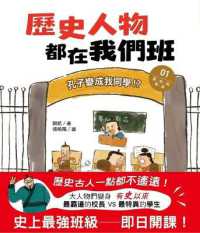内容説明
「歌唱台湾」=「台湾を歌う」。本書は台湾語流行歌から台湾を描き出そうするものである。台湾語流行歌の日本化、演歌化は戦後、国民党政府支配になってからである。台湾人が日本的な要素を自らの歌唱文化に取り込んだのは、いかなる要因に由来するのだろうか。台湾社会が工業化へ向かう中、何が起こったのか。農村人口が大量に移動し始める戦後の社会的な変遷の中で、台湾語流行歌はいかなる需要を基盤に、どのようにして日本演歌と共に自分が歌う「伝統」を作り出したのか。
目次
序章 台湾語流行歌―台湾人のある社会文化史
第1章 台湾語流行歌の生成と発展―新民謡運動・閨怨女・太平洋戦争
第2章 半封建的な農業社会で暮らす台湾人―「平穏」な籠の中で歌う
第3章 再植民地統治と台湾語流行歌―「閨怨」から「苦恋」への戦後初期
第4章 「港歌」に見る再植民地統治下の台湾語流行歌―海/港から日本へ
第5章 台湾語流行歌の全盛期と日本―工業化社会の望郷演歌と股旅演歌
第6章 自力救済か、他力本願か―一九七〇年代のテレビ布袋戯と社会問題
第7章 結論に代えて―再植民地統治下の国語・台湾語流行歌
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
糸文
5
日本統治時代は第一植民時代だとしたら、国民党が台湾を"占領"してから1987年戒厳解除までの期間は再植民時代となる、そして今は後再植民時代。この三つの期間に起きた事件と時代背景で今の台湾語流行歌に至る。台湾語と言えば、1945年前既にこの地に住んでた台湾人が喋る言葉。台湾人と言えば、ずっと長い間二等国民扱いされてきて、学問の無い貧しい出身が多かった。そのため、台湾語流行歌も現実に抱く不満や理不尽の歌詞が大半だった。歌い方が演歌っぽい訳は性に合うだけでなく、国民党に反抗する意思も含まれてた。色々勉強になった2023/10/11
-
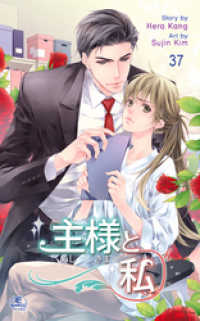
- 電子書籍
- 主様と私37 NETCOMICS
-
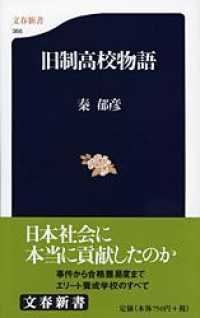
- 和書
- 旧制高校物語 文春新書