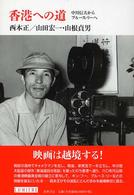出版社内容情報
(1998年『キラルテクノロジーの工業化』普及版)
【刊行にあたって】
近年,医農薬や機能材料分野において光学活性有機化合物(エナンチオマー)の需要が高まり,光学活性体を製造・供給しようとする工業技術”キラルテクノロジー”が注目されている。本書は,国際的にも高いレベルにある我が国のキラルテクノロジーの現状を概観し,今後の発展に資するよう企画されたものである。筆者が”キラルテクノロジー”あるいは”chirotechnology"という言葉に出会ったのは1992年のC&EN誌(10月26日号)に掲載された「"chirotechnology"revolution」と題するP.Rotheim氏(Business Commun.Co.)の投書であったと思う。同氏はここでキラルテクノロジー革命はバイオテクノロジー革命よりも規模が大きい。1989年度の米国キラルテクノロジーの売上高は$494 million であったが,今後その成長率は年17.5%で,2000年には$2.8 billion に達する,などを予測している。その頃,筆者も”不斉合成”という科学用語に対応する魅力的な工業技術用語を造ることを考えていて,個人的には,”キラル分子工学”を提唱していた。近年,キラルテクノロジーは高付加価値を指向する精密化学工業界のキーワードの一つとなり,とりわけ医薬業界における chiral drugs,racemic switches の流れが速くなり,今日の活気がもたらされるものと思う。
このキラルテクノロジーの進展は,益々不斉合成へ指向する今日のacademicな有機合成化学の進展とも同調して,”新科学”が即”新技術”になる可能性を秘め,まさに企業と大学が共同して進行している状況にあり,世界中でベンチャー型企業を生む基板を提供している。事実,最近世界中でキラルテクノロジーを主題とする産学合同のmeetingが定期的に開催されている(chiral USAなど)。このキラルテクノロジーの最新の進歩を5回(最新版は1997年10月20日号)も特集していたり,「Chirotechnology」,「Chirality in Industry」と題する単行本なども続々出版されたりと,工業界におけるキラルテクノロジーへの関心の大きさがうかがえる。
この分野における我が国の学界・工業界の実力は,その実績から見て,国際的にもかなりのものであることは自他ともに認めるところであろう。こうした状況の中で本書が出版されることはまさに時を得ており,本書が我が国のキラルテクノロジーの一層の発展の一助となり,現在,やや元気のない化学工業界の活性化につながればと願う。
【執筆者一覧(執筆順)】
中井 武 東京工業大学 工学部化学工学科 教授
(現) 新潟大学 大学院自然科学研究科 エネルギー基礎科学専攻 教授
大橋 武久 鐘淵化学工業(株) 総合研究所 取締役所長
(現) 鐘淵化学工業(株) 研究開発本部 常務理事
長谷川淳三 鐘淵化学工業(株) 総合研究所 高砂研究所 主席研究員
(現) 鐘淵化学工業(株) ライフサイエンスRDセンター 主席幹部
古川 喜朗 ダイソー(株) 研究所 主席研究員
田村 鋼二 日東化学工業(株) 中央研究所 有機合成研究開発グループ
(現) 三菱レイヨン(株) 大竹事業所 化成品工場 生産技術課 課長代理
平田 祐司 日東化学工業(株) 大竹事業所 製造部技術課
(現) 三菱レイヨン(株) 横浜事業所 生産技術課 課長代理
古林 祥正 日東化学工業(株) 中央研究所 有機合成研究開発グループリーダー
(現) 三菱レイヨン(株) 中央技術研究所 触媒研究グループ グループリーダー/主席研究員
遠藤 隆一 日東化学工業(株) 中央研究所 微生物応用研究開発グループリーダー
(現) 三菱レイヨン(株) 横浜技術研究所 研究企画推進グループ 主席技師
広瀬 芳彦 天野製薬(株) 中央研究所 主任研究員
(現) 天野エンザイム(株) メディカル事業部 主任研究員
半澤 敏 東ソー(株) 東京研究所 主任研究員
後藤 誠 三菱化学(株) 筑波研究所 生物化学研究室 副主任研究員
(現) (株)エーピーアイコーポレーション 袋井工場 品質保証グループ グループマネージャー
湯川 英明 三菱化学(株) 筑波研究所 生物化学研究室 室長
柴谷 武爾 田辺製薬(株) 医薬開発研究所 部長研究員
(現) 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科客員教授
南井 正好 住友化学工業(株) 有機合成研究所 グループマネージャー
(現) 広栄化学工業(株) 研究所 研究主幹
佐藤 治代 東レ(株) ケミカル研究所 主席研究員
尾崎 明夫 協和発酵工業(株) 東京研究所 主任研究員
三浦 孝志 高砂香料工業(株) ファインケミカル研究所 第1部 部長
高橋 泰裕 日産化学工業(株) 化学品機能製品事業部 企画開発部 主査
鈴鴨 剛夫 住友化学工業(株) 研究主幹 研究室長
(現) GSC技研 所長
光田 賢 住友化学工業(株) 生命工学研究所 主席研究員
(現) 住友化学工業(株) 技術経営企画室 担当部長
村上 尚道 山川薬品工業(株) 取締役
牧野 成夫 ダイセル化学工業(株) キラルケミカルズ事業部 開発部 部長
新開 一朗 エーザイ(株) 開発研究 取締役
(現) (株)ベータ・ケム 代表取締役社長
(執筆者の所属は,注記以外は1998年当時のものです)
【構成および内容】
序 論 中井 武
総 論 キラルテクノロジー工業化の展望 大橋武久
1.キラルテクノロジーの概念
2.生体触媒を用いる技術
3.不斉合成技術
第I編 不斉合成-生化学的手法
第1章 バイオ技術と有機合成を組み合わせた医薬品中間体の合成 長谷川淳三
1.はじめに
2.光学活性β-ヒドロキシ脂肪酸とその利用
2.1 カプトプリル
2.2 β-ラクタム抗生物質
2.3 その他の利用
3.光学活性オキサゾリジノン類とβ-ブロッカー合成
4.光学活性1,2-ジオール類生産と利用
4.1 (R)-3-クロロ-1,2-プロパンジオール
4.2 光学活性1,2-ジオール類
5.おわりに
第2章 微生物を用いたキラルビルディングユニットの開発 古川喜朗
1.はじめに
2.光学活性C3化合物生産菌の探索
3.光学活性エピクロロヒドリン(EP)の反応性と応用例
4.光学活性3-クロロ-1,2-プロパンジオール(CPD)の反応性と応用例
5.4-クロロ-3-ヒドロキシブタン酸エステルの光学分割
6.おわりに
第3章 バイオ法による光学活性-α-ヒドロキシ酸製造技術の開発
田村鋼二,平田祐司,古林祥正,遠藤隆一
1.はじめに
2.シアンヒドリンの特性と光学活性マンデル酸製造への応用
3.立体特異的ニトリル加水分解酵素の探索
4.亜硫酸イオンの効果
5.ベンズアルデヒドと青酸からの(R)-マンデル酸の製造
6. シアンセンサーの利用による反応の無人化
7.置換マンデル酸,およびα-置換-α-ヒドロキシ酢酸の生産
8.培養菌体の保存法
9.光学活性スチレンオキサイドへの変換
10.キラルビルディングブロックとしての応用
11.おわりに
第4章 リパーゼを用いた光学活性化合物の製造 広瀬芳彦
1.はじめに
2.1,4-DHPのプロテアーゼによる不斉加水分解およびエステル交換反応
2.1 1,4-DHPの酵素のスクリーニング
2.2 プロテアーゼによる加水分解反応について
2.3 エステル交換反応について
3.1,4-DHP中間体の合成検討
3.1 加水分解酵素について
3.2 基質の大きさについて
3.3 反応溶媒について
3.4 酵素反応温度について
3.5 添加剤の効果について
3.6 酵素の固定化による反応性の向上
3.7 部位特異的変異による立体選択性の改変
4.おわりに
第5章 アスパルテーム生産における酵素の効率的利用 半澤 敏
1.はじめに
2.酵素法によるAPMの合成
3.サーモライシンの改良
3.1 サーモライシン
3.2 変異導入のストラテジーと変異の導入
3.3 変異体酵素の活性評価
4.縮合反応系の改良
4.1 基質濃度比の最適化
4.2 溶媒添加
5.おわりに
第6章 膜リアクターによるアミノ酸製造 後藤 誠,湯川英明
1.はじめに
2.膜リアクタープロセスの概要
3.L-アスパラギン酸製造プロセスへの応用
3.1 概要
3.2 アスパラギン酸生成酵素系
3.3 アスパラギン酸生成反応条件
3.4 限外濾過膜の選定
3.5 遺伝子組換えによる生産性の向上
4.L-イソロイシン,L-バリン製造プロセスへの応用
4.1 概要
4.2 L-イソロイシン,L-バリン生成経路
4.3 L-イソロイシン生産
4.4 L-バリン生産
5.おわりに
第7章 酵素法による光学分割と微生物による不斉還元反応 柴谷武爾
1.はじめに
2.リパーゼを用いる不斉加水分解反応
2.1 ジルチアゼム合成工程への不斉加水分解反応の利用
2.2 不斉加水分解酵素のスクリーニング
2.3 酵素反応の最適化
2.4 膜バイオリアクターの利用
2.5 酵素の高生産
3.パン酵母を用いる不斉還元反応
3.1 ジルチアゼム合成工程への不斉還元反応の利用
3.2 非晶質の基質
第8章 酵素反応を利用した強誘電性液晶化合物の合成 南井正好
1.はじめに
2.強誘電性液晶
2.1 強誘電性と表示原理
2.2 強誘電性液晶の分子設計
2.3 キラル側鎖部分の構築
3.強誘電性液晶の合成と物性
3.1 フェニルベンゾエート系強誘電性液晶
3.1.1 キラル炭素がコア直結型強誘電性液晶の合成
3.1.2 メチレン鎖導入型フェニルベンゾエート系強誘電性液晶の合成
3.1.3 その他のフェニルベンゾエート系強誘電性液晶の合成
3.1.4 コア部分の構造と液晶性および相系列
3.1.5 自発分極と絶対構造の関係
3.2 2環性ビフェニルおよびフェニルピリミジン系強誘電性液晶の構造と物性
3.2.1 ビフェニル系強誘電性液晶の合成
3.2.2 フェニルピリミジン系強誘電性液晶の合成
3.2.3 不飽和メチレン鎖導入型フェニルピリミジン系強誘電性液晶の合成
3.2.4 2環性ビフェニルおよびフェニルピリミジン系強誘電性液晶の構造と物性
4.おわりに
第9章 微生物を利用したD-アラニン,D-酒石酸の工業的製造法とその展開 佐藤治代
1.はじめに
2.D-アミノ酸の製造法
2.1 D-アラニンの一般的製造法
(1)発酵法
(2)酵素法
(3)化学分割法
2.2 選択資化法による新しい製造法
2.3 応用例
3.D-酒石酸の工業的製造法
3.1 一般的方法
(1)化学的分割法
(2)酵素法
3.2 選択資化法による製造法
4.光学活性酒石酸の用途
4.1 キラルビルディングブロックとしての利用
4.2 光学分割剤としての利用
(1)アミン類の分割
(2)アルコール類の分割
4.3 不斉触媒リガンド
4.4 光学純度分析試薬
第10章 酵素法によるヒドロキシプロリン製造法の開発 尾崎明夫
-位置および立体特異的プロリン水酸化酵素の開発と応用-
1.はじめに
2.HYP分析法の開発
3.プロリン水酸化酵素のスクリーニング
4.プロリン水酸化酵素の性質
5.遺伝子取得と大腸菌での活性発現
6.HYP生産プロセスの確立
6.1 2OG供給リサイクルシステムの確立
6.2 L-Pro分解経路の遮断
6.3 trans-4HYPの生産
7.おわりに
第II編 不斉合成-不斉触媒合成
第1章 BINAP-金属錯体を触媒に用いた不斉反応の利用 三浦孝志
1.はじめに
2.BINAP-金属錯体を用いた不斉合成
2.1 不斉異性化反応
2.2 オレフィン化合物の不斉水素化
2.3 ケトン類の不斉水素化反応
2.4 単純ケトンの不斉水素化反応
3.おわりに
第2章 不斉合成・光学分割技術によるプロスタグランジン類の開発 高橋泰裕
1.はじめに
2.日産化学のPG合成法
2.1 佐藤-日産法によるPG製造法
2.1.1 従来技術
2.1.2 2成分連結法
2.2 ω鎖合成技術
2.3 相模-日産法
3.PG類の工業化
4.おわりに
第III編 光学分割法
第1章 光学活性ピレスロイドの合成法の開発と工業化 鈴鴨剛夫,光田 賢
1.はじめに
2.酸成分
2.1 化学的光学分割
2.2 菊酸異性体の立体変換反応プロセス(エピ化とラセミ化)
(1)エピ化プロセス(C-1およびC-3エピ化)
(2)ラセミ化プロセス
2.3 酵素的光学分割
3.アルコール成分
3.1 光学活性アレスロロン
3.1.1 光学分割
3.1.2 酵素的光学分割
3.2 プロパルギルロン
3.2.1 光学分割
3.2.2 酵素的光学分割
4.おわりに
第2章 ジアステレオマー法による光学活性体の製造 村上尚道
1.山川薬品工業における開発の経過
2.マンデル酸の光学分割とその応用
2.1 光学分割
2.2 その他の製法
2.3 用途
3.α-フェネチルアミンの光学分割とその応用
3.1 光学分割
3.2 その他の製法
3.3 光学活性PEAの用途
4.その他の光学分割例
5.ジアステレオマー法光学分割の特徴と限界
6.光学分割剤の選択
第3章 液体クロマトグラフィーを用いた光学分割の工業的利用 牧野成夫
1.はじめに
2.単カラム法による光学活性体の生産
3.SMB法による光学活性体の生産
3.1 開発の背景
3.2 SMB法の原理
3.3 SMB法の特徴
3.4 開発の現状
3.5 運転条件の設定と評価
3.5.1 運転を左右する条件
3.5.2 運転条件設定に際して考慮すべき要因
3.5.3 光学活性体の目標品質設定
3.5.4 評価すべき項目
3.6 キラル分離例
3.6.1 初期運転条件検討
3.6.2 生産性向上についての検討
3.6.3 長期連続運転
3.6.4 SMB法と単カラム法生産性比較
4.おわりに
展 望
展 望 新開一朗
1.はじめに
2.プロテアーゼ阻害剤
2.1 アミノインダノールの合成
2.2 C-3の設置
2.3 ピペラジンの合成
2.4 合成法の確立
3.中間体製造企業の最近の動向
4.おわりに
内容説明
近年、医農薬や機能材料分野において光学活性有機化合物(エナンチオマー)の需要が高まり、光学活性体を製造・供給しようとする工業技術“キラルテクノロジー”が注目されている。本書は、国際的にも高いレベルにある我が国のキラルテクノロジーの現状を概観し、今後の発展に資するよう企画されたものである。
目次
キラルテクノロジー工業化の展望
第1編 不斉合成―生化学的手法(バイオ技術と有機合成を組み合わせた医薬品中間体の合成;微生物を用いたキラルビルディングユニットの開発 ほか)
第2編 不斉合成―不斉触媒合成(BINAP‐金属錯体を触媒に用いた不斉反応の利用;不斉合成・光学分割技術によるプロスタグランジン類の開発)
第3編 光学分割法(光学活性ピレスロイドの合成法の開発と工業化;ジアステレオマー法による光学活性体の製造 ほか)
展望
著者等紹介
中井武[ナカイタケシ]
東京工業大学工学部化学工学科教授。(現)新潟大学大学院自然科学研究科エネルギー基礎科学専攻教授
大橋武久[オオハシタケヒサ]
鐘淵化学工業(株)総合研究所取締役所長。(現)鐘淵化学工業(株)研究開発本部常務理事
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 空気の日記
-

- 電子書籍
- カワセミさんの釣りごはん 分冊版 19…