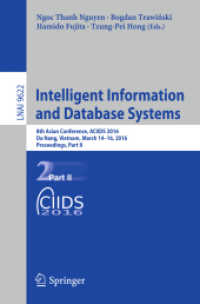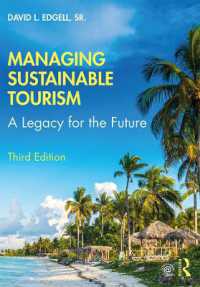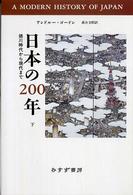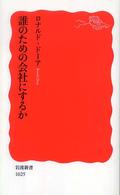出版社内容情報
【構成および内容】
第1章 序論
1.はじめに
2.塗料(塗装)産業の置かれた立場
3.開発の考え方
3.1 塗料の「高付加価値」と「客」のニーズ
3.2 複合材料としての塗料
3.3 薄膜とブレンドの技術
3.4 開発の効率化
4.現代科学と技術の問題点
4.1 技術革新の長期波動
4.2 科学・技術の歴史的展開(技術開発によって生じる負のインパクトの軽減・アセスメント方法論)
4.3 科学,科学者,技術,技術者,工学について(視点のなかの思想性の必要)
4.3.1 科学と技術
4.3.2 何のための科学,何のための技術(我々の進んだ科学・技術も偏見として見直す必要がある)
4.3.3 現代科学の方法論(機械論的自然観の崩壊)と現代技術(工学)の形成
4.3.4 現田尾科学技術批判
4.3.5 現代科学・技術と科学技術者の倫理
4.4 エネルギーと資源
第2章 材料開発の科学
1.序
2.塗料ビヒクルの構造
2.1 はじめに
2.2 ビヒクル成分としてのアルキド樹脂の分子量と分子量分布
2.2.1 実験
2.2.2 結果と考察
2.2.3 結論
2.3 ミクロゲルの生成
2.3.1 実験
2.3.2 結果と考察
2.3.3 結論
2.4 環状構造の役割
2.5 不均一構造の役割
2.5.1 漆膜の不均一構造
2.5.2 放射線重合ポリマーの二層構造
3.塗料用ビヒクル成分の溶解性
3.1 はじめに
3.2 アルキド樹脂およびメラミン樹脂の希釈価
3.2.1 アルキド樹脂およびメラミン樹脂の樹脂化反応過程の溶解性
3.2.2 メラミン樹脂の樹脂化反応過程の溶解性
3.3 アルキド樹脂を含む塗料用合成樹脂の相溶性
3.3.1 実験
3.3.2 結果と考察
3.3.3 結論
3.4 溶剤の役割と溶解性パラメータの関係
3.4.1 溶剤の役割と欠陥
3.4.2 溶解
3.4.3 溶解性パラメータ
3.5 貧溶媒論-溶液と溶媒効果について-
3.5.1 塗料溶液における貧溶媒の役割
3.5.2 塗料材料プレポリマー分子の配向
3.5.3 塗膜形成過程における溶剤効果
4.塗膜の形成過程とレオロジー
4.1 はじめに
4.1.1 塗液のレオロジー
4.1.2 塗膜のレオロジー
4.2 レオロジーの一般的な知識
4.2.1 変形と弾性および粘性
4.2.2 弾性
4.2.3 流動性
4.3 粘弾性
4.3.1 弾性と流動の共存する現象
4.3.2 粘弾性の数式的表現と緩和時間
4.3.3 動的粘弾性
4.4 塗液のレオロジー
4.4.1 塗液のレオロジーの一般的な法則
4.4.2 流動性・レオロジーの本質
4.4.3 作業性のレオロジー
4.5 塗液のレベリングと”たれ”
4.5.1 レベリングと”たれ”現象のレオロジー解析
4.5.2 実用塗料レベリングと”たれ”と
4.5.3 レベリングと”たれ”のズリ速度
4.5.4 最適な流動特性
4.6 塗膜の粘弾性
4.6.1 塗膜のレオロジーと粘弾性の関連
4.6.2 応力-ひずみ関係
4.6.3 塗膜の性能とレオロジー
4.7 おわりに
5.顔料の分散
5.1 はじめに
5.2 分散過程と貧溶媒の役割
5.3 塗料ポリマーの吸着と顔料の分散
5.4 隠蔽力に関する限界顔料容積濃度
5.4.1 実験
5.4.2 結果と考察
5.4.3 結論
5.5 各種塗料系の隠蔽力と光沢
5.5.1 実験
5.5.2 結果と考察
5.5.3 結論
5.6 塗料系の有機顔料の分散性
5.6.1 実験
5.6.2 結果と考察
5.6.3 結論
6.付着性
6.1 はじめに
6.2 付着の理論
6.2.1 濡れと付着仕事
6.2.2 分子間力と付着
6.2.3 機械的結合
6.2.4 凝集破壊と付着破壊
6.2.5 内部応力と付着強さ
6.2.6 相溶性と付着強さ
6.2.7 粘弾性と付着強さ
6.2.8 多層系塗膜の付着と層間剥離
6.3 表地表面の状態
6.3.1 金属の表面
6.3.2 素地の清浄化
6.4 リン酸塩化成処理
6.4.1 化成処理の概要
6.4.2 リン酸塩化成処理
6.5 表面処理剤による付着性の改善
6.5.1 表面処理法
6.5.2 シラン系カップリング剤
6.5.3 チタン系カップリング剤
第3章 材料の設計と処方化
1.汎用塗料の設計と処方化
1.1 ワニスとペイント
1.1.1 短油性ワニス
1.1.2 中油性ワニス
1.1.3 長油性ワニス
1.1.4 代表的な処方例
1.1.5 合成樹脂ワニス:アルキド,エポキシおよびポリウレタン樹脂ワニス
1.1.6 アルキド-油性ハウスペイント
1.2 ニトロセルロースラッカー
1.2.1 溶媒均衡
1.2.2 溶媒組成
1.2.3 蒸発速度
1.2.4 カブリ
1.2.5 可塑剤および樹脂
1.2.6 樹脂比率
1.2.7 樹脂の種類
1.2.8 NCラッカーの処方化
1.3 アクリルラッカー
1.4 塗料用アクリル樹脂の物性
1.4.1 アクリル樹脂の重合
1.4.2 アクリル樹脂の一般的特性
1.4.3 アクリル樹脂のガラス転移温度
1.4.4 アクリル樹脂の酸価とヒドロキシル化
1.5 ポリウレタン塗料
1.5.1 ポリウレタン塗料の現況
1.5.2 ポリウレタン塗料の種類と主な用途
1.5.3 ポリウレタン塗料の化学
1.6 超速乾型ウレタン樹脂塗料
1.7 反応性ポリエステル樹脂塗料
1.7.1 反応性ポリエステルをつくるための原料
1.7.2 反応性ポリエステルによる各種塗料
1.8 エポキシ樹脂塗料
1.8.1 溶剤型塗料
1.8.2 水系塗料
1.8.3 ハイソリッド塗料
1.8.4 粉体塗料
1.9 オルガノゾルとプラスチゾル
1.9.1 プラスチゾルの製法
1.9.2 オルガノゾルの処方化
1.9.3 塗装法
1.9.4 プライマーの処方化
2.低公害化塗料概論
2.1 ハイソリッド塗料の設計と制御
2.1.1 はじめに
2.1.2 分子量と粘度
2.1.3 Polymeric Melamine Curing
2.1.4 NAD系ハイソリッドの設計と制御
2.2 自動車用水溶性塗料の塗装法の開発
2.2.1 はじめに
2.2.2 アクリル系水性樹脂の動向
2.3 粉体塗料
2.3.1 はじめに
2.3.2 粉体塗装法の種類と原理
2.3.3 粉体塗装の前処理
2.4 粉体塗装設備
2.4.1 静電粉体塗装機の選定
2.4.2 粉体塗装ブース
2.4.3 粉体塗料回収装置
2.4.4 空気供給機
2.4.5 焼付炉と焼付温度管理
2.4.6 コンベア
2.4.7 塗装ライン
2.4.8 廃水処理
2.4.9 設備の保守と管理
2.5 粉体塗装の特性と種類
2.5.1 粉体塗料の特徴
2.5.2 省資源,低公害型塗料の中における粉体塗料のメリット
2.5.3 粉体塗料の種類
2.6 低公害化塗料のフローシート
3.有機・無機複合体塗料の処方化(有機・無機複合体とセラミックコーティング)
3.1 有機・無機複合体塗料
3.1.1 概要
3.1.2 複合体形成可能な無機材料
3.1.3 ケイ素化合物を使用した複合体塗料
3.1.4 有機・無機複合塗料(コスマー)
3.2 セラミック・コーティング
3.2.1 アルカリ金属ケイ酸塩をバインダーとした無機塗料の例
3.2.2 せらみっくを顔料とする有機塗料の例
3.2.3 耐熱性重防食セラミック・コーティングの例
3.3 新しいセラミック・コーティング剤
3.3.1 種類と物性
3.3.2 特徴
4.シリコン樹脂塗料の処方化
4.1 シリコン樹脂について
4.2 用途別解説
4.2.1 耐熱性コーティング
4.2.2 耐候性コーティング
4.2.3 弾性コーティング
4.2.4 表面保護用
4.2.5 その他
5.フッ素樹脂塗料の処方化
5.1 フッ素樹脂の種類・特徴・用途
5.2 低温硬化型フッ素樹脂
5.2.1 組成1
5.2.2 組成2
5.3 低温硬化型フッ素樹脂の塗料化
5.3.1 溶媒の選定
5.3.2 硬化剤の選定
5.3.3 塗料化
5.3.4 塗膜性能と用途
第4章 実用と信頼性
1.性能と試験法
1.1 概論
1.1.1 はじめに
1.1.2 塗料(塗膜)の試験規格
1.1.3 研究のための試験法
1.2 実用塗料に要求される性質
1.2.1 表面・界面の性状
1.3 付着性試験法
1.3.1 試験法の概要
1.3.2 ゴバン目試験(含む描画試験)
1.3.3 アドヘロメーター
1.3.4 剥離試験
1.3.5 引っ張り・剪断付着試験
1.3.6 引っ張り付着試験法
1.3.7 剪断付着試験法
1.3.8 超遠心付着試験法
1.3.9 超音波付着試験法
1.3.10 鉛筆引っかき法
1.3.11 衝撃試験
1.3.12 エリクセン試験,屈曲試験
1.4 耐久性
1.4.1 暴露によって発生する欠陥
1.4.2 塗膜の劣化試験
1.5 暴露と促進試験
1.5.1 暴露環境
1.5.2 促進試験法
1.5.3 暴露条件と塗膜の劣化
1.6 塗料と塗膜の欠陥
1.6.1 塗料の欠陥
1.6.2 塗装過程において発生する欠陥
1.7 表面の観察と分析
内容説明
本書は、1985年『高機能塗料材料の開発』として刊行されたもので、塗料と塗膜の複合材料としての発展の可能性を示唆する塗料の基礎と物性について、平易かつ簡明に解説するとともに実用性に重点をおいた応用の可能性を究明することに留意した。特に、従来とかく経験的な思考で進められてきた塗料の研究開発の手法にたいして、体系的な概念にもとづいて、分子構造、溶媒効果、粘弾性および分子間相互作用などの関係について可及的に明らかにすることを試みた。特に、長い間使用されてきた漆、油性、アルキド、セルロース系塗料の中に、塗料しての適性が示されている。
目次
第1章 序論(塗料(塗装)産業の置かれた立場
開発の考え方
現代科学と技術の問題点)
第2章 材料開発の科学(塗料ビヒクルの構造;塗料用ビヒクル成分の溶解性;塗膜の形成過程とレオロジー;顔料の分散;付着性)
第3章 材料の設計と処方化(汎用塗料の設計と処方化;低公害化塗料概論;有機・無機複合体塗料の処方化(有機・無機複合化とセラミックコーティング)
シリコン樹脂塗料の処方化
フッ素樹脂塗料の処方化)
第4章 実用と信頼性(性能と試験法)
-
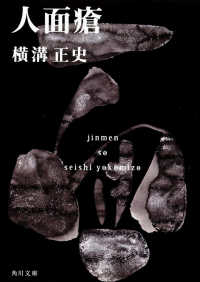
- 和書
- 人面瘡 角川文庫