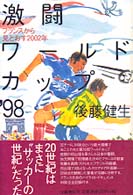出版社内容情報
★前書「老人性痴呆症と脳機能改善薬」刊行から18年。大きく進歩した認知症治療薬開発の最前線!!
★発症のメカニズム,臨床,治療薬の開発手法,開発中の医薬品今後の展望等 最新動向を網羅!!
★第一線で活躍する産学官の研究者20名による分担執筆!!
--------------------------------------------------------------------------------
わが国は世界一の長寿国であり,65歳以上の高齢者数はすでに総人口の20%近くに達している。それに伴い,看護を要する認知障害者数も160~180万人と推定され,さらに増大することが考えられている。認知症の患者数の増大に伴う家庭の負担の増加,医療機関の増設やその設備・介護・運営の充実など,その対策が社会問題として大きくクローズアップされ続けている。
認知症の治療薬は過去において脳循環代謝改善薬と称して多数承認されていたが,平成10年および11年,厚生省通達「慢性期脳血管障害に対する脳循環代謝改善効能を有する医薬品の再評価について」によりたくさんの医薬品から認知症に対する効能が削除され,販売中止または簡略申請に追い込まれた。現在,中枢神経系用薬のなかでその他の中枢神経系用薬に分類され数種が市販されているだけである。
とはいえ,1988年に故朝長正徳教授とともに編集した「老人性痴呆症と脳機能改善薬」を出版して以来,約20年たち,その間,莫大なデータ,認知症に関する基礎・臨床の研究のデータが蓄積され,治療薬・予防薬の新しいスクリーニング法も考案され,医薬品開発が盛んに行われている。
本書は将来の新しい認知症改善薬の開発のために必要な今までの研究および期待される研究を医薬品の開発に関する面から集積したものである。さらに,我々の長期にわたる研究結果を加えている。認知症改善薬の開発に関しては,他の医薬品の開発に比べ広範囲な知識が要求される。本書は開発に従事する研究者の入門書として,また,実験の際の参考書として役立つであろう。
2006年3月 (齋藤洋,本書「はじめに」より抜粋)
--------------------------------------------------------------------------------
阿部和穂 武蔵野大学 薬学部・薬学研究所 教授
新里和弘 東京都立松沢病院 精神科 医長
上野秀樹 東京都立松沢病院 精神科 医長
松下正明 東京都立松沢病院 院長
小倉博雄 エーザイ(株) 創薬第一研究所 評価統轄部長
香月博志 京都大学大学院薬学研究科 薬品作用解析学分野 助教授
岩坪威 東京大学 大学院薬学系研究科 臨床薬学教室 教授
岩田修永 (独)理化学研究所 脳科学総合研究センター 神経蛋白制御研究チーム 副チームリーダー
西道隆臣 (独)理化学研究所 脳科学総合研究センター 神経蛋白制御研究チーム チームリーダー
塚田秀夫 浜松ホトニクス(株) 中央研究所 PETセンター長
小笹貴史 エーザイ(株) 創薬第一研究所
宮川武彦 エーザイ(株) 創薬第一研究所 主幹研究員
大林俊夫 エーザイ(株) 臨床研究センター 統轄課長
田平武 国立長寿医療センター 研究所 所長
齋藤洋 武蔵野大学 薬学部・薬学研究所 教授
糸数七重 国立医薬品食品衛生研究所 生薬部
西沢幸二 (株)ノエビア 商品研究開発部 研究員
守口徹 湧永製薬(株) ヘルスケア研究所 活性探索研究室 室長
杉浦実 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所 カンキツ研究部 品質機能研究室 主任研究官
枝川義邦 早稲田大学 先端科学・健康医療融合研究機構 生命医療工学研究所 講師
--------------------------------------------------------------------------------
目次
第1章 認知症とは(阿部和穂)
1. 認知症の定義
2. 仮性認知症を呈する疾患
2.1 うつ病
2.2 統合失調症
2.3 せん妄
3. 認知症の原因疾患
3.1 脳血管性認知症
3.2 アルツハイマー病
3.3 ピック病
3.4 パーキンソン病
3.5 レビー小体病
3.6 ハンチントン舞踏病
3.7 進行性核上性麻痺(PSP)
3.8 クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)
3.9 エイズ
3.10 脳炎・髄膜炎
3.11 進行麻痺
3.12 神経ベーチェット
3.13 多発性硬化症(MS)
3.14 慢性硬膜下血腫
3.15 正常圧水頭症
3.16 甲状腺機能低下症
3.17 ビタミンB12欠乏
3.18 ウェルニッケ-コルサコフ症候群
3.19 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
3.20 その他
4. 認知症の症状
4.1 中核症状
4.1.1 記憶障害
4.1.2 見当識障害
4.1.3 判断・実行機能障害
4.1.4 失語・失行・失認
4.1.5 病識欠如
4.2 周辺症状
5. 認知症の経過
6. 認知症の治療と介助・介護
第2章 認知症の臨床(新里和弘,上野秀樹,松下正明)
1. 認知症の疫学
1.1 はじめに
1.2 アルツハイマー型の認知症は増えているか?
1.3 MCIの増加
2. 診断の実際
2.1 認知症とは何か?
2.2 アルツハイマー型認知症とは?
2.3 実際のケースから
2.4 血管性認知症とは?
2.5 実際のケースから
3. 治療の実際
3.1 高齢者の薬物動態
3.2 認知症高齢者の薬物療法
3.3 中核症状に対する薬物療法
3.4 実際の臨床場面での使用
3.5 周辺症状の薬物療法
3.6 せん妄状態を伴わないBPSDの薬物療法
4. 臨床現場から治験薬開発に期待すること
4.1 副作用が少なく,長期服用の可能な薬剤の開発を
4.2 BPSDに対する薬剤開発を
4.3 剤形や服用回数にも配慮を
第3章 記憶の脳メカニズム(阿部和穂)
1. はじめに
2. 記憶の構造
2.1 記憶の過程
2.2 記憶の内容による分類
2.3 記憶の保持時間による分類
2.4 従来の分類にあてはまらない記憶
3. 記憶に関与する脳部位
3.1 海馬
3.2 側頭葉
3.3 海馬傍回
3.4 前頭前野
3.5 その他
4. 日常的な物忘れと認知症で問題となる記憶障害
4.1 日常的な物忘れや失敗の原因
4.2 認知症で問題となる記憶障害
5. 記憶と可塑性
5.1 長期のシナプス可塑性
5.2 シナプス伝達の可塑性
5.3 海馬LTPの分子メカニズム
5.4 海馬LTPと記憶・学習の関連
6. 海馬外神経系による海馬シナプス伝達可塑性の調節
6.1 中隔野
6.2 青斑核
6.3 縫線核
6.4 視床下部
6.5 扁桃体
第4章 発症のメカニズム
1. コリン仮説やその他の神経伝達物質関係の変化(小倉博雄)
1.1 歴史的な背景
1.2 「コリン仮説」の登場
1.3 コリン仮説に基づく創薬研究
1.4 コリン作動性神経の障害はADの初期から起こっているか
1.5 コリン仮説とアミロイド仮説
1.6 コリン作動性神経以外の神経伝達物質系の変化
1.7 おわりに -「コリン仮説」がもたらしたもの-
2. 神経変性疾患,認知症と興奮性神経毒性(香月博志)
2.1 はじめに
2.2 脳内グルタミン酸の動態
2.3 グルタミン酸受容体
2.4 興奮毒性のメカニズム
2.5 興奮毒性の関与が示唆される中枢神経疾患
2.5.1 虚血性脳障害
2.5.2 アルツハイマー病
2.5.3 てんかん
2.5.4 パーキンソン病
2.5.5 ハンチントン病
2.5.6 HIV脳症
2.5.7 その他の疾患
2.6 おわりに
3. アルツハイマー病,パーキンソン病,Lewy小体型認知症の発症機序(岩坪威)
3.1 はじめに
3.2 アルツハイマー病,Aβとγ-secretase
3.2.1 アルツハイマー病とβアミロイド
3.2.2 Aβの形成過程とそのC末端構造の意義
3.2.3 AβC末端と家族性ADの病態
3.2.4 プレセニリンとAD,Aβ42
3.2.5 プレセニリンの正常機能-APPのγ-切断とNotchシグナリングへの関与
3.2.6 プレセニリンとγ-secretase
3.2.7 AD治療薬としてのγ-secretase阻害剤の開発
3.2.8 PS複合体構成因子の同定とγセクレターゼ
3.3 アルツハイマー病脳非Aβアミロイド成分の検討-CLAC蛋白を例にとって-
3.4 パーキンソン病,DLBとα-synuclein
3.4.1 α-synucleinとPD,DLB
3.4.2 α-synucleinの機能と構造
3.4.3 α-synucleinの凝集,線維化と神経変性
3.4.4 α-synucleinの翻訳後修飾とパーキンソン病,DLB
3.5 おわりに
4. アルツハイマー病の発症機序-ネプリライシン(岩田修永,西道隆臣)
4.1 はじめに
4.2 脳内Aβ分解システム
4.3 ネプリライシンの酵素化学的性質
4.4 ネプリライシンとAD病理との関係
4.4.1 脳内分布と細胞内局在性
4.4.2 加齢依存的脳内発現レベルの変化
4.4.3 AD脳での発現レベル
4.5 ヒトネプリライシン遺伝子の多型
4.6 ネプリライシンを利用したAD治療戦略
4.7 AD発症メカニズムとの関連
4.8 おわりに
5. グリア細胞の関与(阿部和穂)
5.1 はじめに
5.2 アストロサイトの神経保護的役割
5.3 アルツハイマー病発症におけるアストロサイトの関与
5.4 アルツハイマー病発症におけるミクログリアの関与
第5章 開発手法I-前臨床試験
1. 機能的画像計測による脳循環代謝および神経伝達機能の測定(塚田秀夫)
1.1 はじめに
1.2 PET・SPECTの計測原理
1.3 認知症患者の機能画像所見
1.4 脳血流反応性におよぼすAChE阻害薬の影響
1.5 ドネペジルの多面的評価
1.6 おわりに
2. 脳内神経伝達物質の測定(小笹貴史)
2.1 はじめに
2.2 コリン作動性神経伝達物質
2.2.1 アセチルコリン(ACh)
2.2.2 マイクロダイアリシス法
2.2.3 アセチルコリンエステラーゼ(AChE),コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)
2.3 モノアミン(MA)作動性神経伝達物質
2.3.1 MAおよびそれらの代謝物の測定
2.3.2 MAの測定
2.4 グルタミン酸
3. 培養神経細胞を用いた実験(宮川武彦)
3.1 はじめに
3.2 神経細胞死の抑制
3.3 脳血管性認知症
3.4 アルツハイマー病
3.5 神経回路の再生
3.6 培養神経細胞の問題点
4. 電気生理学的実験(阿部和穂)
4.1 はじめに
4.2 記録法の選択
4.2.1 微小電極法
4.2.2 パッチクランプ法
4.2.3 ユニット記録法
4.2.4 脳波
4.2.5 集合誘発電位の細胞外記録
4.3 標本の選択
4.3.1 生体脳
4.3.2 摘出脳
4.3.3 急性脳スライス
4.3.4 培養脳スライス
4.3.5 急性単離神経細胞
4.3.6 培養単離神経細胞
4.4 実験例
4.4.1 実験例1 麻酔ラットのBLA-DGシナプスにおけるLTP誘導に対する薬物作用解析例
4.4.2 実験例2 ラット海馬スライス標本におけるLTP誘導に対する薬物効果の検討
4.4.3 実験例3 ホールセル記録による培養ラット海馬神経細胞の膜電流応答に対する薬物効果の検討
5. 行動実験(小倉博雄)
5.1 はじめに
5.2 空間学習を評価する試験法
5.2.1 放射状迷路課題
5.2.2 水迷路学習課題
5.3 記憶力を評価する試験法
5.3.1 マウスを用いた非見本(位置)合わせ課題
5.3.2 サルを用いた遅延非見本合わせ課題
5.4 おわりに
6. 脳破壊動物モデル・老化動物(小笹貴史,小倉博雄)
6.1 はじめに
6.2 コリン系障害モデル
6.2.1 興奮系毒素(excitotoxin)による障害
6.2.2 Ethylcholine aziridium ion(AF64A)による障害
6.2.3 immunotoxin192lgG-サポリンによる障害
6.3 脳虚血モデル
6.3.1 慢性脳低灌流モデル
6.3.2 マイクロスフェア法
6.3.3 一過性局所脳虚血モデル
6.3.4 一過性全脳虚血モデル
6.4 老化動物
7. 病態モデル-トランスジェニックマウス-(宮川武彦)
7.1 はじめに
7.2 神経変性疾患に関わるトランスジェニックマウス
7.3 アルツハイマー病モデル
7.4 脳血管性認知症モデル
7.5 APPトランスジェニックマウスの特徴と有用性
8. 脳移植実験(阿部和穂)
8.1 はじめに
8.2 脳移植実験の目的
8.3 材料の選択
8.4 移植方法の選択
第6章 開発手法II-臨床試験(大林俊夫)
1. 臨床試験の流れ
1.1 一般的な臨床試験の流れ
1.2 認知症治療薬の試験目的
1.2.1 第I相試験
1.2.2 第II相
1.2.3 第III相
1.3 認知症治療薬の薬効評価
1.3.1 臨床評価方法ガイドライン概略
1.3.2 認知機能検査
1.3.3 総合評価
2. 治療の依頼等
2.1 治験の依頼手続き
2.2 治験の契約手続き
第7章 現在承認済みまたは開発中の治療薬
1. はじめに(阿部和穂)
2. 神経伝達物質に関連し機能的改善をねらった治療薬
2.1 コリン系薬物
2.1.1 コリンエステラーゼ阻害薬
2.1.2 ムスカリン受容体に作用する薬物
2.1.3 ニコチン受容体作動薬
2.1.4 アセチルコリンの遊離を促進する薬物
2.1.5 コリン取り込み促進薬
2.2 アミン系薬物
2.2.1 セロトニン関連薬物
2.2.2 その他モノアミン関係薬物
2.3 アミノ酸系薬物
2.3.1 AMPA型グルタミン酸受容体修飾薬
2.3.2 GABA受容体修飾薬
3. 神経障害の要因を除く治療薬
4. 神経保護作用を有する治療薬
4.1 神経栄養因子に関連する薬物
4.2 ホルモン関連薬物
4.3 その他
5. NSAIDs
6. スタチン系コレステロール低下薬
7. インスリン抵抗性改善薬
8. アルツハイマー病原因療法薬
8.1 Aβの凝集・生成を阻害する薬
8.1.1 Aβの凝集を阻害する薬
8.1.2 アミロイド斑の形成を阻害する薬
8.1.3 Aβの生成を阻害する薬
8.2 ワクチン療法(田平武)
8.2.1 はじめに
8.2.2 ADのワクチン療法の発明からヒトでの治験へ
8.2.3 副作用としての髄膜脳炎
8.2.4 ワクチン接種患者の剖検脳
8.2.5 ワクチン接種後の臨床経過
8.2.6 ワクチン接種とMRI
8.2.7 経口ワクチンの開発
8.2.8 Aβワクチンのメカニズム
8.2.9 おわりに
9. 記憶増強薬(阿部和穂)
10. 認知症の精神症状や行動異常に対する治療薬
10.1 非定型抗精神病薬
11. その他
11.1 不飽和脂肪酸
11.2 化学構造および作用順序が非公開の薬物
第8章 認知症の治療に有効と考えられる生薬
1. はじめに(齋藤洋)
1.1 西欧の伝統医学
1.2 中国の伝統医学
1.3 最近の医学
2. 中国伝統医学における認知障害治療薬の変遷,日本への影響と将来の方向
2.1 「黄帝内経」
2.2 健忘と認知症
2.3 治健忘(認知症)の処方
2.4 治健忘の生薬
2.5 「千金方」(備急千金要方)
2.6 「医心方」
2.7 江戸時代以後の治健忘の処方
2.8 おわりに
3. 様々な処方,生薬及びこれらの有効成分の研究
3.1 総論(齋藤洋)
3.2 開心散(齋藤洋,糸数七重)
3.2.1 はじめに
3.2.2 開心散及び生薬の受動的回避学習・条件回避学習に対する影響
3.2.3 Amygdala損傷で誘発した学習障害に対する開心散の影響
3.2.4 老化促進マウスの記憶・学習能低下に対する長期投与の開心散の影響
3.2.5 胸腺摘出により誘導される記憶・学習障害に対する長期投与の開心散の影響
3.2.6 海馬の長期増強(LTP)出現に対する開心散及びその構成生薬の影響
3.2.7 おわりに
3.3 加味帰脾湯(西沢幸二)
3.3.1 はじめに
3.3.2 加味帰脾湯の配合生薬について
3.3.3 記憶獲得,固定,再現障害に対する加味帰脾湯の作用
3.3.4 老化動物における記憶障害に対する加味帰脾湯の作用
3.3.5 不安モデル動物に対する加味帰脾湯の作用
3.3.6 神経症以外に対する加味帰脾湯の作用
3.3.7 おわりに
3.4 ニンニク(守口徹)
3.4.1 老化促進モデルマウスに対するAGEの作用
3.4.2 ラット胎仔海馬神経細胞の生存に対するAGEとその関連化合物の作用
3.4.3 海馬神経細胞の生存促進活性を持つための構造活性相関の検討
3.5 サフラン(杉浦実,阿部和穂,齋藤洋)
3.5.1 はじめに
3.5.2 アルコール(エタノール)誘発学習障害に対するCSEの影響
3.5.3 in vivo(麻酔下ラット)における海馬LTP発現に対するエタノールとCSEの影響
3.5.4 CSE中の有効成分の探索
3.5.5 ラット海馬スライス標本のCA1野及び歯状回におけるLTPに対するエタノールとクロシンの効果
3.5.6 NMDA受容体応答に対するエタノールとクロシンの効果
3.5.7 エタノール誘発受動的回避記憶・学習障害に対するクロシンの効果
3.5.8 クロシン単独のLTP促進作用(未発表)
3.5.9 おわりに
3.6 地衣類由来の多糖(枝川義邦)
3.6.1 地衣類とは
3.6.2 地衣類の分類
3.6.3 私たちの生活に利用される地衣類
3.6.4 地衣類固有の代謝産物―地衣成分―
3.6.5 地衣成分としての多糖類
3.6.6 地衣類由来の多糖がもつ学習改善作用
3.6.7 記憶の基礎メカニズムと地衣類由来多糖の作用
3.6.8 海馬LTP増大を導くメカニズム
3.6.9 相反するメカニズムのバランスに基づいたLTP調節機構
3.6.10 LTP増大作用をもつ地衣類由来多糖の共通性
第9章 今後期待される新分野
1. はじめに(阿部和穂)
2. 診断法の開発
3. 治療装置の開発
4. 再生医療
5. 多機能分子としてのbFGF(阿部和穂,齋藤洋)
6. 脳循環代謝改善剤(齋藤洋)
6.1 はじめに
6.2 中国伝統医学に見られる認知症改善薬の変遷
6.3 脳循環代謝改善薬
6.4 脳神経細胞治療薬
6.5 配合による相互作用
目次
第1章 認知症とは
第2章 認知症の臨床
第3章 記憶の脳メカニズム
第4章 発症のメカニズム
第5章 開発手法1―前臨床試験
第6章 開発手法2―臨床試験
第7章 現在承認済みまたは開発中の治療薬
第8章 認知症の治療に有効と考えられる生薬
第9章 今後期待される新分野
著者等紹介
齋藤洋[サイトウヒロシ]
武蔵野大学薬学部・薬学研究所教授
阿部和穂[アベカズホ]
武蔵野大学薬学部・薬学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
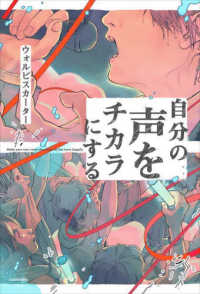
- 和書
- 自分の声をチカラにする