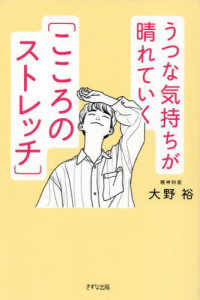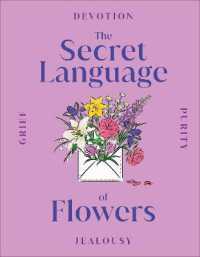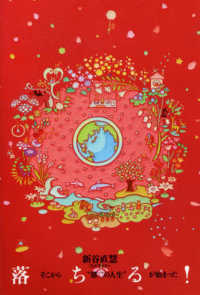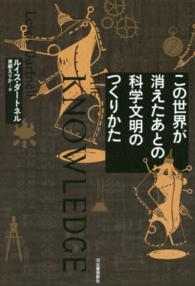出版社内容情報
★高い変換効率や優れた燃料適応性など,多くのメリットを有するSOFCに今世界が注目!
★発電システムや構成材料など,実用化に向けた最先端の研究開発動向を解説!
★標準化や劣化の問題など,今後の課題も詳しく解説!
★国内第一線の研究者による分担執筆!
--------------------------------------------------------------------------------
昨今の燃料電池の過熱気味の開発競争の中,固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell: SOFC)は化石燃料を使用するエネルギー変換技術の中でも,最高の効率が達成可能であると期待されている。以前はリン酸形,溶融炭酸塩形に続く第3世代燃料電池と呼ばれていたが,最近では固体高分子形燃料電池の強力な開発・技術発展に牽引される形で次世代発電技術として注目を集めている。海外では車載用の補助電源としてのSOFCの応用などが大きな関心を呼んでおり,国際学会では欧米の過熱した研究努力が目に付くが,国内では,定置用を目的とした技術の蓄積が着実になされ,SOFCに関しては諸外国に劣らない先端技術を保有していると考えられる。国内におけるSOFC開発の歴史は古く,NEDO第I期プロジェクトが1989年に開始されている。セル構造や構成材料,セラミックセル作製技術などに多くの技術的蓄積と経験がある。SOFCの特徴は燃料電池の中で最も高温作動であり,廃熱,高温排ガスを利用することにより,高効率となると期待されている。また,全固体で腐食や電解質の揮発の問題がなく,高温に起因する高い燃料適応性や貴金属触媒が不必要など,他の燃料電池にない優れた特徴を持っている。一方で,高温で各材料の機能性を持続するための熱劣化の抑制や高温ガスシールなど,これまで他分野で要求されなかった技術の発展が不可欠であったために,最後に実用化される高効率燃料電池と位置づけられてきた。現在,コージェネレーションの試験システムが運転に供され,小型スタックにおいて高い発電効率が実証されるなどプレスをにぎわす機会も多くなり,より実用を見渡せる新たな段階に入りつつあるといってよい。国内ではコージェネレーション機をまず商用化しようという動きが顕在化しつつある。SOFC開発の情報交換の舞台として,電気化学会の元でSOFC研究会が組織され,国際会議などを主催してきたが,今後システムや応用分野を見据えた,より広い分野の協力体制が必要な段階と考えられる。このような現状で,国内の最先端技術を網羅し,将来の開発課題やシーズなどについてまとめておくことは有意義であると考える。本書はそのような背景から,各社または各研究機関の最新の状況を比較的自由に執筆していただくよう依頼したもので,国内におけるSOFC開発の現状を把握し,新た展開に踏み出す一助となれば幸いである。
2005年10月 江口浩一
--------------------------------------------------------------------------------
江口浩一 京都大学大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻 教授
横川晴美 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 総括研究員 兼 燃料電池グループリーダー
堀田照久 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 燃料電池グループ 主任研究員
氏家孝 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 燃料電池・水素技術開発部 主査
服部雅俊 中部電力(株) 電力技術研究所 エネルギーエンジニアリンググループ 燃料電池チーム 研究副主査
稲垣亨 関西電力(株) エネルギー利用技術研究所 チーフリサーチャー
鵜飼健司 東邦ガス(株) 基盤技術研究部 材料基盤技術グループ 係長
松崎良雄 東京ガス(株) 総合研究所 主席研究員
荒川正泰 日本電信電話(株) 環境エネルギー研究所 主幹研究員 グループリーダー
久留長生 三菱重工業(株) 長崎造船所 火力プラント設計部 燃料電池開発課 課長
武信弘一 三菱重工業(株) 神戸造船所 新製品・宇宙部 新エネルギー設計課 主席技師
上野晃 東陶機器(株) 総合研究所 事業開発部 燃料電池開発グループ グループリーダー
上原利弘 日立金属(株) 冶金研究所 主任研究員
石原達己 九州大学 大学院工学研究院 応用化学部門 教授
荒地良典 関西大学 工学部 専任講師
伊藤響 (財)電力中央研究所 材料科学研究所 機能・機構発現領域 主任研究員
川田達也 東北大学 多元物質科学研究所 融合システム研究部門 複合系応用システム研究分野 助教授
嘉藤徹 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 燃料電池グループ 主任研究員
菊地隆司 京都大学大学院 工学研究科 物質エネルギー化学専攻 助教授
高橋収 出光興産(株)中央研究所 エネルギー研究室 主任部員
酒井夏子 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 燃料電池グループ 主任研究員
鈴木健二郎 芝浦工業大学 大学院機械工学専攻 教授
--------------------------------------------------------------------------------
目次
第1章 固体酸化物形燃料電池(SOFC)の原理と基礎研究(江口浩一)
1. はじめに
2. SOFCの動作原理と基本構成材料
3. SOFCのセル構造,構成材料,及び作製法
3.1 電池の構造と支持形式
3.2 各種SOFCセル及びスタックの構造と作製法
3.3 SOFCの構成材料と低温作動化
4. 燃料電池の燃料適応性
5. 結言
第2章 SOFCの開発動向(横川晴美,堀田照久)
1. はじめに
2. 円筒縦縞型SOFCの開発
3. 円筒横縞型SOFCの開発
4. 平板型SOFCの開発
5. 円筒平板型
6. マイクロチューブ型SOFC
第3章 NEDOプロジェクトにおけるSOFC開発の経緯と現状(氏家孝)
1. NEDOプロジェクト開発経緯の概要
2. 固体酸化物形燃料電池システム技術開発の概要
2.1 研究開発の目的
2.2 研究開発項目
2.3 研究開発の目標・内容
3. 今後について
第4章 電力事業から見たSOFC
1. コージェネレーション(服部雅俊)
1.1 はじめに
1.2 電力各社の開発動向
1.3 中部電力における開発動向
1.4 おわりに
2. 中温作動システムの開発(稲垣亨)
2.1 背景
2.2 高性能セルの開発
2.3 熱自立発電モジュールの開発
2.4 1kW級発電システムの実証
2.5 今後の取り組み
第5章 ガス会社におけるSOFCの取り組み
1. 東邦ガスにおけるスカンジア安定化ジルコニア電解質を用いたSOFCの開発状況(鵜飼健司)
1.1 はじめに
1.2 開発中のシステム概要
1.2.1 開発コンセプト
1.2.2 高性能・高信頼性単セルの搭載
(1) ScSZ電解質について
(2) 高性能・高信頼性単セルの開発
1.2.3 システムの概要
(1) 初号機の開発
(2) 愛・地球博展示システムの概要
1.3 おわりに
2. 中低温作動支持膜式SOFCの研究開発(松崎良雄)
2.1 緒言
2.2 支持膜式単セルの作製方法
2.3 応力緩和スタックの構造
2.4 Cr被毒への対策
2.4.1 YSZ電解質上LSM電極のCr被毒
2.4.2 様々な電解質上のLSM電極に対するCr被毒
2.4.3 SDC電解質上の様々な電極に対するCr被毒
2.4.4 Cr被毒対策に関する結論
2.5 スタックの作製と評価
2.5.1 発電特性
2.5.2 燃料ガスの基板内拡散特性
2.5.3 セル内部の電流密度分布と燃料利用率特性の予測
2.6 まとめ
第6章 情報通信サービス事業におけるSOFCへの取り組み(荒川正泰)
1. 情報通信サービス事業におけるエネルギー需要の動向と燃料電池への要求条件
2. 電解質材料
3. 空気極材料
4. 燃料極支持形SOFCの特性
5. おわりに
第7章 SOFC発電システムの展開
1. 円筒型燃料電池の開発とハイブリッドシステムへの応用(久留長生)
1.1 円筒型燃料電池の開発
1.1.1 SWPCにおける円筒型SOFCの開発状況
1.1.2 三菱重工業における円筒型SOFCの開発状況
1.2 ハイブリッドシステムへの応用
1.2.1 米国SECA(SOLID-STATE ENERGY CONVERSION ALLIANCE)プロジェクト
1.2.2 NEDOプロジェクト
1.2.3 ロールスロイス社
2. MOLB形燃料電池とコージェネレーションシステム(武信弘一)
2.1 はじめに
2.2 電池構造
2.3 電池の開発経緯
2.4 実用化電池の開発
2.4.1 改良型MOLBの開発
2.4.2 連結式一体積層形(T-MOLB形)構造の開発
2.5 数10kW級モジュール開発
2.6 熱自立モジュールの開発
2.6.1 モジュールの特長
2.6.2 熱交換器の集合化検証
2.6.3 モジュール運転制御自動化検証
2.7 小容量機開発
2.8 200kW級コージェネレーションシステム開発
2.8.1 開発目標および実施内容
2.8.2 開発状況
2.9 おわりに
3. 円筒型燃料電池の湿式セルスタック製造と応用(上野晃)
3.1 概要
3.2 定置型燃料電池用セルスタック開発状況
3.2.1 単セル開発状況
3.2.2 スタック開発状況
3.3 可搬型燃料電池用セルスタック開発状況
3.3.1 低温作動形マイクロチューブセル開発
3.3.2 マイクロチューブセルスタックの開発
3.4 おわりに
第8章 SOFCの構成材料
1. 金属セパレータ材料(上原利弘)
1.1 はじめに
1.2 種々合金の位置付け
1.3 Cr基合金
1.4 Ni基合金
1.5 Fe-Crフェライト系合金
1.6 ZMG232
1.7 今後の課題と展望
2. 電解質材料-ランタンガレート系(石原達己)
2.1 はじめに
2.2 新規酸化物イオン伝導体としてのLaGaO3ペロブスカイト
2.3 LaGaO3系ペロブスカイトのSOFCへの応用
2.4 おわりに
3. 電解質材料-スカンジア安定化ジルコニア(荒地良典)
3.1 はじめに
3.2 蛍石型構造を示す酸化物イオン伝導体
3.3 蛍石型酸化物の酸化物イオン伝導性
3.4 ジルコニアを基体とした酸化物イオン伝導体
4. 燃料極材料(伊藤響)
4.1 燃料極における反応過程
4.2 燃料極の要件と種類
4.2.1 燃料極に要求される条件
4.2.2 燃料極材料の種類
4.3 サーメット燃料極材料
4.3.1 熱膨張挙動
4.3.2 ガス拡散性
4.3.3 導電率
4.3.4 化学的・熱力学的相互作用
(1) インターコネクタと相互作用
(2) 燃料ガス中不純物との反応
4.3.5 燃料極材料の製法
4.4 おわりに
5. 空気極材料(川田達也)
5.1 空気極反応経路と電極設計
5.2 空気極材料に求められる要件
5.3 高温型SOFC用空気極材料
5.3.1 安定性と不定比性,導電率
5.3.2 酸素輸送経路と電極反応
5.3.3 電解質との両立性
5.3.4 長期特性変化と陽イオン輸送
5.3.5 実用電極の設計
5.4 中低温型SOFC用空気極材料
5.4.1 LaCoO3系ペロブスカイトの酸素不定比性と導電率
5.4.2 (La,Sr)CoO3の電極反応
5.4.3 LaCoO3系電極と電解質
5.4.4 La(Co,Fe)O3系ペロブスカイト
第9章 SOFCの課題
1. SOFCにおける標準化(嘉藤徹)
1.1 はじめに
1.2 燃料電池の国際標準化動向
1.3 日本の規格標準化に対する体制
1.4 燃料電池に対する日本の規格標準化の取り組み
1.5 規格・標準化を指向した高精度SOFC効率測定技術の開発
1.6 水素流量基準および都市ガス流量基準の開発
1.7 SOFCの実用化にむけて
2. SOFCの燃料適応性(菊地隆司)
2.1 はじめに
2.2 炭素析出領域とNi-YSZ燃料極を用いた種々の燃料での発電特性
2.3 塩基性酸化物および貴金属添加によるNi-YSZ燃料極の燃料適応性向上
2.4 混合伝導体を用いた新規燃料極による燃料適応性の向上
2.5 まとめ
3. 燃料電池用の石油改質技術(高橋収)
3.1 はじめに
3.2 石油燃料
3.2.1 石油精製工程と製品性状
3.2.2 燃料電池の原燃料に要求されること
3.3 燃料電池用水素の製造方法
3.3.1 水素の製造・供給方式
3.3.2 水素製造技術
(1) 概要
(2) 脱硫工程
(3) 改質工程
3.4 灯油からの水素製造
3.4.1 灯油脱硫技術
3.4.2 灯油改質技術
3.4.3 燃料電池用灯油改質器の開発と燃料電池システムの実証試験
3.5 今後の課題とSOFCへの適用
4. SOFCの劣化要因について(酒井夏子,横川晴美)
4.1 はじめに
4.2 劣化の種類と要因
4.2.1 形状変化を伴う劣化
4.2.2 拡散・反応が主原因となる劣化
(1) 外部要因による劣化
(2) 材料自体の劣化
(3) 異種材料間の反応・拡散による劣化
5. SOFC単体セルへとSOFCモジュールの数値シミュレータ(鈴木健二郎)
5.1 まえがき
5.2 数値モデル
5.2.1 モデルの概要
5.2.2 計算手法
5.3 シミュレーションの結果
5.3.1 セル単体に対するシミュレーション
5.3.2 円筒型SOFCモジュールの数値モデル
5.4 おわりに
目次
第1章 固体酸化物形燃料電池(SOFC)の原理と基礎研究
第2章 SOFCの開発動向
第3章 NEDOプロジェクトにおけるSOFC開発の経緯と現状
第4章 電力事業から見たSOFC
第5章 ガス会社におけるSOFCの取り組み
第6章 情報通信サービス事業におけるSOFCへの取り組み
第7章 SOFC発電システムの展開
第8章 SOFCの構成材料
第9章 SOFCの課題
著者等紹介
江口浩一[エグチコウイチ]
京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学専攻教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。