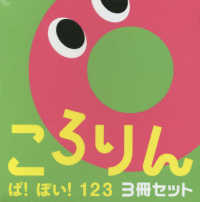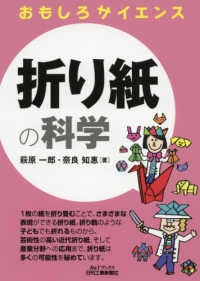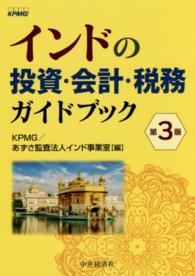出版社内容情報
★基盤研究から新しい食品まで,データに基づき解説!!
★近年注目の「機能性食品成分」のがん予防効果を詳述!!
--------------------------------------------------------------------------------
日本人の食生活の急激な欧米化の結果,男女共に大腸がんの発症が急激に増加し,男性の前立腺がん,女性の乳がんも急増するなど,今まで日本の長寿を支えてきた日本型食生活も大きな曲がり角にきているといっても過言ではない状況です。このような背景のなかで,われわれの食生活をもう一度見直そうという動きは世界的な流れとなり,特に注目されたのが,日常私たちが摂取する「非栄養素」成分,すなわち,ポリフェノール類やイオウ化合物,テルペノイドやアルカロイド,カロテノイドなど,「栄養素」以外の食品成分でした。
「がん予防成分」を科学的にも納得できるようにデザインされた食生活で摂取することにより,天寿を全うするまでがんの進行をスローダウンさせることで老化と足並みを揃えることが大切でしょう。そのためには,単に「ある食品にがん予防効果がある」といった現象論的なデータではなく,「バイオマーカー」を基盤にした最新の評価システムを用いた「がん予防フードファクター」の最新の研究が紹介されている点は,本書の基本的な概念として大きな注目を集めるものと期待されています。
(本書「はじめに」より抜粋)
2005年4月 名古屋大学 大澤俊彦
--------------------------------------------------------------------------------
大澤俊彦 名古屋大学 大学院生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 食品機能化学研究室 教授
大東肇 京都大学 大学院農学研究科 食品生物科学専攻 教授
小林博 (財)札幌がんセミナー 理事長
津金昌一郎 国立がんセンター がん予防・検診研究センター 予防研究部 部長
金沢和樹 神戸大学 農学部 教授
橋本堂史 神戸大学 農学部 助手
豊國伸哉 京都大学 大学院医学研究科 基礎病態学講座病態生物医学 助教授
中村宜督 岡山大学 大学院自然科学研究科 助教授
傳田阿由美 奈良県立医科大学 分子病理 講師
森光康次郎 お茶の水女子大学 生活科学部 食品化学研究室 助教授
西野輔翼 京都府立医科大学 分子生化学 教授
森秀樹 岐阜大学 大学院医学研究科 腫瘍病理 教授
上原万里子 東京農業大学 応用生物科学部 栄養科学科 助教授
太田好次 藤田保健衛生大学 医学部 化学教室 教授
福澤健治 徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 衛生薬学分野
下位香代子 静岡県立大学 環境科学研究所 教授
石川秀樹 京都府立医科大学 大学院医学研究科 分子標的癌予防医学博士研究員 兼 地域保健医療疫学 客員講師
村上明 京都大学 大学院農学研究科 食品生物科学専攻 助手
原征彦 三井農林株式会社 食品総合研究所 所長
矢澤一良 東京海洋大学 大学院海洋科学技術研究科 ヘルスフード科学(中島董一郎記念寄附講座)教授
山本順寛 東京工科大学 バイオニクス学部 教授
立花宏文 九州大学 大学院農学研究院 生物機能科学部門 助教授
越阪部奈緒美 明治製菓?梶@食料健康総合研究所 研究企画部 次席研究員
?コ田春邦 京都府立医科大学 分子医科学教室 助手
古倉聡 京都府立医科大学 大学院医学研究科 生体安全医学講座 助教授
内藤裕二 京都府立医科大学 大学院医学研究科 消化器病態制御学 講師
吉川敏一 京都府立医科大学 大学院医学研究科 生体機能制御学 教授
許栄海 湧永製薬?梶@ヘルスケア研究所 製品評価研究室 室長
池川哲郎 日本統合医学研究会 常任理事
矢野昌充 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所 カンキツ研究部 上席研究官
矢ケ崎一三 東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 生命農学部門 教授
三浦豊 東京農工大学大学院 共生科学技術研究部 生命農学部門 助教授
細野明義 信州大学名誉教授
熊澤茂則 静岡県立大学 食品栄養科学部 助教授
松江一 青森県立保健大学 大学院健康科学研究科 教授
奈良岡哲志 青森県工業総合研究センター 環境技術研究部 部長
内沢秀光 青森県工業総合研究センター 環境技術研究部 総括主任研究員
高谷芳明 名城大学 薬学部薬学科 医薬資源化学研究室 助教授
津田洋幸 名古屋市立大学 大学院医学研究科 分子毒性学分野 教授
深町勝巳 名古屋市立大学 大学院医学研究科 分子毒性学分野
大嶋浩 名古屋市立大学 大学院医学研究科 分子毒性学分野
飯郷正明 国立がんセンター研究所 化学療法部(2003年8月迄)
現国立がんセンター研究所 がん予防基礎研究プロジェクト
高須賀信夫 国立がんセンター研究所 化学療法部(2003年8月迄)
現国立がんセンター研究所 がん予防基礎研究プロジェクト
松田栄治 国立がんセンター研究所 化学療法部(2003年8月迄)
現国立がんセンター研究所 がん予防基礎研究プロジェクト
関根一則 名古屋市立大学;国立がんセンター研究所;森永乳業?梶@栄養科学
研究所・生物科学研究所
大久保重俊 名古屋市立大学;国立がんセンター研究所;森永乳業?梶@栄養科学
研究所・生物科学研究所
神津隆弘 国立がんセンター中央病院 内視鏡部 がん予防検診研究センター
島村眞里子 東京都臨床医学総合研究所 医薬研究開発センター
細川雅史 北海道大学 大学院水産科学研究科 機能性物質化学研究室 助教授
田中卓二 金沢医科大学 腫瘍病理 教授
--------------------------------------------------------------------------------
第1編 概論編
第1章 がん予防食品の開発の現状と動向(大澤俊彦)
1. はじめに
2. 「フードファクター」とは?
3. 「がん予防」を目的とした「フードファクター」探索と「バイオマーカー」の確立
4. 酸化ストレス評価のための新しい「バイオマーカー」の探索
5. 抗酸化食品因子への期待
第2章 がん予防科学の動向と今後の展開(大東肇)
1. はじめに
2. β‐カロテンの介入試験が残したもの
3. 食によるがん予防に求められる今日的課題
4. 予防の対象群は?
5. 複合系による予防効果の増強戦略
6. おわりに
第3章 がん予防とライフスタイル(小林博)
1. がん予防のための身近なライフスタイル
1.1 まえがき
1.2 米国の罹患率の低下から学ぶ
1.3 とくに禁煙の効果
1.4 食生活改善による予防 Behavioral Prevention
1.5 ライフスタイルの改善-いつから始めるか
1.6 がんの化学予防 Chemoprevention
1.7 カロリー摂取制限の効果
1.8 身体的な運動の効果
1.9 ストレスの発散によるがん予防
1.10 炎症の阻止によるがん予防
2. がん予防に留意すべきライフスタイル
2.1 「いい」といわれるものの真偽を問う
2.2 検診を受けるライフスタイルを-あとがきに代えて
第2編 基盤的研究
第1章 疫学からみたがん予防(津金昌一郎)
-食品成分・食習慣改善によるがん予防の可能性-
1. がん予防の可能性
2. 疫学研究:がん予防におけるエビデンスを作る研究
3. がん予防効果の評価における科学的証拠
4. 日本人における食品摂取・食習慣改善によるがん予防を目指して
5. 予防介入研究によるがん予防効果の証明
6. β-カロテンによる無作為化比較試験から学ぶもの
7. おわりに
第2章 がん予防食品因子とデータベース(金沢和樹,橋本堂史)
1. がん予防食品因子研究の進展
2. 本来のがん予防作用
2.1 紫外線・放射線防御
2.2 発がん物質を消化管内で除去
2.3 間接発がん物質の抑制
2.4 抗酸化
2.5 第2相酵素誘導
2.6 ステロイドホルモンにかかわる発がんの予防
3. がん細胞に対する作用
3.1 G0/G1期停止誘導
3.2 G2/M期停止誘導
3.3 MAPキナーゼ阻害
3.4 アポトーシス誘導
3.5 メタロプロテアーゼ阻害
3.6 サイトカイン分泌調節
3.7 血管新生抑制
3.8 トポイソメラーゼ阻害
3.9 標的遺伝子の調節
4. バイオアベイラビリティの問題
5. 有効ながん予防成分を選び出す7つの研究戦略
6. 注目されている成分
第3章 酸化ストレスバイオマ-カーとがん予防(豊國伸哉)
1. はじめに
2. 酸化ストレスと発がんの関連
3. 鉄による発がんモデルとその標的遺伝子
4. 遺伝学的手法による標的遺伝子の探索
5. 発現の変化する標的遺伝子の探索
6. チオレドキシン系の変化
7. 酸化ストレスバイオマーカー
8. 酸化ストレスバイオマーカーのがん予防への応用
9. おわりに
第4章 がん抑制におけるアポトーシスの意義(中村宜督)
1. はじめに
2. 細胞死の定義とその役割
2.1 アポトーシスとネクローシス
2.2 アポトーシス,ネクローシスの分子機構
3. 発がんにおけるアポトーシスの意義
4. アポトーシスを誘導する食品成分
5. イソチオシアネートによるアポトーシス誘導作用とその分子機構
6. おわりに
第5章 ノックアウトマウスを用いたCOX2の作用と抑制(傳田阿由美)
1. はじめに
2. COXとその関連経路
3. COX-1とCOX-2
4. NSAIDsによる大腸癌予防研究からCOX-2へ
5. 遺伝子改変動物・阻害剤・拮抗剤を用いたin vivo発がん研究から見えてきたCOX-2,
COX-1およびその他のCOX経路関連遺伝子の発がんへの関与機構
5.1 COX-2,COX-1遺伝子ノックアウトによる大腸発がんの抑制
5.2 APC△716 マウス小腸ポリープにおけるCOX-2>EP2>血管新生のループ
5.3 Min,APC??1309マウスおよびAOM誘発小腸・大腸発がんでのEP1,EP4による発がん促進的シグナルとEP31による抑制シグナル
5.4 cPLA2ノックアウトによるAPC△716 およびMinマウス小腸発がんの抑制
5.5 COX-2,COX-1ノックアウトによる早熟分化亢進を介するマウス皮膚発がんの抑制
5.6 COX経路関連遺伝子導入による造腫瘍性
5.7 種々の実験的臓器発がんへのCOX-2,COX経路関連遺伝子への関与
6. COX-2の発がんへの関与機構-最近の知見
7. 腫瘍細胞にてCOX-2が構成的に発現する機構
8. おわりに
第3編 成分・素材編
第1章 硫黄化合物(森光康次郎)
1. はじめに
2. ポリスルフィド類と発がん抑制
3. ネギ属香辛野菜の毒性とポリスルフィド類
4. ポリスルフィド類と第二相解毒酵素誘導
5. ポリスルフィド類による細胞内レドックスサイクリング
第2章 カロテノイド(西野輔翼)
1. カロテノイドによるがん化学予防
2. カロテノイドの作用機序
3. 今後の展望
第3章 ポリフェノール(森秀樹)
1. はじめに
2. ポリフェノールの種類と抗発がん,抗がん作用
2.1 茶ポリフェノール
2.2 クロロゲン酸
2.3 フェルラ酸
2.4 カフェイ酸
2.5 エラグ酸
2.6 プロトカテク酸
2.7 レスベラトール
2.8 シリマリン
2.9 その他のポリフェノール
3. 発がん予防および抗がん作用の機序
4. おわりに
第4章 クルクミノイド(大澤俊彦)
1. はじめに
2. 「アキウコン」とは
3. 「クルクミノイド」による「がん予防」
4. 「テトラヒドロクルクミン」の機能
第5章 イソフラボン(上原万里子)
1. はじめに
2. イソフラボンの基本構造と分布
3. イソフラボンの分布方法の種類
3.1 ガスクロマトグラフィ-マススペクトロメトリ-(GC-MS)
3.2 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)
3.3 イムノアッセイ
4. イソフラボンの代謝
4.1 イソフラボンの吸収経路
4.2 イソフラボンの代謝を修飾する物質
4.3 注目されるイソフラボン代謝産物のEquol
5. イソフラボンのがん予防効果
5.1 抗酸化作用が有するイソフラボンのがん予防効果
5.2 選択的エストロゲン受容修飾因子(SERM)としてのイソフラボンのがん予防効果
5.3 イソフラボンの抗エストロゲン作用以外のがん予防効果
5.4 疫学研究が示すイソフラボンの乳がんおよび前立腺がん予防効果
6. イソフラボンのNegative Effects
7. おわりに
第6章 ビタミン(太田好次,福澤健治)
1. はじめに
2. ビタミンA
2.1 疫学調査
2.2 サプリメント効果
2.3 実験的検討
3. ビタミンD
3.1 疫学調査
3.2 サプリメント効果
3.3 実験的検討
4. ビタミンE
4.1 疫学的調査
4.2 サプリメント効果
4.3 実験的検討
5. ビタミンK
5.1 疫学的調査
5.2 サプリメント効果
5.3 実験的検討
6. ビタミンC
6.1 疫学的調査
6.2 サプリメント効果
6.3 実験的検討
7. ビタミンB6
7.1 疫学的調査
7.2 サプリメント効果
7.3 実験的検討
8. ビタミンB12
8.1 疫学的調査
8.2 サプリメント効果
8.3 実験的検討
9. 葉酸
9.1 疫学的調査
9.2 サプリメント効果
9.3 実験的検討
10. ナイアシン
10.1 疫学的調査
10.2 サプリメント効果
10.3 実験的検討
第7章 フラボノイド(下位香代子)
1. はじめに
2. 疫学調査におけるがんのリスク
3. 発がん物質の解毒代謝
4. 摂取量のバイオマーカー:血中動態と尿中排泄量
5. 血中代謝物の局所における有効性
6. おわりに
第8章 イソチオシアネート(森光康次郎)
1. はじめに
2. イソチオシアネートの生理作用の二面性
3. イソチオシアネートの吸収について
4. アブラナ科野菜としての効果
第9章 食物繊維(石川秀樹)
1. はじめに
2. 食物繊維と大腸癌の観察的疫学研究
3. 食物繊維による大腸癌予防介入試験
4. 介入試験の成績に関する考察
4.1 食物繊維の摂取で大腸癌の発生を予防することはできない
4.2 腺腫の発生を大腸癌の中間代理指標とする事の問題
4.3 試験期間・時期の問題
4.4 食物繊維の種類・投与量に関する問題
4.5 食事調査,食事指導の問題
4.6 参加者集団の問題
5. 最後に
第10章 テルペノイド(村上明)
1. はじめに
2. Terpenoidの分類と生合成
3. 発がん予防活性と作用メカニズム
4. 求電子性発がん予防食品成分 zerumbone
5. おわりに
第11章 緑茶カテキン(原征彦)
1. 茶カテキンによる発がん予防の可能性
2. 茶カテキンによるがん予防臨床試験の戦略
3. 「ポリフェノン○RE」による発がん予防臨床試験
第12章 DHA,EPA(矢澤一良)
1. はじめに
2. EPAの発がん抑制
2.1 エイコサイノド,サイトカイン産生と免疫状態の改変
2.2 細胞膜流動性,被酸化性に対する影響
2.3 がん細胞の分化誘導
2.4 がん増殖,転移の抑制
2.5 がん性悪液質改善作用
3. DHAの発がん抑制
3.1 DHAの発がん抑制のメカニズム
3.2 n-6系高度不飽和脂肪酸による発がん促進作用
3.3 DHAによる抗がん剤の副作用軽減効果
3.4 DHAによるがんの転移抑制
4. おわりに
第13章 コエンザイムQ(山本順寛)
1. コエンザイムQの発見
2. 抗酸化作用
3. コエンザイムQ10とスタチン類
4. 加齢に伴う細胞内濃度の減少
5. 所要量と安全性
6. がん予防食品としての可能性
7. 紫外線発がん実験系での検証
8. おわりに
第4編 新しい機能食品
第1章 植物系
1. ブロッコリーのがん予防効果(大澤俊彦)
1.1 アブラナ科野菜の解毒酵素誘導活性
1.2 ブロッコリースプラウトと「がん予防」
1.3 スルフォラファンの抗酸化活性
1.4 スルフォラファンの解毒酵素誘導のメカニズム
2. 緑茶カテキンエピガロカテキンガレート(立花宏文)
2.1 はじめに
2.2 がん予防の疫学調査
2.3 がん予防臨床試験
2.4 EGCGの生体利用性
2.5 EGCGの発がん抑制作用
2.6 EGCGのアポトーシス誘導作用
2.7 EGCGのがん転移阻害作用
2.7.1 血管新生阻害作用
2.7.2 浸潤転移阻害
2.8 EGCGの抗がん作用に関与する標的分子
2.8.1 マトリックスメタロプロテアーゼ
2.8.2 プロテアソーム
2.8.3 ERK1/2,Akt
2.8.4 DNAメチルトランスフェラーゼ
2.8.5 Bcl-2
2.8.6 ラミニンレセプター:EGCGの細胞増殖抑制作用を仲介する受容体
2.9 おわりに
3. カカオポリフェノールの発ガン予防作用(越阪部奈緒美)
3.1 緒言
3.2 抗変異原作用
3.3 染色体異常誘発抑制作用
3.4 皮膚二段階発ガンモデルに対する作用
3.5 多臓器発ガンモデルに対する作用
3.6 おわりに
4. ハーブ類のがん予防(?コ田春邦)
4.1 はじめに
4.2 試料の評価方法
4.2.1 試験管内細胞を用いたNO作用に対する抑制効果の評価法
4.2.2 小動物を用いたNO作用に対する抑制効果の評価法
4.3 おわりに
5. イチョウ葉エキス(古倉聡,内藤裕二,吉川敏一)
5.1 はじめに
5.2 EGb761の薬理作用
5.2.1 EGb761の活性酸素・フリーラジカル消去活性
5.2.2 EGb761の脂質過酸化抑制作用
5.2.3 活性酸素産生抑制作用
5.3 発癌におけるフリーラジカルの関与
5.4 イチョウ葉エキスや抗酸化剤による癌の予防
6. ニンニクの癌予防効果(許栄海)
6.1 はじめに
6.2 ニンニクの加工法と成分
6.3 熟成ニンニク抽出液
6.4 デザイナーフーズプログラム
6.5 化学発癌抑制作用
6.6 免疫調節作用
6.7 抗酸化作用
6.8 メカニズム
6.9 ヒトを対象とした研究
6.10 おわりに
7. きのこ -予防医学におけるバイオマーカーの評価システム- (池川哲郎)
7.1 抗がん作用
7.2 発がん予防作用
7.3 疫学研究
7.4 EEMの臨床研究
7.5 きのこと漢方薬
7.6 その他の作用
7.7 医食同源,薬食同源
8. カンキツ(矢野昌充)
8.1 疫学研究におけるカンキツ類
8.1.1 「国際版 がん予防の15か条」にみるカンキツ
8.1.2 カンキツとがん予防に関する最近の知見
8.2 カンキツ成分の発がん抑制作用
8.2.1 β‐クリプトキサンチン(β‐cry)
(1) 発がん修飾作用
(2) 疫学研究
(3) 発がん抑制の機序
(4) β‐cryとは
(5) カンキツにおける含有量
(6) 調製技術
8.2.2 ノビレチン(NOB)
(1) NOBとは
(2) 発がん抑制作用
(3) 作用機序
(4) カンキツにおける存在量
(5) 調製法
8.2.3 オーラプテン(AUR)
(1) AURとは
(2) 発がん抑制作用
(3) 作用機序
(4) カンキツにおける含有量
(5) 調製法
8.3 おわりに
9. コーヒー(矢ヶ崎一三,三浦豊)
9.1 はじめに
9.2 コーヒーの成分
9.3 コーヒーの発がんに対する作用
9.4 コーヒーの癌細胞に対する作用
9.4.1 癌細胞の増殖・浸潤・転移について
9.4.2 コーヒーの肝癌細胞増殖・浸潤・転移に対する作用
9.4.3 コーヒー成分と肝癌細胞の増殖・浸潤抑制作用
9.5 おわりに
10. パパイア(中村宜督)
10.1 はじめに
10.2 パパイアに含まれる栄養機能成分
10.3 抗酸化物質と解毒酵素誘導物質
10.4 パパイアに含まれ覯鯑嚢攸罵尭格?颯戰鵐献襯ぅ愁船?轡▲諭璽?
10.5 応用と展望
第2章 動物系
1. 発酵乳(細野明義)
1.1 歴史と種類
1.1.1 歴史
1.1.2 種類
1.2 発酵乳の栄養・保健効果
1.3 ガン予防効果
1.3.1 発酵乳の抗変異原性
1.3.2 乳酸菌菌体の変異原生物質への結合
1.3.3 抗腫瘍作用
2. プロポリス(熊澤茂則)
2.1 はじめに
2.2 プロポリスに含まれる成分
2.3 プロポリスの生理活性研究の現状
2.3.1 抗酸化活性
2.3.2 抗菌活性
2.3.3 抗腫瘍活性
2.3.4 臨床治療への応用の現状
3. イカスミ-イカスミ食品とイカスミ抗腫瘍活性成分の最近の研究
(松江一,奈良岡哲志,内沢秀光,高谷芳明)
3.1 はじめに
3.2 伝統的イカスミ食品
3.3 イカスミブームが契機となって開発された食品
3.4 今注目されているイカスミ食品
3.5 イカスミの抗腫瘍活性の本体探索の歴史
3.6 イカスミ抗腫瘍活性画分のイレキシンペプチドグリカンとチロシナーゼ活性の関係
3.7 イカスミ抗腫瘍活性画分の疎水クロマトグラフィーによる画分
3.8 イカスミ抗腫瘍活性画分のチロシナーゼ活性
3.9 イカスミ分画物の抗腫瘍活性
3.10 イレキシンペプチドグリカンとチロシナーゼの抗腫瘍活性と相互作用
3.11 最後に
4. ラクトフェリン
(津田洋幸,深町勝巳,大嶋浩,飯郷正明,高須賀信夫,松田栄治,関根一則,大久保重俊,神津隆弘,島村眞里子)
4.1 がん予防の必要性
4.2 がん予防物質の作用機序-医薬と天然由来物質―
4.3 ウシラクトフェリンとは
4.4 ウシラクトフェリン(bLF)の動物におけるがん予防作用とその機序
4.1.1 ポストイニシエーション期投与
4.1.2 イニシエーション期投与
4.5 まとめ
5. アスタキサンチン(細川雅史,田中卓二)
5.1 はじめに
5.2 動物実験におけるアスタキサンチンの発癌抑制作用
5.3 アスタキサンチンの抗腫瘍作用
5.4 アスタキサンチンの癌転移抑制作用
5.5 アスタキサンチンの癌抑制機構
5.6 アスタキサンチンの安全性
5.7 おわりに
目次
第1編 概論(がん予防食品の開発の現状と動向;がん予防科学の動向と今後の展開 ほか)
第2編 基盤研究(疫学からみたがん予防―食品成分・食習慣改善によるがん予防の可能性;がん予防食品因子とデータベース ほか)
第3編 成分・素材(硫黄化合物;カロテノイド ほか)
第4編 新しい機能食品(植物系;動物系)
著者等紹介
大沢俊彦[オオサワトシヒコ]
名古屋大学大学院生命農学研究科応用分子生命科学専攻食品機能化学研究室教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。