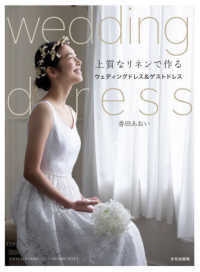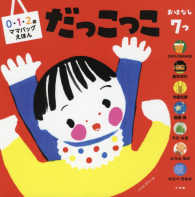出版社内容情報
☆高分子学会ゲル研究会のメンバーが中心となって纏めたゲルの一大成書。
☆様々な分野において使用されているゲルの詳細。
☆実際にゲルを『つくる』事と『みる』事に関し,その応用である『つかう』事を含め各項目毎に解説。
【はじめに】
約150年前のゴムの硫化(架橋)現象の発見は,自動車産業の隆盛をもたらし,さらには他の分野の産業のあり方を一変させた。ゴムはまさしく形状記憶という機能性高分子ゲルである。イオン交換樹脂は,半世紀以上の歴史をもつ機能性高分子ゲルである。当初は発電所や工場のボイラー給水処理などに用いられていたが,現在では食品,医薬,触媒,さらにはLSI製造に不可欠な超純水の製造などに広く用いられている。1960年代に開発されたHEMAと呼ばれているソフトコンタクトレンズも最近,その基本特許が切れるまでチェコアカデミーの財政を支えてきたヒット商品である。このように機能性ゲルは一旦,社会に受け入れられると非常に長い寿命をもつ材料である。1970年代に生まれた高吸水性樹脂も例外ではない。これらに加えて,近年,芳香剤,整髪料,インク,吸水剤など,ゲルという名の付く日用品が多く現れるようになった。これらはゲルの持つ保水性や薬品保持能,徐放性などを生かした商品で,ゲルの高付加価値化が進んでいる。
ゲル研究は1940年代のFloryやStockmayerのゲル化の理論に始まると考えられるから,日本の高分子研究の歴史そのものとほぼ重なる。ゲル研究の特徴は,高分子科学の中においても,合成,構造,物性,応用,といった非常に幅広い分野にまたがること,さらにはソフトマターとしての物性物理から,高分子加工,生物学,医・薬学,食品科学などにも深くかかわる学際領域的色彩ももっているところにある。特に,ここ20年ほどのゲル研究の歴史は,高吸水性ゲルの開発から,体積相転移,刺激応答を利用した基礎・応用研究に総括される。
このように学問的にも応用面でもゲルに対する関心が深まる中,新しい概念や分子設計に基づく新規ゲルの創成が相次ぎ,これまでには実現が難しいとされていたスーパーゲルが次々と開発されつつある。たとえば,ゲルとは思えないほど強靱な高強度ゲル,驚くほど摩擦係数が小さい低摩擦ゲル,大容量電池・キャパシタ用電解質ゲル,化学薬品や生体物質に鋭敏に応答する環境応答性ゲル,多量の有機溶媒を固化するオイルゲル化剤など,枚挙にいとまがない。さらに,ゲルのナノファブリケーションに基づく高性能センサーゲル,キラル選択性カラム充填剤,知的ドラッグデリバリーシステムなど,ますますゲル機能の進化が進んでいる。その一方で,ゲルの振動現象や選択分離能,運動などの研究は,生物機能の再構築をめざす意味で,次世代の高機能性ゲルや知的ゲルへのブレークスルーとも考えられる。
このような状況下,ゲル研究の第一線で活躍している高分子学会ゲル研究会を中心としたメンバーにより,高分子ゲルの最新動向をまとめた成書を出版することとなった。本書の特徴は,これまでの解説書で多く取られていた,基礎編と応用編と分けるのではなく,各章の著者が研究のバックグラウンドを説明する「つくる,みる」の部と,それを応用した最新動向の紹介「つかう」部から構成される形式を取っている。そのため,各トピックの最新動向について基礎から応用・発展まで把握することが容易にできる。その一方,「ゲルの科学」に必要な化学,物理学,材料学,食品科学,薬学,医学などの広い学問領域にわたる知識を各章の「つくる,みる」部に配置した。つまり本書は,ゲルの科学的基礎を「縦糸」に,高付加価値ソフトマテリアルとしての高分子ゲルについての最新動向(「つかう」)を「横糸」とした実用性の高い技術書である。この本から新たな長寿命ヒット商品となるゲルが一つでも開発されることを祈念している。
2004年2月 第10期高分子学会ゲル研究会委員長(2002~2004) 東京大学物性研究所 柴山充弘
第4期高分子学会ゲル研究会委員長(1992~1994) 大妻女子大学 梶原莞爾
【執筆者一覧(執筆順)】
柴山充弘 東京大学 物性研究所 中性子科学研究施設 教授
梶原莞爾 大妻女子大学 家政学部 被服学科 教授
青島貞人 大阪大学大学院 理学研究科 教授
金岡鐘局 大阪大学大学院 理学研究科 助教授
杉原伸治 大阪大学大学院 理学研究科 日本学術振興会 特別研究員
;現 福井大学 工学部 助手
川口春馬 慶應義塾大学 理工学部 教授
英 謙二 信州大学大学院 工学系研究科 教授
鈴木正浩 信州大学大学院 工学系研究科 助手
青木隆史 京都工芸繊維大学 繊維学部 高分子学科 助教授
Gong Jianping 北海道大学大学院 理学研究科 教授
原口和敏 (財)川村理化学研究所 理事
伊藤耕三 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授
桜井敬久 (株)ジェルテック 取締役 開発部長
宮田隆志 関西大学 工学部 教養化学 助教授
青柳隆夫 鹿児島大学大学院 理工学研究科 ナノ構造先端材料工学専攻 教授
平谷治之 (株)メニコン 基礎研究部
吉井文男 日本原子力研究所 高崎研究所 材料開発部 環境機能材料研究グループ グループリーダー 主任研究員
足立芳史 (株)日本触媒 吸水性樹脂研究所 研究員
光上義朗 (株)日本触媒 吸水性樹脂研究所 研究員
大本俊郎 三栄源エフ・エフ・アイ(株) 第一研究部 ハイドロコロイド研究室 課長
池田新矢 大阪市立大学大学院 生活科学研究科 食・健康科学講座 助手
金田 勇 (株)資生堂 マテリアルサイエンス研究センター 副主任研究員
竹岡敬和 名古屋大学大学院 工学研究科 物質化学専攻 助教授
明石量磁郎 富士ゼロックス(株) 研究本部 先端デバイス研究所 主任研究員
吉田 亮 東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻 助教授
古川英光 北海道大学大学院 理工学研究科 生物科学専攻 助教授
浦山健治 京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻 講師
西成勝好 大阪市立大学大学院 生活科学研究科 食・健康科学講座 教授
安藤 勲 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻 教授
黒木重樹 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻 助手
兼清真人 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻 研究員
小泉 聡 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻
山根祐治 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻
上口憲陽 東京工業大学大学院 理工学研究科 物質科学専攻
【構成および内容】
第1編 つくる・つかう
第1章 環境応答
1.温度応答性ゲルの合成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 青島貞人,金岡錘局,杉原伸治
1.1 序
1.2 温度応答性ポリマーおよびゲルの合成(LCST型)
1.2.1 NIPAMポリマー系
1.2.2 オキシエチレン側鎖を有するビニルエーテルポリマー
1.2.3 その他の温度応答性ポリマー,ゲル
1.3 温度応答性ポリマーおよびゲルの合成(UCST型)
1.3.1 有機溶媒中でのUCST型相分離を利用した刺激応答性ゲル
1.4 その他の刺激応答性ポリマーおよびゲル:まとめにかえて
2.微粒子合成・微粒子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 川口春馬
2.1 はじめに
2.2 物理架橋で形成されるゲル微粒子
2.2.1 ミセル
2.2.2 生態系のミクロゲル
2.3 化学架橋ゲル微粒子
2.3.1 化学結合で分子鎖が束ねられたミクロゲル
2.3.2 凝集後架橋して得られるミクロゲル
2.3.3 微粒子生成重合で得られるミクロゲル
2.4 ゲル粒子結晶
2.5 おわりに
3.オイルゲル化剤・ヒドロゲル化剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・27 英 謙二,鈴木正浩
3.1 はじめに
3.2 オイルゲル化剤
3.2.1 低分子化合物のオイルゲル化剤
3.2.2 アミノ酸系オイルゲル化剤
3.2.3 環状ペプチド型オイルゲル化剤
3.2.4 シクロヘキサンジアミン誘導体のオイルゲル化剤
3.2.5 双頭型アミノ酸誘導体のオイルゲル化剤
3.2.6 all-powerfulなゲル化能をもつオイルゲル化剤
3.3 ヒドロゲル化剤
3.3.1 アミノ酸誘導体のヒドロゲル化剤
3.3.2 糖を含むヒドロゲル化剤
3.3.3 その他のヒドロゲル化剤
4.キラルゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 青木隆史
4.1 はじめに
4.2 天然高分子ゲル
4.2.1 透明セルロースゲル(TCG)
4.2.2 微小な温度変化を電気信号に変換する糖タンパク質ゲル
4.3 合成高分子キラルゲル
4.3.1 不斉炭素を有する合成高分子からなるキラルゲル
4.3.2 不斉炭素を有する合成高分子からなる感温性キラルゲル(その1)
4.3.3 不斉炭素を有する合成高分子からなる感温性キラルゲル(その2)
4.3.4 へリックス構造を形成するキラル合成高分子が作るキラルゲル
4.4 おわりに
第2章 力学・摩擦
1.高分子ゲルの摩擦・低摩擦ゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・54 Gong Jianping
1.1 はじめに
1.2 固体の摩擦と流体潤滑
1.3 ゲルの滑り摩擦
1.3.1 ゲル摩擦の特異的な挙動
1.3.2 ゲル摩擦の吸着・反発モデル
1.3.3 理論モデルと実験との比較
1.3.4 表面自由鎖の摩擦低減効果
1.4 おわりに
2.力学:ナノコンポジットゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 原口和敏
2.1 はじめに
2.2 有機架橋ゲルの課題
2.3 ナノコンポジット型ヒドロゲル(NCゲル)の創製
2.3.1 NCゲルの合成とネットワーク構造
2.3.2 NCゲルの機能性
2.4 NCゲルの力学物性とその制御
2.4.1 NCゲルの力学的特徴
2.4.2 NCゲルの力学物理制御(その1)-有機/無機成分種による変化-
2.4.3 NCゲルの力学物理制御(その2)-ゲルの組成による物性制御-
2.5 おわりに
3.膨潤理論・トポロジカルゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 伊藤耕三
3.1 はじめに
3.2 ゲルの膨潤理論
3.2.1 Flory-Rhener理論
3.2.2 田中理論
3.3 トポロジカルゲル
3.3.1 トポロジカルゲルとは
3.3.2 環動ゲルの作成法
3.3.3 応力-伸長特性
3.3.4 小角中性子散乱パターン
3.3.5 準弾性光散乱
3.3.6 環動ゲルの応用
4.ゲルダンピング材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 桜井敬久
4.1 はじめに
4.2 防振
4.3 シリコーンゲルダンピング材の特徴
4.4 シリコーンゲルダンピング材の粘弾性
4.5 シリコーンゲルダンピング材の用途
4.5.1 各種防振材
4.5.2 複合型防振材
4.5.3 光ピックアップアクチュエーター用ダンピング材
4.5.4 ステッピングモーターダンパー
4.6 今後の課題
第3章 医用
1.生体分子応答性ゲルの合成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・114 宮田隆志
1.1 はじめに
1.2 生体分子機能を利用したグルコース応答性ゲル
1.3 完全合成系のグルコース応答性ゲル
1.4 抗原応答性ゲル
1.5 糖タンパク質応答性ゲル
1.6 おわりに
2.医用におけるゲル・医用,DDS応用 ・・・・・・・・・・・・・129 青柳隆夫
2.1 はじめに
2.2 バイオチップとハイドロゲル
2.3 生体適合性とハイドロゲル
2.4 再生医学用材料としてのハイドロゲル
2.5 生分解性材料を用いた医用,DDSのためのゲルの合成
2.6 DDSのためのゲル
2.7 おわりに
3.ソフトコンタクトレンズの物性と機能 ・・・・・・・・・・・・・140 平谷治之
3.1 はじめに
3.2 コンタクトレンズの分類
3.3 コンタクトレンズの物性
3.3.1 機械的強度
3.3.2 透明性
3.3.3 酸素透過性
3.3.4 表面親水性
3.4 最近のコンタクトレンズの開発動向
3.4.1 屈折矯正手術とカスタムメイドCL
3.4.2 遠近両用コンタクトレンズ
3.4.3 治療用ソフトコンタクトレンズ
3.5 おわりに
第4章 産業
1.放射線合成ハイドロゲルの応用 ・・・・・・・・・・・・・・・・150 吉井文男
1.1 はじめに
1.2 PVA,PEO及びPVPのハイドロゲル合成
1.2.1 固体,水溶液及び溶融相での放射線橋かけ
1.2.2 ハイドロゲルの創傷被覆材への応用
1.2.3 ハイドロゲルの多糖類添加効果
1.3 多糖類誘導体ハイドロゲル合成
1.3.1 ペースト状放射線橋かけ
1.3.2 多糖類誘導体ハイドロゲルの応用
2.高吸水性樹脂の用途展開 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
-農工業資材及び生分解性高吸水性樹脂の開発動向- 足立芳史,光上義朗
2.1 はじめに
2.2 高吸水性樹脂の製法と特性
2.3 衛生材料用途の吸水性樹脂
2.4 止水材(水膨潤ゴム・光ケーブル止水材・水のう)
2.5 低摩擦材料
2.6 加泥材・滑材・廃泥処理剤
2.7 空隙充填材
2.8 消火剤・耐火材
2.9 農園芸保水材
2.10 吸着剤
2.11 生分解性高吸水性樹脂の開発動向
2.11.1 多糖類
2.11.2 ポリアミノ酸
2.11.3 ポリビニルアルコールおよびポリエチレングリコール
2.12 おわりに
第5章 食品・日用品
1.食品(多糖類) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180 大本俊郎
1.1 はじめに
1.2 主な多糖類の製造方法
1.3 食品への応用のための多糖類の使用方法と効果
1.4 食品への応用例
1.4.1 増粘剤に使用される主な多糖類と食品への応用
1.4.2 ゲル化剤に使用される主な多糖類と食品への応用
1.4.3 安定剤に使用される主な多糖類と食品への応用
2.食品(タンパク質) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205 池田新矢
2.1 はじめに
2.2 つくる
2.3 つかう
3.レオロジー・化粧品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216 金田 勇
3.1 はじめに
3.2 レオロジー
3.2.1 流動性(粘性)
3.2.2 粘弾性
3.3 化粧品開発研究におけるレオロジーの活用
3.4 おわりに
第6章 光
1.ゲルを用いて光を操る~構造色ゲル~ ・・・・・・・・・・227 竹岡敬和
1.1 はじめに
1.2 構造色の発現メカニズム
1.2.1 光の性質
1.2.2 身近な構造色の例
1.3 構造色を示すゲルの作り方
1.3.1 オパール構造とその光学物性
1.3.2 逆オパール構造を有するゲルの調製
1.4 構造色を示すゲルの応用
2.光の吸収,反射・調光性材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・242 明石量磁郎
2.1 はじめに
2.2 調光性高分子材料
2.3 色素細胞と調光のしくみ
2.4 つくる(高分子ゲル調光材料の合成と評価)
2.5 つかう(高分子ゲル調光材料の応用検討)
2.6 おわりに
第7章 開放系としてのゲル-リズム運動 吉田 亮
1.開放系物質としてのゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251
2.ゲルの機能化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251
3.ゲルの運動機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252
4.開放系が生み出すゲルの時間的リズム ・・・・・・・・・253
4.1 外部環境とのカップリングによるゲルのリズム運動
4.2 ゲルの自励振動
4.2.1 周期的リズム運動を生み出す化学/力学共役システムの設計
4.2.2 振動リズムの制御
4.2.3 ゲルが生み出す蠕動運動
4.2.4 自励振動ゲルの微細加工によるマイクロアクチュエータ(人工繊毛)の作成
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260
第2編 みる・つかう
第8章 光散乱によるゲルの構造解析とジャングルジム状ポリイミドゲルの合成 古川英光
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
2.ゲルの動的光散乱に関する最新動向 ・・・・・・・・・・・265
2.1 光散乱の原理
2.2 希薄高分子溶液の光散乱
2.3 準希薄溶液・ゲル系の光散乱
2.4 不均一性をもつ化学架橋ゲルの静的光散乱
2.5 不均一性をもつ化学架橋ゲルの動的光散乱
2.6 逆ラプラス変換による緩和モードの解析
3.みる-ゲルの動的光散乱で測定できること・・・・・・・・271
3.1 網目サイズとその分布
3.2 静的不均一性
3.3 ゲル化点
3.4 臨界緩和現象
4.つかう-動的光散乱を活用した均一なポリイミドゲルの合成・・・274
5.まとめ-現状と今後の発展 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275
第9章 X線でゲルを見る:小角X線散乱によるゲル構造解析 梶原完爾
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・277
2.小角X線散乱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278
3.メチルヒドロキシプロピルセルロースの場合 ・・・・・282
4.有機無機ハイブリッドゲル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
5.糖鎖ゲルの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・289
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・295
第10章 中性子散乱 柴山充弘
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297
2.観る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297
2.1 中性子散乱の基礎
2.1.1 中性子
2.1.2 中性子散乱の測定原理と得られる情報
2.1.3 散乱理論
2.1.4 装置
3.使う:最新動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302
3.1 水溶性ブロック共重合体の物理ゲル化
3.2 放射線架橋ゲルと化学架橋ゲル
3.3 オイルゲル化剤
3.4 その他のゲル
3.5 おわりに
第11章 液晶ゲル・相転移挙動を中心として 浦山健治
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310
2.みる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310
2.1 液晶ゲルの合成
2.2 液晶ゲルのキャラクタリゼーション
3.つかう
3.1 液晶相転移に伴う液晶エラストマーの自発変形
3.2 液晶相転移に伴う液晶ゲルの体積相転移
第12章 熱測定・食品ゲル 西成勝好
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・319
2.ゲル-ゾル転移の熱力学的解析法 ・・・・・・・・・・・・・319
2.1 ジッパーモデル
2.2 多重架橋モデル
3.熱可塑性ゾル-ゲル転移の実験データ ・・・・・・・・・・322
3.1 ジェランガム
3.2 アガロース,ゼラチンゲルのゲル-ゾル転移のジッパーモデルによる解析
3.3 ポリビニルアルコールゲルのゾル-ゲル転移のジッパーモデルおよび田中プロットによる解析
3.4 その他の多糖及び蛋白質のゾル-ゲル転移
第13章 NMR 安藤 勲,黒木重樹,兼清真人,小泉 聡,山根祐治,上口憲陽
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
2.固体MMRによるアプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330
2.1 パルスNMR法
2.2 固体高分解能NMR法
3.磁場勾配NMRによるアプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・335
3.1 磁場勾配NMRによる自己拡散係数の解析
3.2 ゲル中の溶媒の拡散過程
3.3 ゲル中のプローブ分子の拡散過程とネットワーク構造
4.NMRイメージングによるアプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・339
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340
--------------------------------------------------------------------------------
-

- 電子書籍
- 私のことがスキすぎて死んじゃいそうな兎…