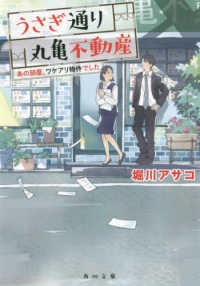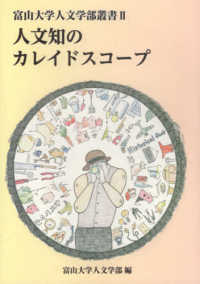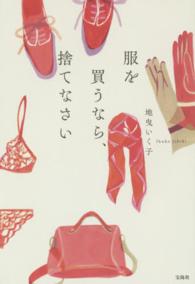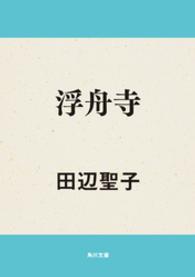出版社内容情報
両者が切り拓いてきた「対幻想論」「家族論」の領域を、「幼年」に焦点を当てることでさらに豊饒なものとするスリリングな対話。「こころ」「人類史」の新地平がみえる。
内容説明
自己史、子ども、家族のあり方、太宰、漱石などの文学作品、天皇制などを通して自在に語られる思想としての幼年。
目次
第1章 「幼年」とはいつのことか
第2章 乳房論
第3章 “吉本的性格”の幼年論的分析
第4章 「初期」―詩と隅田川
第5章 きょうだい論へ―「九州的」な吉本家
第6章 太宰治、夏目漱石、そして天皇の家族
第7章 「きょうだい」論の深部
第8章 「親しい」とはどういうことか―『彼岸過迄』と『行人』
第9章 女系論
著者等紹介
吉本隆明[ヨシモトタカアキ]
詩人、評論家。1924年東京生まれ。1947年東京工業大学理学化学科卒
芹沢俊介[セリザワシュンスケ]
評論家。1942年東京生まれ。1965年上智大学経済学部卒
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
のん@絵本童話専門
1
幼年期の軒遊びの勉強のために。1〜3章とあとがきのみで十分でした。乳児期の家遊びから群れ遊び・外遊びへ移行する中間の時期に、軒遊びは位置する。幼年期の子は家事をしながら傍にいてくれる母の存在を感じることで、安心して一人遊びができる。2000年代以降は早期教育により、存在することだけでは許されず何かすることを求められるように。母が苦悩して育児した程度でも性格の形成に影響を及ぼす。幼年期は重要、この時期の育ち方がよければ一生もの朗らかさが得られるとまで述べられている。柳田国男『分類児童語彙』も今読んでいます。2021/07/02