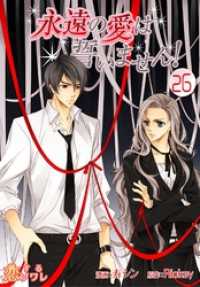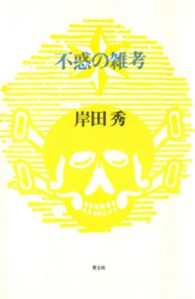出版社内容情報
病院や施設で理学療法士が実際に行っているリハビリテーションの専門技術を家庭でできるように詳しく図解。寝たきり予防に。
老化によって起こる骨折、病気やケガの後遺症によるマヒなどが原因になって寝ついたままになってしまうことがあります。本来なら動ける能力を持っている人が、いつのまにか寝たきりになってしまう場合が多いのです。つまり、寝たきりになる原因はそのほとんどが作られているといってよく、ならないためには退院後のリハビリテーションがきめ手となります。
◆本書の特長◆
●専門技術をわかりやすく図解
病院や施設で理学療法士が実際に行っているリハビリテーションの専門技術を、ご家庭でできるように詳しく図解。
●寝たきりの生活から、外出ができるまで機能アップを目標にしたステップアップのリハビリテーション
●家庭でリハビリテーションをおこなうときに利用できる介護・介護予防サービスを紹介
介護・介護予防サービスを上手に使って、家庭でリハビリテーションを続ける介護保険の利用法を解説。
●著者はリハビリテーションの第一線で活躍している経験豊かな専門家
著者は理学療法士として障害者施設等で、多くの障害のある人のリハビリテーションを実際に指導してきた専門家。
あなたはどのタイプにあてはまりますか?
Aタイプ ベッドから離れることができない人の運動
Bタイプ ひとりでは起きあがりが難しい人の運動
Cタイプ 立ち上がりや歩くのが難しい人の運動
Dタイプ 歩くことができる人の運動
Step1 関節がかたくなるのを防ぐ!
(関節を柔らかくするリハビリテーション)
◆ひとりでおこなう運動
◆介助でおこなう運動
Step2 起きる、そして座ることをめざす!
(寝がえり・起きあがりのリハビリテーション)
◆寝がえり
◆起きあがり
Step3 気持ちよく「外出」をめざす!
(立ちあがり・車いす・歩行のリハビリテーション)
Step4 より活動的な毎日をめざす!
(ひとりで行う日常のリハビリテーション)
◆座っておこなう運動
◆運動のあとにおこなうストレッチ
(巻末)介護保険を利用して行う機能改善
【著者紹介】
神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 大学院保健福祉学研究科 リハビリテーション領域教授
内容説明
病院や施設で理学療法士が実際に行っているリハビリテーションの専門技術を、家庭で家族といっしょにできるように詳しく図解した、リハビリテーションのマニュアル。ベッドで寝がえりをおこなうリハビリテーションから、補装具などを使って自力で外出するまで、気がついたら「できることが増えていた」リハビリテーションの方法を解説。家庭でリハビリテーションをおこなうときに使える介護・介護予防サービスを紹介している。
目次
毎日少しずつでもからだを動かしましょう(ベッドから離れることができない人の運動;ひとりで起きあがりが難しい人の運動 ほか)
1 関節がかたくなるのを防ぐ!(指や手首の動きをよくする;ひじ・腕・肩の動きをよくする ほか)
2 起きる、そして座ることをめざす!(介助による寝がえり;ひとりでおこなう寝がえり ほか)
3 気持ちよく「外出」をめざす!(介助によるベッドからの立ちあがり;ひとりでベッドからの立ちあがり ほか)
4 より活動的な毎日をめざす!(指の曲げ伸ばし;肩を開き、わき腹と背中を伸ばす運動 ほか)
著者等紹介
隆島研吾[タカシマケンゴ]
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科理学療法学専攻、大学院保健福祉学研究科リハビリテーション領域教授。1956年長崎県生まれ。1978年東京都立府中リハビリテーション専門学校理学療法学科卒業。1998年玉川大学文学部教育学科卒業。2001年筑波大学大学院修士課程修了(リハビリテーション修士)。1978年より横浜市立大学医学部付属病院リハビリテーション科に20年勤務した後、1998年より川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎にて在宅リハビリテーションに従事。2005年神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科准教授、2012年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。