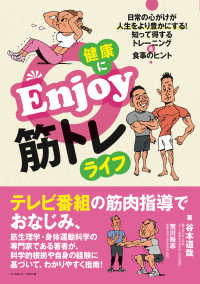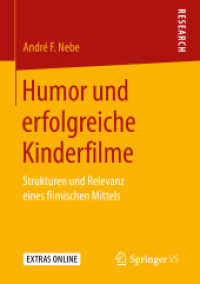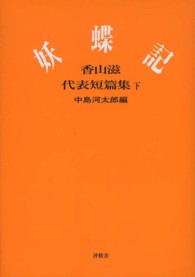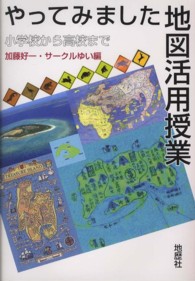内容説明
コッポラの「地獄の黙示録」の原作であると同時に、ポストコロニアリズム論にもしばしば登場する、二十世紀、英語圏諸国の大学で教材として最も多く使われた英文学屈指の名作、半世紀ぶりの新訳。原文対比の詳細な註釈、現代におけるこの小説の社会・思想的意味を鋭くえぐる小論考。本書をめぐる過去半世紀の膨大な研究・評論などを踏まえての緻密な2部構成の訳註、この小説がはらむ社会・思想的問いに焦点を絞った小論考「あとがき」にも注目。
著者等紹介
コンラッド,ジョセフ[コンラッド,ジョセフ][Conrad,Joseph]
1857‐1924。ポーランド出身のイギリスの作家
藤永茂[フジナガシゲル]
1926年満州国長春生れ。九州大学理学部物理学科卒。1968年からカナダのアルバータ大学教授、現在同名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
榊原 香織
90
英文購読でよく使われるイメージ。 全編差別用語みたいな。コンゴ暗黒時代。 映画”地獄の黙示録”の元らしい。 新訳なのだけど、文末訳注Ⅱで、旧訳の間違い指摘が英語併記でずらずらと。この訳者は物理学者。 訳者あとがきがかなり面白かった2024/07/02
藤月はな(灯れ松明の火)
51
光文社古典文庫を皮切りに岩波文庫版、長崎大学翻訳叢書版と読み比べながら読了。クルツの臨終の言葉は岩波文庫版と同じく、「地獄だ、地獄だ!」でした。この本を読むと原始から続き、社会性や宗教などの文化、倫理に埋もれつつも自分の中にある「闇」を見つめて囚われるような感覚に襲われます。自分を培ってきたものがあるきっかけで取り返しがつかない程、損なわれる現実と望みを叶えるために捨てるべきだが捨てきれないもの(自分を培ってきた道徳や社会文化など)との狭間で苦悩する魂に心がぐわん、ぐわんと揺さぶられます。2014/08/15
おさむ
46
英文学史上屈指の名作とされる本作品。アフリカのベルギー領コンゴにおけるレオポルド2世の大虐殺が主題ですが、私の脳裏に浮かぶのは、舞台をベトナムに置き換えたコッポラの映画「地獄の黙示録」の映像の方でした。マーロン・ブランドの怪演が思い出されます。文章としては難解でありながら詩的な表現も多く、20世紀に英語圏の大学で最も教材として多く使われたというのも納得(こんな文章、英語の試験で出たら泣きますけどね笑)。2016/06/19
キムチ
45
「読み人の数だけ評価がある」と言われるだけあると実感。闇の奥の奥は・・結局果てしなき業火に包まれた漆黒のopening ending コンラッドが長い船員生活の後に書いた「象牙とクルツ」に焦点化された作品だからこそその果てから浮かび上がってくる文明批評の複雑さはラスト武田氏の解説を読んで驚愕・・ここまで深いのかと。確かにマーロウの口を借りて語る饒舌すぎるほどの連弾批評に込められる複雑さは19,20Cと時を経る中でもコアの部分は変わらぬはず。我が国で4冊目の訳本となった苦慮も巻末に記されており興趣深い。 2016/07/23
白のヒメ
38
何故あるヨーロッパ白人がたった一人、アフリカのジャングルにおいて言葉も通じず、人肉を食らうような風習も価値観も違う野蛮な黒い現地人達に崇拝され、あり得ないほどの豊かな象牙をジャングルの外へ送り出すことが出来たのか。その人物はどういった人間だったのか。主人公はその人物を見極めにジャングルへと向かう。実際に作者のコンゴにおける体験を基にしたという。物語は曖昧模糊として霧に包まれているけれど、霧の向こうの深淵さは計り知れない。「The horror!The horror!」人生とは恐ろしいものだ。2014/11/15