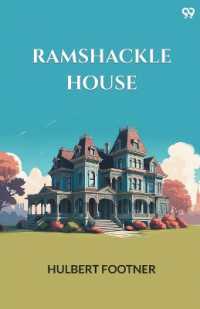出版社内容情報
新しく制定された弁護士職務基本規程踏まえて、刑事弁護人として、弁護活動上、最低限何をし、何をしてはいけないかを、設問を通して解説する。
◎目次 ハンドブック刑事弁護
刊行によせて i
刊行にあたって――本ハンドブックの成り立ちとその目的 ii
第1章 弁護人の基本的役割
総 論 3
第1 最善努力義務・誠実義務 8
1 最善努力義務 8
〔設問 1 〕弁護士偏在と最善努力義務 8
〔設問 2 〕頻繁な接見要求 15
〔設問 3 〕弁護人の個人的良心と最善努力義務 18
2 弁護方針と被告人の意向 22
〔設問 4 〕被告人の意思に反する弁護活動(金庫指紋事件) 22
〔設問 5 〕無罪主張と被害弁償等 28
〔設問 6 〕早期釈放のための被疑事実の自認
(事実に反する場合) 30
〔設問 7 〕心神喪失と正当防衛の主張(ボンボン虫事件) 32
〔設問 8 〕弁護方針が被告人と弁護人とで異なっている
場合の立証活動 36
〔設問 9 〕執行猶予期間経過を目的とする無罪主張 41
3 権利告知 48
〔設問10〕黙秘の勧めと不適切弁護 48
〔設問11〕黙秘の妥当性・取調べ立会・署名拒否 54
〔設問12〕余罪への対応・供述拒否 61
4 身体拘束からの解放 62
〔設問13〕身体拘束解放手続の履践と捜査妨害 62
〔設問14〕否認と身体拘束からの解放 67
第2 守秘義務 76
〔設問25〕任意同行されている被疑者との面会 126
〔設問26〕弁護人による証拠の収集と正当業務行為 131
第3章 受任
総 論 135
第1 受任時の留意事項 146
〔設問27〕報酬、預り金の説明・清算義務 146
〔設問28〕面識のない被疑者からの弁護依頼 151
〔設問29〕弁護費用の第三者提供 155
第2 複数当事者間の利害対立 163
〔設問30〕共犯者の同時受任 163
〔設問31〕共犯同時受任後の利害対立 169
〔設問32〕共犯者の同時受任(集団事件・費用・組合弾圧) 176
〔設問33〕顧問会社の従業員の弁護 182
第4章 接見交通権
総 論 187
第1 接見の留意点 193
〔設問34〕接見に赴くまでの留意点 193
〔設問35〕初回接見時の留意点 195
〔設問36〕接見時における弁護依頼者の開示要求への対応 197
第2 接見妨害 201
〔設問37〕捜査係員による接見妨害 201
〔設問38〕被疑者自身の接見拒否を理由とした接見妨害 203
〔設問39〕執務時間外を理由とした接見妨害 205
〔設問40〕検察官不在を理由とした接見妨害 211
〔設問41〕接見指定による接見妨害 21 266
〔設問52〕被疑者・被告人に対する捜査情報の提供と罪証隠滅 275
第3 捏造証拠の提出の回避 280
〔設問53〕合意と異なる内容の示談書の作成・提出 280
〔設問54〕偽造された証拠の提出(調理師免許のコピー) 282
第4 証人等の偽証・虚偽供述、あらたな犯罪の回避 286
〔設問55〕逃走資金提供者に関する身代り依頼の伝言 286
〔設問56〕虚偽のアリバイ証言 288
第5 参考人との面談 294
〔設問57〕参考人との接触と捜査妨害 294
〔設問58〕共犯者からの事情聴取 298
第6 記録の取扱い 304
総 論 304
〔設問59〕検察官が開示した証拠の謄写・差入れ・交付 313
〔設問60〕公判の記録の一般への公開・配布 319
〔設問61〕弁護人としての開示証拠の取扱い 321
第6章 保釈
総 論 327
〔設問62〕保釈手続に際しての留意事項 331
〔設問63〕保釈請求と同意・不同意、公訴事実の認否 340
第7章 公判
総 論 347
〔設問64〕訴訟遅延と弁護活動の対立 349
〔設問65〕勾留理由開示公判における陳述時間の制限 351
〔設問66〕証拠調べ請求の却下と翌々日の弁論期日の指定 353
〔設問67〕複数弁護人間の意見対立(独自の弁応・相談 389
第3 受任の範囲と留意事項 393
1 示談と被害回復 393
〔設問76〕国選弁護人の権限の範囲 393
2 報酬その他の対価の受領の禁止 394
〔設問77〕報酬その他の対価の受領(儀礼的品物)・私選切替え 394
〔設問78〕報酬その他の対価の受領(実費) 398
3 国選弁護事件における利害相反 401
〔設問79〕国選弁護事件における共犯者の同時受任 401
第4 関連事件への対応 404
〔設問80〕別件余罪への対応 404
〔設問81〕国選弁護事件の被告人からの民事事件等の依頼 406
〔設問82〕国選弁護人の執行猶予取消請求事件への関与 410
第5 判決後の国選弁護人の活動 414
〔設問83〕一審判決後の国選弁護人の権限と対応 414
〔設問84〕一審判決後の弁護活動 416
参考設問 419
刑事弁護関係の懲戒処分例一覧 444
その他の懲戒関連事件 449
参考文献 450
資料 465
弁護士の役割に関する基本原則 465
弁護士職務基本規程 468
弁護士倫理 478
刑事法廷における弁護活動に関する倫理規程 483
国費による弁護人の推薦等に関する準則 485
キーワード索引 487
コラム 刑事弁護ワンポイント
●刊行によせて
国費による被疑者弁護制度が発足し、裁判員による裁判が開始されることにより、刑事弁護のスキルアップがこれまで以上に要求されることは言うまでもありません。
これまで刑事弁護の世界における技術の習得は、もっぱら刑事専門弁護士の「秘伝」ともいうべき技術をいかに個人的に習得していくかというレベルにとどまっており、弁護士集団が討論と相互批判を通じてスキルアップをはかっていくというものではありませんでした。
技術の向上のみならず、具体的事件において、そもそも刑事弁護を引き受けるべきか、また、刑事弁護人としてどこまでの弁護活動ができるのかといった疑問や悩みに直面しても、ABAの事例解説集のように、それに解答を与えてくれるものは存在せず、これも個人のレベルでの解釈・解決にとどまっていました。
このような状況を改善する立場から、日弁連刑事弁護センター刑事弁護実務研究小委員会の委員が中心となって、具体的事例をもとに、どのような弁護活動を行うべきかの指針を明らかにすべく精力的に検討を重ねてきました。その成果をまとめ、今回『ハンドブック刑事弁護』として、刊行されるに至ったものです。本書においては、具われわれが遭遇する問題は、その対処を誤ればたんに「誤った」だけで済まないことがある。弁護人の活動は、われわれ弁護士のためのものではなく、まずなによりも被疑者・被告人のためのものであり、当然のことながら、弁護活動の効果が良きにつけ悪しきにつけ被疑者・被告人に及ぶからである。そのように重大な問題をとり扱う職業に就きながら、われわれの近くには、さまざまな問題に遭遇したときに、どう考え、どのように対処すべきかをひろく検討した書物がなかった。
たしかに、これまで刑事弁護に関する書物やマニュアルあるいはパンフレットは数多く出版されてきた。最近では弁護人の倫理を説いた書物は少なくない。実際の弁護活動と裁判を素材に弁護技術を伝えようとする書物も多くある。日弁連もこれまで多くの研修会を主催してきた。さらに、弁護活動全般にわたるアクションプログラムを提起している。日弁連が主催した研修会における研究の成果なども書物になっている。日常の弁護活動や先輩同僚との交流に加えて、それらの書物を読むことによって、弁護活動上遭遇する諸問題に対処することはできるかもしれない。
しかし、弁護人が弁護活動の過程で遭遇するかもしれないさまざまな。
もっとも、すべての見解を等しく紹介してはいない。われわれは、「弁護人の最も基本的な責務は、被疑者・被告人の権利と利益を守ることことにある」という点で意見が一致していたからである。それゆえに、弁護人の職責をそのように理解していない前提に立つ見解を紹介する価値はないと判断した。そのような見解に価値があるとすれば、それは批判の対象としての価値があるにすぎないのである。
また、解説では、学問的な観点にも目を配ることを心がけつつ、主として実務的にどう対処すべきかについて説明を加えるようにした。
とはいえ、われわれは深い学識を有しているわけではない。そのため、解説には不十分なところや掘り下げの足らないところが多くあるであろう。また、できるだけ詳しく問題点を指摘すると同時に、多くの論点を網羅したいとも願ったことから、かえって中途半端な論述になってしまったところも少なくない。さらに、複数の執筆者が分担した結果、討議を重ねたとはいえ、解説の中に不統一や矛盾がみられるであろう。
このような本書の至らざるところは読者自身が補っていただきたい。そして、大いに議論していただきたい。
3 本書の成り立ちと執筆