出版社内容情報
現在の日本人は、人類史上最もバラエテイ豊かな飲酒生活を送っているのかもしれません。ビールをはじめ、TPOに合わせて日本酒、ワイン、焼酎、チューハイとさまざまなお酒を飲み分けて楽しんでいます。しかしかつては、お酒を飲む機会じたいが少なく、その種類も現在ほどのバラエテイはありませんでした。最初に経済発展と歩調を合わせて酒の日常化を進めて行ったのが「社用族」の酒。やがて1980年代に入ると新しい飲酒シーン開発のリーダーは女性層や若者層、つまりプライベートや家庭で飲む酒に移って行き、酒のバラエティ化に拍車をかけました。一方で、現代の飲み手の重大な関心事として健康との関わりも浮上して来ました。編者の「酒文化研究所」は、1991年に「人と社会にとってよい酒のあり方を考える」というテーマを掲げて創業し、このたび十周年を迎え、その記念企画として進めている「二十世紀の酒文化を考える」というプロジェクトの一環として生まれたのが本書です。豊かな食生活を送るためのパートナーとして知的好奇心を満たす対象としてお酒をとらえてみたい人にお薦めします。
内容説明
今、日本でいちばん伸びざかりの酒は?ポリフェノールが豊富な酒はワインだけ?ひとり暮らしの人に好まれる酒は?読めばわかる!酒に関するデータ集。
目次
第1章 二〇〇一年の酒トレンドを予測する(市場の動向を読む―低アルコール化と二極化がさらに進む!;酒は世につれ、人につれ―飲み手が酒をおもしろくする時代 ほか)
第2章 酒と健康を考える(マンガでわかる―酒と健康BOOK;ワインなら赤、ビールなら麦百パーセント―ポリフェノールの実力を拝見 ほか)
第3章 二〇〇一年の酒ライフスタイルを豊かに(新世紀はゆっくりいこう―スローフード、スロードリンクの時代へ;三低晩酌のすすめ―低塩・低糖・低カロリーが現代人を救う)
第4章 酒に関するデータ集(お酒の消費量;お酒への支出から見る酒ライフ ほか)
-
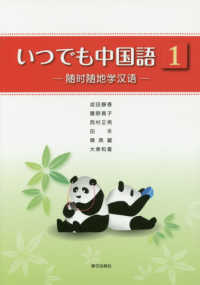
- 和書
- いつでも中国語 〈1〉






